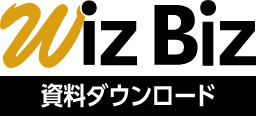お役立ちガイド
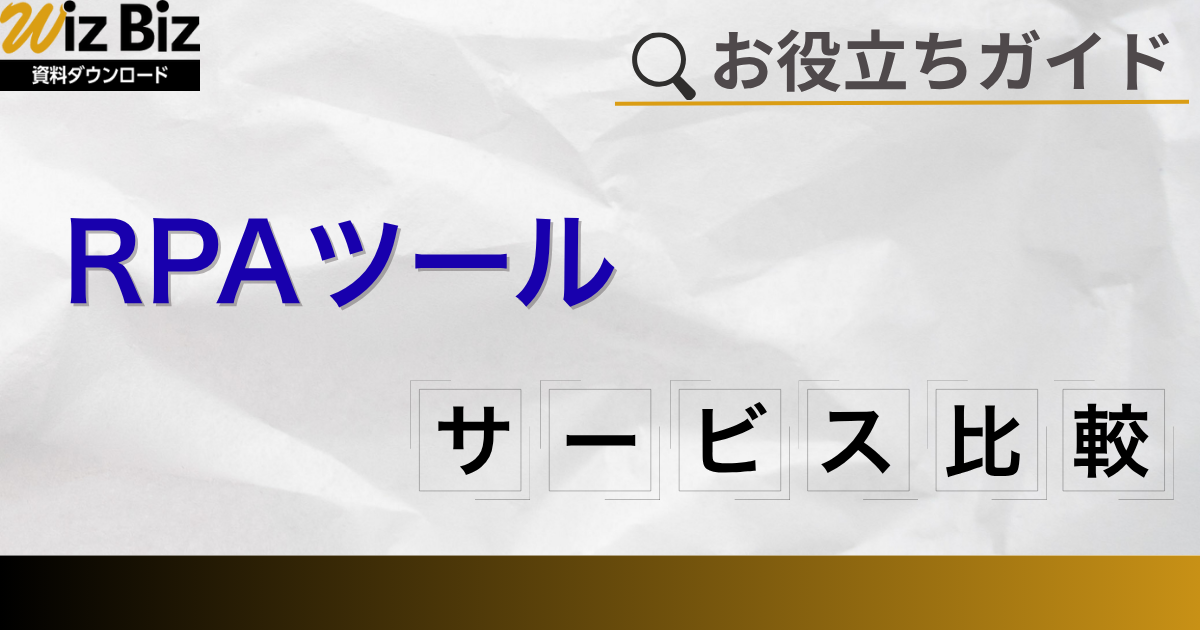
RPAの導入でお悩みの方へ。
RPAを導入すれば、レポート作成やデータ入力、集計といった単純作業を自動化することが可能です。最近では、AIとの連携機能を備えたものも少なくありません。
RPAは各社からさまざまな製品が展開されているため、導入する際には自社に最適なものを慎重に見極めることが重要です。
今回は、RPAの選び方やおすすめのツールを徹底解説します。導入のメリットや注意点なども深掘りするので、ぜひ最後までお読みください。
RPAツールとは?
RPAとは、繰り返し作業を自動化してくれるソフトのことです。人間とは異なり24時間365日いつでも稼働できるため、中小企業から大企業まで幅広く導入が進みつつあります。
スターティアホールディングスが実施した調査によると、RPAを導入している大企業の割合は2024年度時点で27.69%です。これは2023年度に行われた前回調査の24.78%から3%近くの増加であり、RPAツールの市場規模が徐々に拡大しつつあることが伺えます。
働き手不足の深刻化も相まって、RPAは今後ますます欠かせない存在となるでしょう。
決まったルーティン業務を自動化できるツール
RPAとは、人間が行う定型的な業務を代行してくれるソフトのことです。以前はプログラミングの知識がないと利用できないものが多かったですが、最近ではそうした専門知識を必要としないノーコード型のRPAも増えてきています。
RPAを使えば、以下のような業務を自動で実行することが可能です。
- 請求書や見積書の内容の転記
- 毎日同じ時間に特定のデータをダウンロードようなする作業
- メールの自動送信
- 定期的な報告書の作成
定期的に発生するルーティン作業は、RPAによる自動化が向いています。簡単な集計作業や報告書の作成も、RPAで自動化できることが多いです。
ただし、どんな業務でもRPAで自動化できるというわけではありません。例えば臨機応変な対応が必要な顧客対応は、RPAだけだと自動化しづらいです。あくまでも、決まったルールがある業務を効率化するツールだと理解しておきましょう。
異なるアプリ間をまたぐ作業でも対応できる
RPAツールの特徴は、複数のソフトやシステムをまたいだ業務の自動化ができる点です。例えば、以下の一連の業務をすべて自動化できます。
- Excelからデータを取得する
- そのデータをもとにブラウザからCRMシステムへ入力する
- 最後に結果をメールソフトで送信する
手作業だとソフト間で毎回データをコピーアンドペーストしなければいけませんが、RPAによる自動操作だとその手間がありません。
ちなみに、RPAとよく混同されがちなのが、Excelなどに付属しているVBAや、スプレッドシートなどに付属しているGASです。しかし、これらは基本的にそれぞれのソフトの中でしか処理を自動化できません。
ソフトをまたいだ業務の自動化が必要な場合には、RPAが向いています。
RPAツールには主に2つのタイプがある
RPAツールは「Attendedタイプ」と「Unattendedタイプ」の2つに分類されます。それぞれには特徴があるので、企業や業務の特徴に応じて、適切なタイプを選択することが重要です。
以下を参考にしてください。
| Attendedタイプ | Unattendedタイプ | |
|---|---|---|
| 特徴 | 人が操作しながら実行 | 完全自動で実行 |
| 導入コスト | 低め | 高め |
| 主な動作形態 | 個人のPC上で動作 | サーバーで一元管理 |
| 向いている業務 | 判断が必要な業務
例外処理が多い作業 |
定型的な作業
大量データ処理 |
| 主な課金体系 | ユーザー単位 | デバイス単位 |
Attendedタイプは、人の判断を必要とする複雑な業務や、例外的なケースが多い業務に適しています。社員がロボットと協業しながら業務を進めるため、「コールセンターでの顧客対応中に、必要な情報をRPAが自動取得する」といった使い方が可能です。
一方、Unattendedタイプは人間の介入なしに完全自動で動作します。夜間や休日を含めた24時間稼働ができるため、「複数のシステムをまたいだデータの転記を、オフィスの稼働時間外に処理する」といった使い方ができるでしょう。
なお、最近では両方をカバーしたツールも少なくありません。例えばAutomation Everywhereは、AttendedとUnattendedの両方のタスクを実行できます。
RPAツールでできること・改善できる業務
RPAツールは幅広い業務で活用できるツールです。RPAを導入すると、メール返信や勤怠状況の集計といった業務を自動化できます。発注書や請求書の自動作成も可能です。
反対に、臨機応変な対応が求められる業務はRPAの自動化に向きません。定型的な業務が自動化しやすいというポイントをおさえておきましょう。
メールの自動返信や営業メールの自動送信
メールの送信は、RPAによって自動化できる業務の代表例です。定型的な問い合わせに対する自動返信から、顧客情報に基づいた営業メールの個別送信まで、幅広く対応できます。
RPAによって自動化できるメール業務は、以下の通りです。
- 問い合わせメールへの自動返信
- 定期的な営業情報やニュースレターの配信
- メール内容の自動分析
- 担当部署への転送
- 顧客データベースと連携した誕生日メッセージの送信
昨今は、生成AIを使ってメールへの返信内容を個別に作成してくれるツールも増えてきています。問い合わせや取引先の数が多い大企業では、特に導入効果が高いでしょう。
勤怠状況の自動集計や給与の自動計算
勤怠管理や給与計算業務も、RPAの活用が進んでいる業務の一つです。従来は手作業で行われていた複雑な計算や集計作業を自動化することで、作業の効率化とヒューマンエラーの防止が期待できます。
RPAによる自動化が可能な業務は、以下の通りです。
- タイムカードデータの抽出と集計
- 残業時間の算出
- 各種手当や控除項目を含めた給与計算
- 給与明細の自動生成と配信
例えばWinActorでは、警備員の勤怠記録の確認作業を自動化し、15日かかっていた作業を1日まで短縮した事例があります。
在庫状況の自動管理や発注書の自動作成
物流や在庫管理は、RPAによって効率化できる業務の一つです。
RPAによって自動化できる物流や在庫管理業務としては、以下が挙げられます。
- 在庫データを定期的に取得する
- あらかじめ設定した数量に基づいて自動で発注する
- 入出庫データの転記
- 在庫記録の作成
「2024年問題」が指摘されている通り、物流業界では人手不足が深刻化しつつあります。RPAは24時間365日稼働できるので、人手不足の解消にうってつけです。
なお、物流や在庫管理ではWMSやWESといった、物流業務に特化したツールが使われていることがあります。RPAの導入時には、これらとの相性をよく確認しておいてください。
売上管理の自動化や請求書の自動作成
経理や財務部門でも、RPAによる業務効率化が進んでいます。売上データの集計から請求書の作成、入金確認まで、会計業務の多くを自動化することが可能です。
具体的には、以下が挙げられます。
- 販売システムからExcelに売上データを転記する
- 契約内容を契約管理システムから抽出して、Wordで請求書を自動生成する
- 入金状況を確認し、未入金の顧客へ督促メールを送信する
なお、上記の業務はERPやCRMでも自動化できますが、RPAでは既存システムを置き換えることなく自動化できる点が大きな魅力です。
例えばERPで自動化する場合は、請求書の作成や売上データの管理も原則としてERPへ一本化する必要があります。RPAの場合はさまざまなソフトを自動操作できるようになるため、既存のWordテンプレートやExcelのフォーマットをそのまま活用できるのです。
立替経費の自動精算
立替経費精算も、RPAで自動化できる業務の一つです。
具体的には、以下のような活用方法があります。
- 領収書のデータをExcelへ転記する
- 費用項目ごとにデータを分類する
- 立替の承認フローを自動化する(メール送信など)
ちなみに、紙の領収書のデータをRPAで自動転記するためには、別途OCRと連携する必要があります。OCRとは、紙に印刷された文字や手書きの文字を自動で認識し、データ化するツールです。OCRによって領収書をデータ化し、それをRPAで転記するという流れになるため、両者の相性もよく確認しておきましょう。
RPAツールを比較する際にみるべきポイント
RPAツールを選定する際は、以下のポイントを意識することが大切です。
- 自動化したい業務に適した製品を選ぶ
- 自社の予算や規模にあった製品を選ぶ
- サポートが充実している製品を選ぶ
まずは利用規模で大まかにツールを絞り、自動化したい業務に適したものを3〜5個程度選定することがおすすめです。その後、サポートの充実度合いや相見積もりの結果などを勘案して、実際に導入するツールを決めましょう。
どのような業務を自動化するかを明確にする
効率化したい業務を明確にすることが、RPAツール選びの第一歩です。自動化したい業務によって適したRPAは異なるため、まずは自社のルーティン業務をリストアップすることから始めてみてください。
RPAによる効率化が期待できる主な業務領域は、以下の通りです。
| 業務領域 | 具体例 |
|---|---|
| 経理・財務 | 請求書の作成、経費精算、売掛金の管理 |
| 人事 | 勤怠データの転記、給与計算、採用書類の管理 |
| 営業 | 受注データの入力、見積書の作成 |
あらかじめ自動化したい業務内容をリストアップしておくと、見積もりの際の商談もスムーズになります。上記の表を参考にしながら、業務領域ごとに自動化したい内容を列挙してみてください。
自社の予算に合ったRPAツールかどうかを比較
RPAの導入を検討する際は、自社の予算にあったものを選ぶことが大切です。初期コストだけでなく、継続的なメンテナンス費用も含めて判断しましょう。
RPAの利用時には、初期費用と月額費用の2つが発生します。最低でも、それぞれ以下の金額が必要だと考えておきましょう。
- 初期費用……100,000円〜500,000円
- 月額費用……100,000円〜1,500,000円
月額費用に幅がある理由は、RPAの機能によって料金に振れ幅があるためです。例えばシンプルなデータ転記作業のみを自動化したい場合は、月額10,000円以下のRPAでも十分対応できるでしょう。例えばDeNAのCoopelは、月額5,400円から利用可能です。
一方、より大規模な業務自動化を目指す場合には、UiPathやAutomation Anywhereなどの本格的なRPAツールが視野に入ります。初期投資や運用コストは高くなりますが、例えばRPAによって社員1人分の業務が減るのであれば、月額100,000円のRPAツールでも十分採算は取れます。
人件費とのバランスも考えながら、自社の予算に最適な製品を選んでください。
AttendedタイプかUnattendedタイプかを比較
先ほども解説した通り、RPAツールには大きく「Attended型(有人型)」と「Unattended型(無人型)」の2種類が存在します。企業規模や業務に応じてどちらかが適切かは異なるため、自社にあったものを選ぶことが大切です。
以下のようなケースは、Attended型がおすすめです。
- 中小企業や部門単位でRPAを導入する場合
- コストを重視したい場合
- データ転記やレポートの作成補助など、簡単な業務を自動化したい場合
Attended型は人の介入が前提となるため、業務を完全に代替することをイメージして導入するとギャップがあるかもしれません。あくまでも「業務補助」という位置づけで考えておきましょう。
反対に、Unattended型を導入するべきケースは、以下の通りです。
- 大企業での導入や、全社的な導入の場合
- 大量のデータを処理する必要がある場合
- IT部門の体制が整っており、対応できる人材が十分に確保できる場合
- すでにある程度の自動化が進んでいる場合
Unatteded型は人の介入が必要ないため、業務を完全に自動化したい場合に向いています。ただし、Attended型よりも運用コストは高く、導入期間も長引く傾向があるため、基本的には中〜大企業での本格導入に向いていると理解しておいてください。
自社の業務に合った規模のRPAツールかを比較
自社の業務内容に適した規模のRPAツールを選択することで、RPAの効果を最大限に引き出すことができます。
規模ごとに、向いているRPAツールは以下の通りです。
| 従業員数 | 自動化がおすすめの業務 | おすすめのタイプ |
|---|---|---|
| 50名以下 | データ入力などのシンプルな作業 | Attended型 |
| 50名〜500名 | メール返信やデータの分析作業
簡単な条件分岐が伴う作業 |
Attended型 |
| 500名〜 | 大規模なデータ処理が必要な作業 | Attended型 / Unattended型 |
例えばDeNAのCoopelは月額料金が5,400円からと非常に安価なため、従業員数が少ない小規模な導入におすすめです。一方でOCEVISTASのように、大規模な企業での導入に向いているものもあります。
キーエンスのRKシリーズや、株式会社FCEのロボパットDXなど、中小企業から大企業までオールマイティーに対応しているツールを導入することもおすすめです。
発行できるライセンス数やライセンスの共有範囲を比較
RPA導入の費用対効果を高めるためには、自社の利用方法に合ったライセンス体系の製品を選ぶことが重要です。
ライセンスタイプは、大きく「ユーザー単位」「ロボット単位」「従量課金」の3種類が存在します。それぞれの特徴と、向いているケースは以下の通りです。
| ライセンスタイプ | 特徴 | 向いているケース |
|---|---|---|
| ユーザー単位 | 利用ユーザーが増えるごとに課金される | 一人の社員が複数の業務を担当している場合 |
| ロボット単位 | ロボット数が増えるごとに課金される | 利用するロボットの種類が限られている場合 |
| 従量課金制 | ロボットの稼働時間が増えると課金される | 時期によってロボットの稼働時間が大きく変動する場合 |
ライセンスの共有範囲に関しては、1つのライセンスを複数の端末で共有する「フローティングライセンス」に対応しているか確認しましょう。フローティングライセンスに対応しているRPAであれば、複数のデバイスでアカウントを共有ができるため、利便性が高いです。
なお、公式にフローティングライセンスに対応していないツールの場合、「一つのアカウントに複数箇所からログインできない」などの制限があることも少なくありません。複数名でRPAを運用する場合は、フローティングライセンスが標準搭載されたものを選択することが無難です。
RPAツール導入時の初期設定やサポートの充実度を比較
RPAツールの導入を成功させるためには、サポート体制も比較しましょう。
RPAの導入時には、業務シナリオの初期設定を行う必要があります。業務シナリオとは、業務手順をまとめたRPAに対する指示のようなものです。
シナリオは慣れてきたら自社でも作成できますが、初めての場合はベンダー側にサポートしてもらうとよいでしょう。シナリオの難易度によって、10万円〜20万円程度の料金が発生することが一般的です。
運用時のサポートに関しては、以下をチェックしてください。
- エラーが発生した場合のサポートはあるか
- エンジニアの常駐はできるか
- 社員への研修を代行してもらえるか
例えばロボパットDXでは、導入企業ごとに一人ずつ個別の担当者がつき、専属でサポートを行っています。ベンダーのサポートとは別に、「RPAロボアシスタントサービス」のようなRPAの導入支援サービスを用いることも手です。こうしたサービスでは、RPAロボットの管理支援や作成代行などを依頼できます。
担当者がつくかどうか、24時間サポートがあるかどうかといったサポート体制はRPAツールによって差が出やすい部分なので、各ツールの特色をよく見極めてみてください。
RPAにとどまらない業務全体に対する提案が強みです。
機能の提供に注力している製品もあれば、コンサルタントのような立ち位置で深く業務レベルまで入り込んで伴走してくれる製品もあるため、各ツールの特色をよく見極めてみてください。
参考:niscom
おすすめのRPAツール比較10選
アシロボ

引用:アシロボ公式サイト
| 運営会社 | ディヴォートソリューション株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 月額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | 初期費用20万円+月額50,000円 |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
アシロボは、月額5万円(税別)で1契約につきPC2台までインストール可能なコストパフォーマンスに優れたRPAツールです。
IT部門に限らず、非エンジニアでも扱える直感的な設計が特徴で、最短90分で操作を習得できます。
導入時の研修や設定支援、運用開始後のフォローもすべて無償で提供されており、サポート体制も万全です。
さらに、インターネット環境がないオフライン環境でも利用できるため、セキュリティ要件の高い企業にも対応しています。
【アシロボの特徴】
- IT部門以外でも最短90分で習得可能
- OJT形式の操作習得
- 導入時や操作研修、導入後のフォローまで完全無償で提供
RoboTANGO

| 運営会社 | スターティアレイズ株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 月額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | 基本プラン:初期費用10万円+月額65,000円(1ライセンス) リモレクライトプラン:初期費用15万円+月額95,000円(1ライセンス) |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
RoboTANGOは、実際の操作を録画するだけでロボットを構築できるため、専門的な知識がなくても利用できます。
初心者にも扱いやすい直感的なUIが特徴で、初めてRPAを導入する企業でも安心です。
また、1ライセンスで複数台のPC間で共有できるフローティングライセンス方式を採用しており、柔軟な運用が可能です。
料金は月額65,000円(税別)からで、最低1ヵ月から契約できるため、スモールスタートにも適しています。
【RoboTANGOの特徴】
- 導入支援・操作研修・運用フォローまで対応
- 製造、EC、物流、宿泊、医療など幅広い業界で活用中
- 3週間の無料トライアルあり
WinActor

| 運営会社 | NTTアドバンステクノロジ株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 要問い合わせ |
| 料金(中小企業向け) | 要問い合わせ |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
WinActorは、純国産のRPAツールであり、国内シェアNo.1の実績を誇ります。すでに8,000社以上に導入されており、その信頼性と安定性から幅広い企業に選ばれています。
操作画面は直感的なドラッグ&ドロップ式で構成されており、エレメント(要素)ベースの設計により、非エンジニアでもスムーズに扱うことが可能です。
ライセンス形態も柔軟で、1台のPCに固定して使用するノードロックタイプに加え、複数のPCで共有利用が可能なフローティングライセンスも用意されています。
また、Excelやデータベース、OCRなどと連携できる豊富なライブラリが標準搭載されており、さまざまな業務に対応できる拡張性の高さも特徴です。
【WinActorの特徴】
- 純国産で高い信頼性
- NTTの特許技術を活用
- オンプレ・クラウド運用選択可
Microsoft Power Automate Desktop

引用:Microsoft Power Automate Desktop公式サイト
| 運営会社 | Microsoft Corporation |
|---|---|
| 料金形態 | 無料 |
| 料金(中小企業向け) | 無料 |
| 料金(大企業向け) | 無料 |
Power Automate Desktopは、Windows 10およびWindows 11ユーザーであれば無料で利用できるRPAツールです。
ユーザーの操作を録画するだけでロボットを作成できるため、プログラミングなどの専門知識がなくても扱いやすいのが特徴です。
また、UI要素の認識や画像・座標の指定、ファイル操作、Webアクセスなど、業務自動化に役立つ多彩なアクションを備えています。
有料プランを利用すれば、無人でのフロー実行にも対応可能です。
【Microsoft Power Automate Desktopの特徴】
- 無料で利用できる
- 豊富なアクションがありフロー作成が簡単
- アイコンをパズルのように組み合わせるだけで操作可能
ロボオペレータ

引用:ロボオペレータ公式サイト
| 運営会社 | 株式会社PKSHA Associates |
|---|---|
| 料金形態 | 月額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | 要問い合わせ |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
ロボオペレータは、実務担当者が自らロボットの作成・修正を行えるため、現場主導で小規模な業務から手軽に自動化を始められるRPAツールです。
導入時にはオンライン相談やサポートデスクの無償提供があり、安心して運用をスタートできます。
1ライセンスから1ヶ月単位で利用可能で、複数台のPCで共有も可能です。
さらに、1ヶ月間フル機能を試せる無料トライアルも用意されており、導入前に効果を確認できる点も魅力です。
【ロボオペレータの特徴】
- 現場主導の運用が可能
- 導入社数2,500社超、ライセンス7,000件稼働の実績
- 無制限のサポート体制
Coopel

引用:Coopel公式サイト
| 運営会社 | 株式会社Coopel |
|---|---|
| 料金形態 | |
| 料金(中小企業向け) | エントリープラン:初期費用0円+月額12,800円 スタンダードプラン:初期費用10万円+月額50,000円 アドバンストプラン:初期費用20万円+月額100,000円 ※価格はすべて税抜 |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
Coopelは、クラウド環境でもローカル環境でも柔軟に実行できるRPAツールです。
チュートリアルが用意されており、マウス操作だけで設定が可能なため、専門的な知識がなくてもすぐに使い始められます。
また、WebシステムとExcel間でのデータ転記にも対応しており、日常業務の自動化をスムーズに実現します。
導入前に機能を確認できる、30日間の無償トライアルも提供されているので、実際に使って自動化を試すことも可能です。
【Coopelの特徴】
- 申し込みから5分でトライアル利用可能
- クラウド型なので専用パソコンが不要
- エクセル操作にも対応
AUTORO

引用:AUTORO公式サイト
| 運営会社 | オートロ株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 月額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | Light:50,000円/月 Standard:100,000円/月 Pro:200,000円/月 ※価格はすべて税抜 |
| 料金(大企業向け) | – |
AUTOROは、ブラウザだけで利用できるクラウド型のRPAツールです。
操作はドラッグ&ドロップで直感的に行えるうえ、チュートリアルやアニメーションによるヘルプ機能も用意されており、初めての方でも安心して使い始められます。
また、導入後もチャットやメール、オンラインミーティングを通じた伴走型のサポート体制が整っており、安心して運用を継続できます。
さらに、外部APIや他のRPAツールとの接続はもちろん、Salesforceなどの業務システムとの連携実績も豊富で、さまざまな業務プロセスの自動化が可能です。
【AUTOROの特徴】
- 利用人数に合わせてプランを選択可能
- ブラウザ・アプリ・自社開発システムなどでも利用できる
- 即レスのチャットサポート
batton

引用:batton公式サイト
| 運営会社 | 株式会社batton |
|---|---|
| 料金形態 | 月額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | 148,000円(税込)/月 |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
battonはAIを搭載したRPAツールです。
AIが画面上の画像や解像度を自動で判別するため、異なるPC環境でも同じ操作を再現できます。
また、スマートフォンのような直感的な操作感で、キーボードだけでも簡単に扱えるシンプルでわかりやすいUI設計となっています。
ECや人事、経理、営業、飲食など幅広い業務への対応実績があり、1ライセンスで社内の複数PCに無制限で展開できる柔軟性も魅力です。
【battonの特徴】
- AI搭載のRPAツール
- 専任担当によるサポート
- リピート率97%
EzAvater

| 運営会社 | 株式会社テリロジーサービスウェア |
|---|---|
| 料金形態 | 年額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | フル機能ロボット ライセンス:75万円/年 実行専用ロボット ライセンス:20万円/年 ※価格はすべて税抜 |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
EzAvaterは、極めて使いやすさを重視して開発された国産のRPAツールです。
画面認識によって「目で見た操作」をそのまま覚えさせることができ、ITに詳しくない現場の担当者でも直感的に扱える設計となっています。
実際に、ユーザーの約70%が非IT部門での活用となっており、現場主導の業務自動化に適しています。
また、処理速度に応じて動作を自動調整する機能や、エラー時の通知機能が標準で備わっており、ロボットの想定外停止を防ぐ工夫もされています。
【EzAvaterの特徴】
- 操作の簡単さを重視した国産ツール
- ユーザーの約70%が非IT部門
- 2週間の無制限トライアル
UiPath
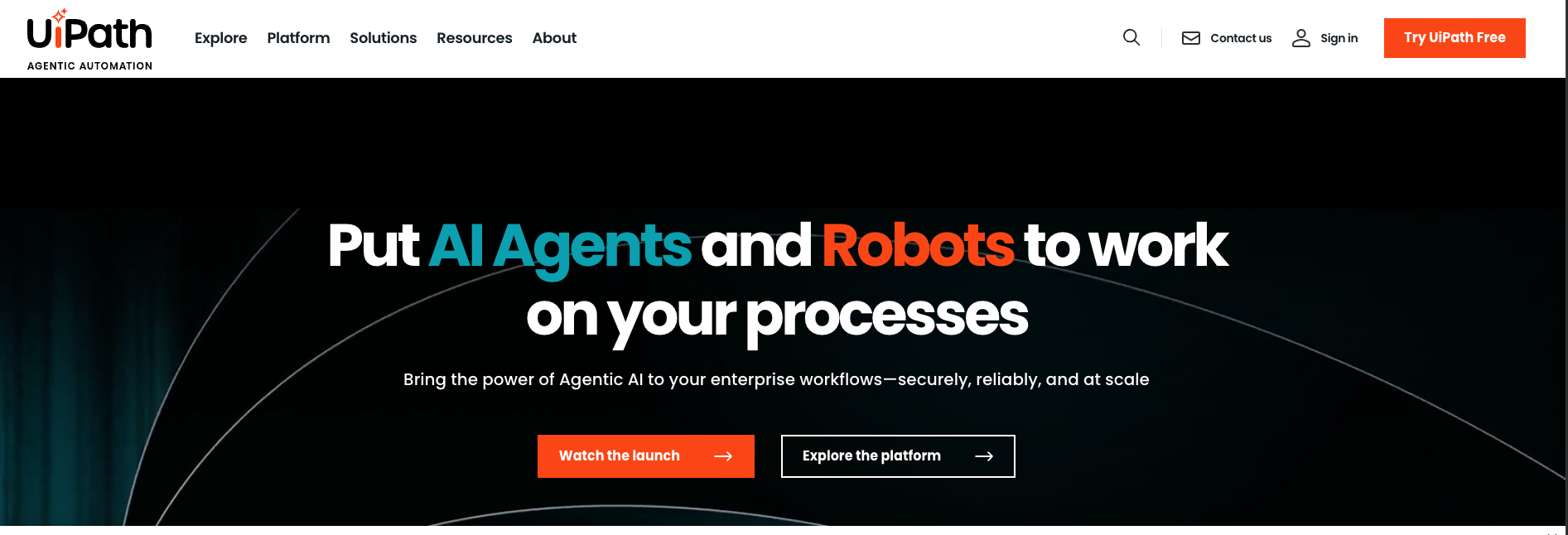
引用:UiPath公式サイト
| 運営会社 | UiPath Inc. |
|---|---|
| 料金形態 | 月額定額制 |
| 料金(中小企業向け) | 25ドル/月〜 |
| 料金(大企業向け) | 要問い合わせ |
UiPathは、初心者からエンタープライズ規模まで幅広く対応できるRPAプラットフォームです。
高度なセキュリティ対策やAIとの連携機能も備えており、業務の自動化を安全かつ高精度に実現します。
また、エージェント・ロボット・人間の役割分担をスムーズに統合できるワークフロー設計により、業務全体の最適化を支援します。
【UiPathの特徴】
- AIとの連携
- エージェント・ロボット・人間のスムーズなワークフロー
- UiPath Academy、認定資格、ユーザーコミュニティなど学習ツールが豊富
RPAツールを導入するメリット
RPAツールの導入には、多くのメリットがあります。業務効率の改善はもちろん、人件費の削減や人的ミスの防止も重要な利点です。また、場合によっては公的な補助金を活用できるかもしれません。
大企業から中小企業まで、RPAの導入によって恩恵を受けることのできる企業は多いです。
手動で行なっていた単純作業を自動化でき業務効率を改善できる
RPAツールの最大の魅力は、定型的な単純作業を自動化できる点です。データ入力やファイル操作、メール送信などの反復作業をロボットが代行することで、業務効率が大きく改善します。
総務省が公表している資料によると、ある大手都市銀行ではRPAの導入によって年間で8,000時間、約1,000日分の業務が削減できたそうです。
定型業務が効率化すれば、社員はより生産性の高いコア業務へ集中できるようになり、企業全体の競争力向上にもつながります。単純な繰り返し作業から解放されるため、社員の精神的負担も軽減できるでしょう。
手動作業にかかっていた人件費を削減できる
RPAツールを導入することで、人件費を大幅に削減できます。
RPAはビジネスツールの中でも比較的高額な部類ですが、その分削減できる人件費も大きいです。例えば前述した大手都市銀行のように年間で8,000時間分の事務作業を軽減できた場合、以下のように4人分の業務を削減できた計算になります。
- 社員1人あたりの1年間の稼働時間:8(時間)✕ 約250(日)=約2,000時間
- RPAが1年間でこなす業務量:8,000時間÷2,000時間=4人分
事務職の社員を1人雇用するためには、最低でも年間500万円必要だと言われています。つまり、RPAによって年間で2,000万円程度の人件費を削減できている計算です。仮にRPAを月額50万円で運用したとしても、年間1,400万円程度のコストカットが見込めます。
企業規模や業務内容によって実際の金額は変わりますが、RPAが大幅な人件費削減につながることは間違いありません。
手動で作業することによる人的ミスを防止できる
人間が行う作業には、どうしても疲労やストレスなどによるミスが発生します。RPAツールは設定されたルールに沿って正確に作業を実行するため、こうしたヒューマンエラーが起こりません。
特に、財務会計などのお金が直接関わるような業務には、RPAの導入が向いています。実際、RPAはもともと金融業界で導入が普及したものでした。人件費や各種手当の算出、データの転記、請求書の作成などのミスが許されない業務は、RPAによる自動化を積極的に検討しましょう。
ツールによってはIT導入補助金をもらえる可能性もある
RPAツールの導入にはコストがかかりますが、IT導入補助金などを活用することで、負担を軽減できる場合があります。
IT導入補助金とは、その名の通りITツールの導入費用の一部を補助してもらえる制度です。RPAも対象となるケースが多く、補助率は最大で導入費用の2分の1となっています。
詳細は年度によって異なりますが、大まかな要件は以下の通りです(2025年時点)。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 450万円(枠によって異なる) |
| 補助率 | 1/2以内(または2/3以内) |
| 対象企業 | 中小企業・小規模事業者 |
| 申請時期 | 年度ごとに複数回公募される |
| その他 | 生産性向上に関する計画の策定が必要 |
補助金を活用すれば、より高機能なRPAツールを導入したり、導入時の負担を軽減したりすることが可能になります。助成金の公式サイトでは補助金のシミュレーターも公開されているため、気になる方はぜひチェックしてみてください。
RPAツールのデメリット・注意点
RPAツールは業務効率化に役立つ一方で、導入時にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。
まず、自動化する作業内容によっては、予想以上の月額費用が生じる可能性がある点に注意が必要です。システムエラーなどが発生した場合には、人による対応が必要になります。さらに、RPAの導入や運用には一定のノウハウも必要です。
ツールの選定や運用計画を立てる前に、これらの注意点を十分に理解しておきましょう。
作業内容によっては月額費用がかさむ可能性もある
RPAツールの月額費用は、自動化する業務の複雑さや規模によって大きく変動します。複雑な業務の自動化では、予想以上にコストがかさむケースがあるため要注意です。
特に従量課金の場合は、事前の見積もりが甘いと予定以上の費用が必要になるケースが珍しくありません。また、シナリオやロボットの作成をベンダーへ依頼する場合は、難易度に応じて1件ごとに10万円〜20万円程度の料金が発生します。
月額費用を低くおさえるポイントは、以下の2つです。
- 自動化する業務を事前に明確化する
- 段階的に利用を拡大していく
自動化する業務をあらかじめ明確にしておけば、必要以上に高機能なツールを選ぶことがなくなります。また、まずは伝票処理や定型レポート作成などの反復作業から始め、効果を確認しながら徐々に拡大する方法もおすすめです。まずは1アカウントや1ロボット単位での導入を行い、効果があれば本格的に横展開していくとよいでしょう。
システムエラーなど予期しないトラブルには対応できない
RPAツールは設定されたルール通りに動作しますが、システムの変更やエラーに対して柔軟に対応することができません。
例えば以下のような些細なことでも、RPAの動作が止まってしまうケースがあります。
- 利用ソフトのアップデートによるUI変更
- ポップアップ画面の表示
- ルールの設定ミスによるシステムエラー
- ネットワーク障害によるタイミングのずれ
こうした問題に対処するためには、RPAの担当者を配置するなど、監視体制を整えておくことが大切です。夜間バッチ処理などを行う場合には、24時間体制も視野にいれましょう。
業務プロセスを細かく指定する必要がある
RPAを利用する際には、業務の進め方を細かく指定しなければいけません。
導入前に、以下を整理するように意識しましょう。
- 各業務の大まかな流れ
- 業務の開始条件と終了条件
- 条件分岐とそれぞれの対応フロー
- 考えられるエラーや例外、対応方法
RPAの導入は、IT部門が中心となって進めることも多いかと思います。現場とコミュニケーションを取りながら業務フローを丁寧に洗い出し、曖昧な点や疑問点を解消しておくことが大切です。
また、WinActorなど一部のRPAでは、典型的な業務フローを自動化するためのテンプレートを用意しています。RPA上で業務プロセスを構築する際には、こうしたテンプレートを活用することも手です。
RPAツールに対して的確な指示をするスキルが必要
RPAを最大限に活用するためには、システムに対して適切な指示を行うスキルも必要です。
特に、プログラミングの知識はほとんどのRPAで必須と言っても過言ではありません。RPAツールは、大きく以下の3種類に分かれます。
| 種類 | 特徴 | 代表例 |
|---|---|---|
| コーディング型 | コーディングの知識が必要なもの | WinActor、BizRobo! |
| ローコード型 | 一部、簡単なコーディングが必要なもの | Blue Prism |
| ノーコード型 | コーディングがほとんど必要ないもの | Automation Anywhere |
コーディングが必要なツールを導入する場合には、本格的なプログラミングの知識が必要です。WinActorではVBScript、BizRobo!ではJava形式でそれぞれシナリオを組みます。これらの言語での開発経験が必須というわけではありませんが、変数や関数、条件分岐などの基礎的なプログラミングの知識がなければシナリオの開発は難しいでしょう。
Blue Prismなどは、いわゆるローコード開発の部類です。ローコードのRPAではほとんどコーディングの知識が必要ありませんが、簡単な関数や式の入力が必要な場合があります。
Automation Anywhereは、視覚的なシナリオの作成が可能なノーコード型の一つです。プログラミングの知識は必要ありませんが、その分動作の自由度は限られます。
また、プログラミング以外にも以下のスキルが必要です。
- 論理的思考力
- データの処理スキル(CSV,Excelなど)
- ITリテラシー
こうしたスキルを兼ね備えた人材を育成するためには、多くの時間がかかります。初期研修でRPAの使い方を教えるようにするなど、必要に応じて人材育成と連携した施策も検討してみてください。
RPAツールの導入検討時によくある質問
ここからは、RPAの導入時に企業担当者の方からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。この記事の最後に、RPAに関する疑問点をまとめて解決していきましょう。
無料で利用できるRPAツールはありますか?
無料で利用できるRPAツールは複数存在します。例えば、以下のツールは完全無料で利用可能です。
- Automation Anywhere (Community Edition)
- AUTORO Assistant
- Power Automake Desktop
- UiPath Platform
- マクロマン
- UWSC
データの転記などシンプルな定型作業であれば、無料のツールでも対応できる場合があります。中でも、Automation AnywhereのCommunity Editionは、小規模事業者にぴったりな無料RPAの一つです。デバイス数や処理できるページ数には制限がありますが、事業規模が拡大した場合には有料版のAutomation Anywhereへスムーズに切り替えることができます。
また、AUTORO AssistantはGoogle Chromeの拡張機能としてリリースされているため、ブラウザ上での簡単な作業を自動化することが可能です。
このほか、ほとんどの人気RPAツールでは無料トライアルを用意しています。完全無料のRPAには機能制限がある場合がほとんどなので、本格的な導入を検討している場合には、はじめから有料ツールの体験版を利用することがおすすめです。
特定の部門に特化したRPAツールはありますか?
各部門の業務に特化したRPAツールも複数存在します。代表的なものは、以下の2つです。
| 部門 | ツール |
|---|---|
| 人事部門 | ILias |
| コールセンター | NICE Robotic Process Automation |
人事部門では、ILiasが人気です。給与や手当の計算の自動化機能が充実しているため、人事や経理部門の業務効率向上に役立つでしょう。コールセンター向けのものでは、NICE Robotic Process Automationが代表的です。電話対応中に発生するデータ入力や検索業務を自動化できます。
部門特化型のRPAを導入する最大のメリットは、導入がスムーズな点です。機能もシンプルなことが多いため、現場担当者に大きな負担をかけることがありません。
RPAツールの導入や運用は難しいですか?
RPAツールの導入や運用は、一般的なビジネスツールと同程度の難易度です。
ERPやCRMなどとは異なり、RPAは既存のツールを置き換えるわけではありません。既存のツールをそのまま自動化するため、場合によっては他のビジネスツールよりも簡単に導入できるでしょう。
ただし、いきなり本格的なコーディングが必要なツールを選定すると、十分に現場で活用されない可能性があります。特にIT人材が限られている中小企業では、ノーコードやローコードの製品の導入が無難です。
RPAツールの価格相場はどれくらいですか?
RPAツールの価格設定は導入規模や利用形態によって幅があります。中小企業向けの一般的な価格相場は以下の通りです。
| 初期費用 | 月額費用 | |
|---|---|---|
| クラウド型 | 100,000円〜500,000円 | 1ライセンスあたり5,000円〜20,000円 |
| デスクトップ型 | 1台あたり100,000円〜200,000円 | – |
| サーバー型 | 1,000,000円〜 | 100,000円〜 |
※従業員50名以下の企業での導入を想定
クラウド型の場合は初期費用がかからないと思われがちですが、RPAの場合はシナリオの作成もベンダーに合わせて依頼することが多いため、その際に100,000円〜500,000円程度の費用が発生します。
デスクトップ型の場合は、買い切り型のものが多いです。月額費用はかかりませんが、導入時に1台あたり100,000円〜200,000円程度の費用が発生します。サーバー型の場合は、メンテナンスを自社エンジニアで行うのか、外部委託するのかによって大きく費用が上下する点に注意しましょう。
RPAツールのまとめ
この記事では、RPAの基本機能、導入するメリットやデメリットなどを網羅的に解説しました。
最近は国内製・海外製問わず、さまざまなRPAツールが展開されています。月額1万円を切る手軽なツールも増えてきており、中小企業で導入を検討するケースも珍しくありません。
RPAの導入を成功させるためには、RPAによって自動化したい業務を明確化することがポイントです。その上で、自社の規模や予算にあったツールを選びましょう。中小企業の場合は、補助金の活用も忘れずに検討してみてください。
ぜひこの記事の内容を参考に、RPAによる業務効率化に取り組んでみてはいかがでしょうか。
SHARE
関連記事
-
2025年10月06日(月)
【2025年最新】ハラスメント社外相談窓口のおすすめ比較10選!外部委託の費用相場やメリットは?
- おすすめ

-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】決済代行サービスのおすすめ比較10選|機能・メリット・導入時の注意点まで徹底解説
- おすすめ
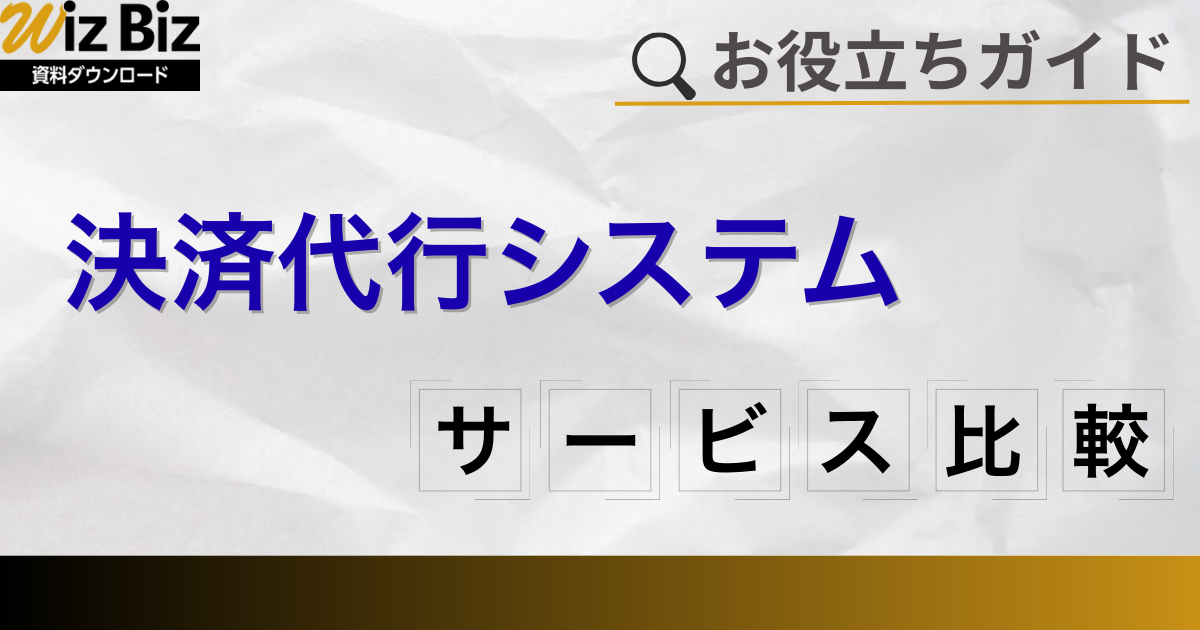
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】メール配信システムのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気のメール配信システムを解説
- おすすめ
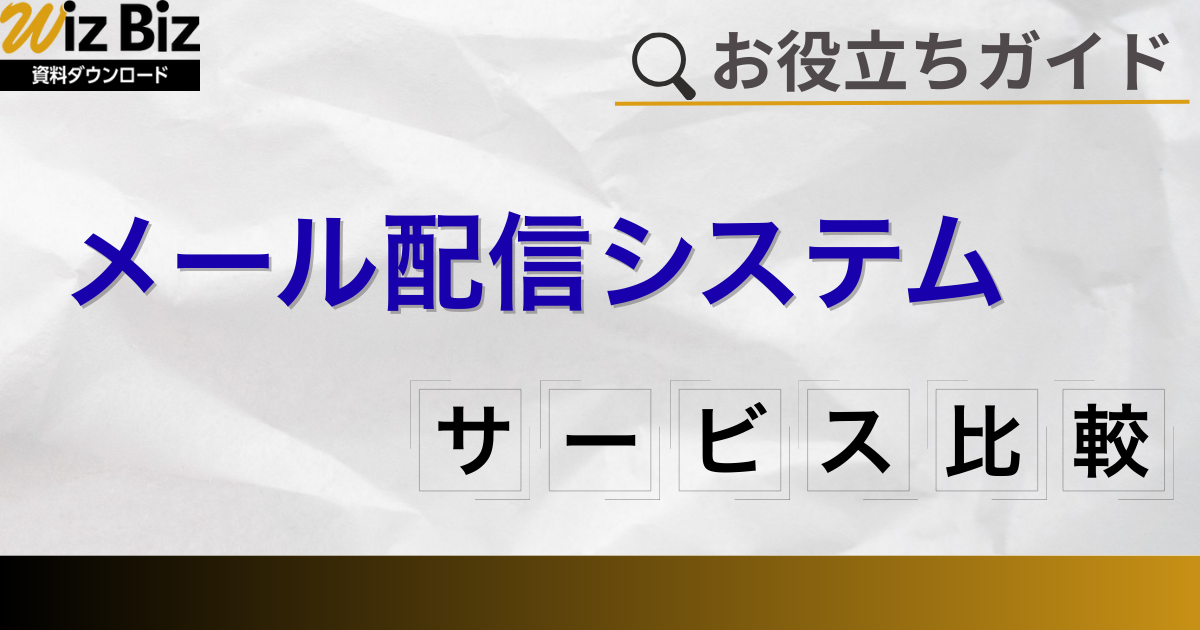
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】SFAツールのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気営業支援システムを解説
- おすすめ
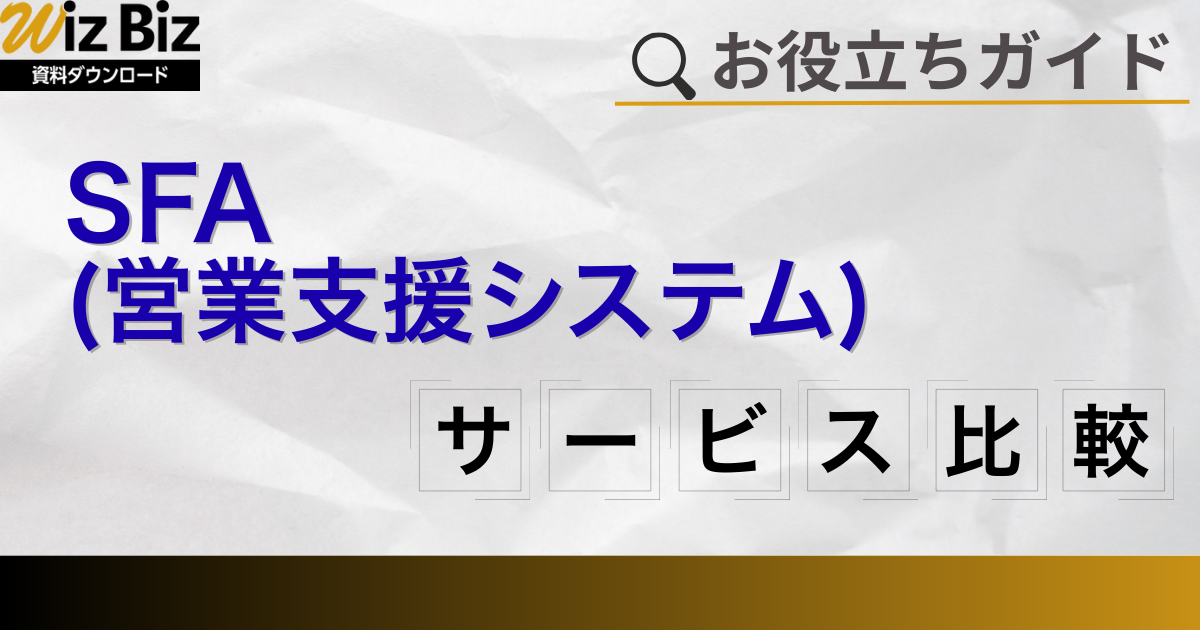
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】名刺管理ソフト・アプリのおすすめ比較10選|機能別・料金別で人気製品を比較!
- おすすめ
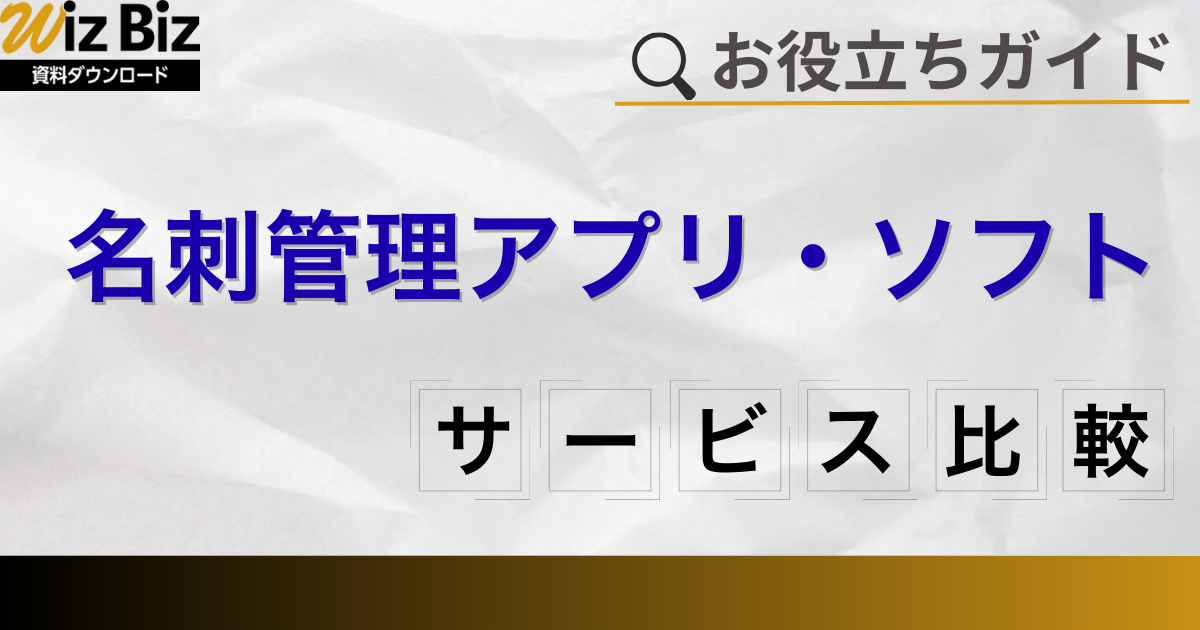
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】POSレジのおすすめ比較10選|業界別・機能別の人気POSレジやタブレット端末で使えるシステムは?
- おすすめ
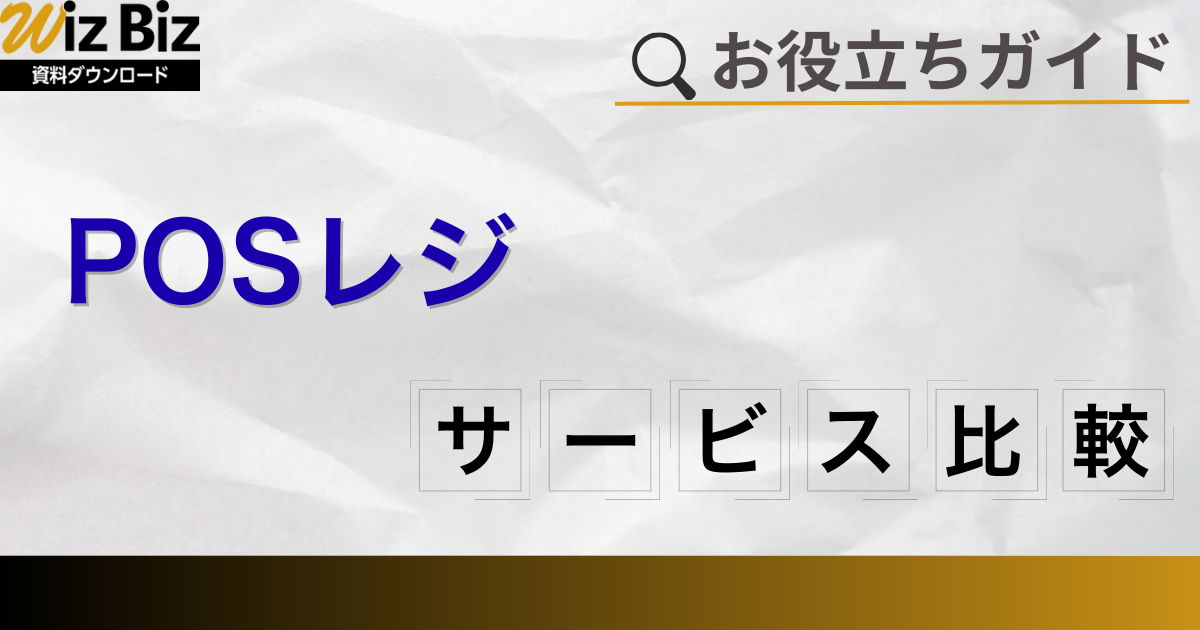
おすすめサービス
- 法人ガソリンカードのおすすめランキング比較!最強の給油カードを選ぶ方法や割引について詳しく解説!
- 一覧へ戻る
- CMSのおすすめ比較10選【2025年最新】簡単にWebサイトを構築できるCMSを料金・導入

ダウンロード候補に
追加しました!

削除しました