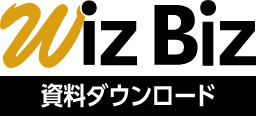お役立ちガイド
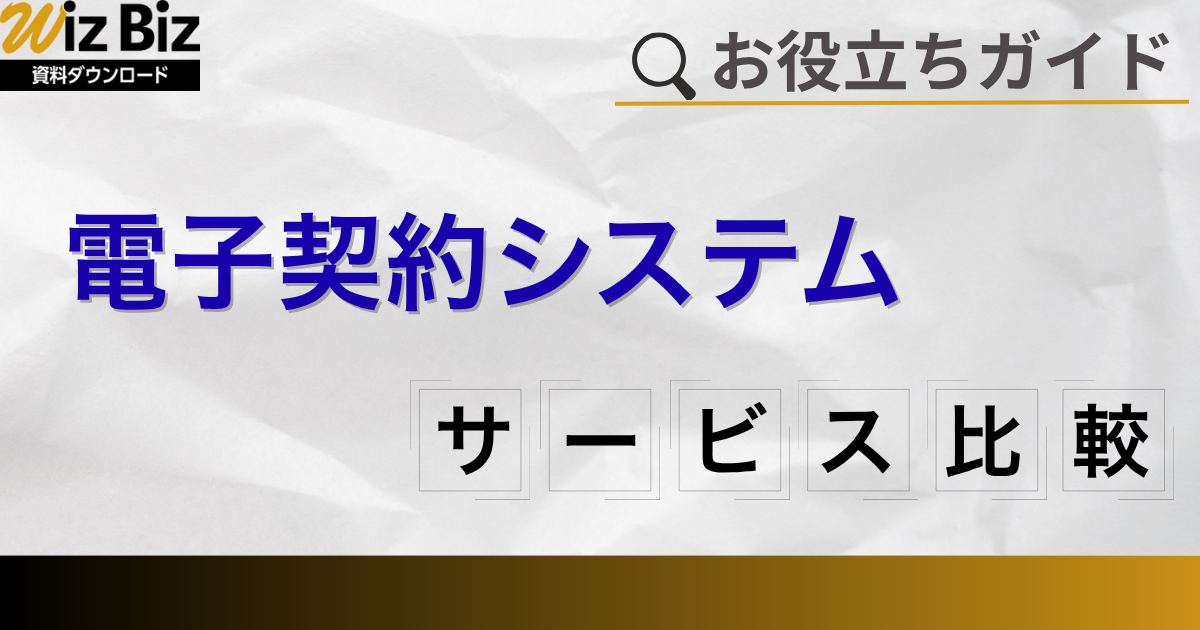
「先方まで出向くことなく、オンライン上で契約書を作成したい」
「電子契約に移行したいが、システムが多すぎて選び方がわからない」
こうしたお悩みをお持ちの方も多いでしょう。
最近では、紙の契約から電子契約への移行が進んでいます。
電子契約システムは、効率的に電子契約を締結するうえで欠かせない存在です。
しかし、昨今は多くの電子契約システムが乱立していることも事実。
システムによって機能や料金は微妙に異なるため、「自社の規模に最適なシステムを見極めることが難しい」と感じる担当者の方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、電子契約システムの基本的な仕組みや契約方法、システム比較のポイントなどをわかりやすく解説します。
おすすめの電子契約システムのランキングも紹介するので、ぜひ最後までお読みください。
【著者】新谷哲 WizBiz株式会社 代表取締役社長
経歴
|
電子契約システムとは?使い方は簡単?
電子契約システムとは、これまで紙で行われてきた契約をデジタル化することで、オンライン上での契約を可能にするシステムです。
主な機能はデジタル上での署名と契約締結ですが、中には契約書の保管や管理、更新通知といった機能を搭載しているものも存在します。
なお、2024年に行われた一般財団法人日本情報経済社会推進協会の調査では、実に77.9%の企業が電子契約システムを導入していることが明らかになっています。
電子契約システムは、あらゆる企業にとって欠かせない業務ツールの一つです。
電子契約システムの仕組み
電子契約システムは、デジタル上で契約を締結できるようにするシステムのことです。
以下のような仕組みで、オンライン上での契約締結を可能にします。
- 電子契約システム上で契約書を作成する
- 契約書のURLをメールやチャットツールなどで相手へ共有する
- 相手がURLを開き、署名や必要事項を記入する
- 契約の締結が完了する
電子契約システムを使うときは、まずシステム上で契約書を作成します。
手書きで必要事項を記入する必要はなく、テンプレートを用いて自動作成することが可能です。
また、印刷も必要ありません。
作成後は、オンライン上で契約書を相手方へ送付します。
契約書ごとにURLが発行されるシステムが多いので、このURLをメールやSlackなどで共有し、相手方が署名すれば契約締結は完了です。
ここまで、紙の契約書を印刷する必要は一切ありません。
また、電子契約システムは、ブラウザ上で署名できるものがほとんどです。
そのため、相手方が同じ電子契約システムを導入していなくても、オンライン上で契約を締結できる仕組みになっています。
使い方も非常にシンプルなので、初めてでも簡単に導入できるでしょう。
なお、電子契約システムによっては、過去に締結した契約書の一括管理機能が搭載されているものもあります。
これらは「契約書管理システム」と呼ばれることも多いです。
契約書管理システムについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
(ここに「契約書管理システム」の内部リンクの想定です!)
電子契約システムは官公庁や金融機関でも採用され始めている
最近では、電子契約システムが官公庁や金融機関などでも注目されつつあります。
例えば政府は、入札や契約などをオンライン上で行う「調達ポータル」を運用しています。
調達ポータルでは、調達に関わる契約締結をオンライン上で行うことが可能です。
また、金融機関でもローンや融資などの契約における電子化が進んでいます。
例えば三菱UFJ銀行では、住宅ローンの締結を電子化しました。
これまでは窓口などで対応していたため時間がかかりましたが、オンライン上だと待ち時間なしで手続きが完了します。
三井住友銀行も同様の電子契約システムを導入し、住宅ローンなどの契約締結をオンライン上で受け付けています。
また、「SMBCクラウドサイン」という電子契約サービスの自社展開も始めました。
これまでは「オンライン上の契約は信頼できないのでは」という考えもありましたが、最近では紙と同等の効力を持つ契約方法として、官公庁や金融機関にも広く信頼性が認められつつあるのです。
特定の業界に特化した電子契約システムも存在する
電子契約システムの中には、業界ごとのニーズに特化したサービスも増えています。
これらはそれぞれの業界ごとの契約書フォーマットや規制に対応しているため、複雑なカスタマイズなしでスムーズに導入できることが特徴です。
例えば、以下のような業界別システムが登場しています。
| 業界 | 特徴 |
|---|---|
| 医療向け | カルテなどと連携できる。 治療内容を動画やイラストで説明できる |
| 建設・不動産向け | 不動産契約書などのテンプレートが用意されている。 賃貸契約書などを法定保管期限に合わせて管理できる。 |
| 製造業向け | 部品供給契約やOEM契約などのテンプレートが豊富に用意されている。 海外との取引に対応している場合もある。 |
電子契約システムの導入が初めての場合や、その業界でしか使わないようなテンプレートを使って契約を締結したい場合は、こうした業界特化型システムの導入がおすすめです。
電子契約システムの主な機能
電子契約システムはさまざまな機能を搭載しています。
具体的な機能は、以下の通りです。
- ワークフロー
- テンプレートの登録
- 契約の管理やリマインド
- 契約書の保管や検索
オンライン上で契約締結できるだけでなく、オンライン上で契約書を検索したり編集したりできるので、従来よりも大幅に業務をスムーズに進めることができます。
社内稟議を進めやすくするワークフロー機能
電子契約システムには、稟議をスムーズに行うためのワークフロー機能が搭載されています。
契約の締結には、社内稟議が欠かせません。電子契約システムにはワークフロー機能が搭載されているため、オンライン上でスムーズに稟議を進めることができます。
ワークフロー機能の具体例としては、以下が代表的です。
- 承認ルートの管理
- 承認者ごとのコメントや差し戻し
- 担当者に対する通知やメールの配信
承認ルートの管理とは、書類ごとの承認ルートをシステム上で一括管理する機能のことです。
よく使う稟議のパターンや部門ごとの承認フローは、あらかじめシステム上へ登録しておくことができます。
また、複数の承認者がいる場合でも、誰がいつ承認したのかをリアルタイムで確認できます。書類に問題点があれば、承認者ごとにコメントを残したり、差し戻したりすることも可能です。
システムによっては、最後の承認者が承認した時点でメールを配信したり、通知したりできるものもあります。
契約書テンプレートの登録機能
電子契約システムには、契約書テンプレートをあらかじめ登録しておくことができます。
例えば、以下のような契約書はテンプレートを用いて作成することが可能です。
- 雇用契約書
- 業務委託契約書
- 有期雇用契約書
- 事業譲渡契約書
こうした一般的な契約書のテンプレートは、システム側ですでに用意されていることがほとんどです。
また、自社でしか用いないような契約書のテンプレートを作成したい場合は、オリジナルのテンプレートを作成することもできます。
テンプレートを活用すれば、定型契約書の作成にかかる工数を大幅に削減することが可能です。
また、日付などの基本事項はすべて自動で入力されるため、記入漏れや記入ミスなどを防ぐこともできます。
契約ステータスの表示機能
電子契約システムでは、契約の進捗状況をリアルタイムで表示できます。
契約書のステータス表示は、以下のような形式が一般的です。
| 契約書番号 | ステータス | 承認者 | 担当者 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| 1234 | 内部承認待ち | 田中・中村 | 鈴木 | 2025/02/24 12:15 |
| 1235 | 草案作成済み | ー | 佐藤 | 2025/02/24 13:15 |
| 1236 | 取引先署名待ち | ー | 佐藤 | 2025/02/24 15:32 |
上記のように、システム上からどの契約書が現在どのような状態にあるのかがひと目でわかります。
次に誰が作業するべきかすぐに把握できるので、担当者間の連携がスムーズになり、契約の締結が効率化するのです。
署名忘れのリマインド機能
電子契約システムには、署名や承認を忘れている際にリマインドが届く機能が搭載されています。
社内稟議では、「上長が押印を忘れていて、いつまでも稟議が進まない」といった事態が起こりがちです。
管理職が承認を忘れていたために、業務全体が滞ってしまうケースも珍しくありません。
電子契約システムには自動でリマインド通知やメールを送信する機能が搭載されているので、こうした遅延を未然に防ぐことができます
万が一上長が承認を忘れている場合も、わざわざデスクまで督促しにいく必要がありません。
電子契約書の保管や検索機能
電子契約システムでは、契約書を安全に保管できます。
また、過去の契約書から、目的のものを簡単に検索することも可能です。
内容にもよりますが、ほとんどの契約書は法律で3年〜10年程度の保管期間が定められています。
そのため、紙で契約書を管理しようとすると、過去の書類を保管するために膨大なスペースが必要です。
また、紙の書類の数が増えると、目的の契約書を素早く探し出すことは一層困難になります。
その点、電子契約システムでは過去の契約書をシステム上で一括管理することが可能です。
紙の契約書のように、地震や台風、火災などで汚損するリスクがありません。
また、検索機能が充実しているシステムでは、契約者や契約日、契約期間満了日などで絞り込んで、目的の契約書を素早く探し出すことも可能です。
最近では契約書の内容をもとに、AIが自動で契約書を分類してくれるシステムもあります。
電子契約システムでできる2種類の契約方法
電子契約システムには、大きく分けて「電子サイン」と「電子署名」という2種類の方式があります。
どちらもオンライン上での契約締結を可能にする方法ですが、初期費用や信頼性などが微妙に異なります。
基本的には電子サイン(立会人型)がおすすめですが、まれに電子署名が適しているケースもあるので、両者の違いをおさえておきましょう。
電子サインでの契約(立会人型)
電子サイン方式は、契約の当事者ではない第三者が、当事者からの指示に基づいて電子サインを付与する方法です。
例えば「株式会社A」と「株式会社B」が事業譲渡契約を締結するときを考えます。
このとき、電子契約システムを提供している事業者Cが、株式会社Aと株式会社Bからの指示に基づいて、事業譲渡契約に電子サインを付与する方式が立会人型です。
一見すると、「なぜわざわざ複雑な手順を踏むのだろうか」と思うかもしれませんが、実は後述する当事者型と比べると利便性の高い契約方法です。
実際、多くの電子契約システムはこの方法で動作しています。
立会人型の電子契約システムのメリットは、以下の通りです。
- 初期費用が比較的低く、導入が容易
- 中小企業でもコスト的に使いやすいシステムが多い
- 電子契約システム上での署名管理がシンプル
一方、立会人型の電子契約には以下のデメリットもあります。
- 当事者型(後述)に比べると、なりすましのリスクが高い
- セキュリティレベルは電子契約システムの事業者に依存する
ただし、現実的には立会人型の電子契約でも、十分にセキュリティを担保できることが多いです。
実際、国際的にも立会人型の電子契約は一般的に用いられています。
電子署名での契約(当事者型)
電子署名方式は、公開鍵基盤(PKI)と呼ばれる技術を用いて、契約の当事者自身が署名を行う方式です。
先述した立会人型とは異なり、契約に際して第三者が介入することはありません。
契約の当事者は、認証に必要な機器やICカードなどを自身で用意して、事業者のサポートを受けることなく直接契約を締結します。
例えば、マイナンバーカードを用いた署名がこの一例です。
また、電子契約システムの中には、立会人型と当事者型の両方に対応しているシステムも存在します。
当事者型のメリットは、主に以下の3点です。
- 高い法的効力とセキュリティが保証される
- 大企業や規制の厳しい業界でも問題ない
- 国際基準にも対応している
電子署名システムのベンダーが署名へ介入しないため、高いセキュリティが担保できます。
また、電子署名に関する国際的なセキュリティの基準も満たしやすいです。
一方、当事者型の電子署名には以下のようなデメリットもあります。
- 2〜3年ごとの有効期限があり、定期的な更新が必須
- 電子署名に用いる機器やICカードなどの用意に手間がかかる
- 手間と費用がかかるため、取引先に断られる可能性がある
当事者型の場合だと、前述した立会人型と比べると多くの手間がかかります。
契約を締結する双方に手間がかかるため、取引先から当事者型の署名を断られるケースも少なくありません。
電子サイン・電子署名の特徴比較
電子サイン(立会人型)と電子署名(当事者型)には、それぞれ特徴があります。違いを表で整理すると、以下の通りです。
| 電子サイン | 電子署名 | |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜 | 最低3,000円が目安 |
| 定期的な更新 | 原則として不要 | 2〜3年ごとに必要 |
| 向いている企業 | 個人から大企業まで幅広い | 一部の大企業 |
| 信頼性・法的有効性 | 高い(国内利用には十分) | 極めて高い(国際規格対応) |
原則として、一般的な契約では電子サイン方式を採用すれば間違いありません。
よほど高いセキュリティ水準が求められる契約でなければ、電子サイン方式でも十分にセキュリティレベルを担保できます。
法的な契約の有効性も、国内利用であれば何ら問題ありません。
むしろ、電子署名方式での契約を求めると、取引先から断られてしまうケースが多いです。
ただし、まれではありますが、あえて電子署名方式が必要になるケースも存在します。具体的には、以下の通りです。
- 初めての取引先と、一度限りの高額な取引を行う場合
- 一部の金融業界など、極めて高い信頼性が必要な場合
それぞれの業界には慣習があるので、自社の事業領域などをふまえつつ、最適な方式を選択しましょう。
複数社の電子契約書システムを比較する際にみるべきポイント
最近ではDX化の推進に伴い、数多くの電子契約システムが登場しています。
自社に適したシステムを見極める際のポイントは、以下の3つです。
| 機能面 | 機能の過不足 稟議サポートの充実度 UIやUXなどの操作性 |
| 料金面 | 料金体系が自社に見合っているか |
| セキュリティ面 | なりすましを防げるか 契約に法的効力はあるか |
まずは機能面を見て、自社の契約締結プロセスを実現できそうなツールを絞り込むことをおすすめします。
その後、予算とセキュリティを総合的に加味しながら、自社に最適なものを選びましょう。
自社の規模・契約数に対して適切な機能・料金か
電子契約システムを選ぶ際にまずチェックすべき点が、機能や料金が自社に見合っているかどうかです。
電子契約システムの機能は多岐にわたります。
電子契約を締結できるようにしてくれるだけでなく、契約管理や稟議などもオンライン上でサポートしてくれるものも多いです。
機能が豊富なものを選ぶと、契約に関わる幅広い業務が効率化するでしょう。
ただし、機能が豊富なツールは利用料金も高くなります。
自社の契約締結プロセスを振り返りながら、本当に必要な機能だけを搭載したものを選ぶことが重要です。
無理に高機能なツールを導入して、オーバースペックにならないよう注意してください。
なお、料金体系が自社に合っているかもチェックしましょう。電子契約システムの料金体系は、以下の3通りが一般的です。
| 料金体系 | 例 | おすすめ | 契約数の目安 |
|---|---|---|---|
| 定額課金制 | 月額10,000円〜月額100,000円 | 大企業 | 月に200件以上 |
| 従量課金制 | 電子署名1回あたり200円〜300円 | 中小企業 | 月に50件以下 |
| ユーザー課金制 | 1ユーザーにつき500円〜1,000円 | 中小企業 | 月に50件以上 |
大企業で契約数が膨大な場合は、定額課金制のサービスがおすすめです。
定額課金制サービスだと電子契約システムの利用にかかるコストを見積もりやすいですし、中には1社ごとに担当者がついて利用をサポートしてくれるものもあります。
中小企業などで利用するのであれば、従量課金制やユーザー課金制がおすすめです。
契約数が目安として50件以下なら従量課金制、50件以上ならユーザー課金制が向いています。
法律に準拠しており法的効力が担保されているか
電子署名の法的効力がどの程度担保されているかどうかも、選定する際に意識しておきたいポイントです。
前述した通り、電子署名には以下の2通りの方法があります。
- 電子サイン(立会人型)
- 電子署名(当事者型)
電子署名の方が信頼性は高いですが、必要かどうかはケースバイケースです。
GMOサインやWAN-sign、BtoBプラットフォーム契約書などは、電子署名にも対応しています。
なお、「電子署名に対応していて、電子サインに対応していない」というシステムはほとんどありません。
セキュリティが万全かどうか
電子署名システムを導入する際には、セキュリティに万全の注意を払いましょう。
ログの保存機能や二段階認証があるシステムであれば、セキュリティは充実しているといえます。
大企業や官公庁での導入実績があるかどうかも、判断基準の一つです。
また、国内外の規格への対応状況を確認することもおすすめです。電子署名システムに関連する規格としては、以下のようなものがあります。
- ISO/IEC 27001(情報セキュリティマネジメントシステム認証)
- ISO/IEC 27017(クラウドサービスセキュリティ管理策認証)
- プライバシーマーク
これらを取得しているシステムは、特に信頼性が高いと判断してよいでしょう。
各社は認証マークの取得状況を公表しているので、導入する前に一度チェックしてみてください。
自社・取引先ともに使いやすいUI・UXになっているか
システムの操作性が優れているかどうかも、電子契約システムを導入する際のチェックポイントです。
万が一使いづらいUIのシステムを導入してしまうと、自社ばかりか取引先も不便な思いをしてしまいます。
電子契約システムの使い方がわからずに手戻りが発生すると、かえって業務が非効率になりかねません。
自社・取引先のどちらも操作に戸惑わず、直感的に使えるUIかどうかを確認しましょう。
その際には、デモやトライアル期間を活用して、担当者が実際にシステムを試すことが重要です。
社内稟議ができる機能はあるか
せっかく電子契約システムを導入するのであれば、社内稟議のサポート機能がついているものがおすすめです。
社内稟議のサポート機能があると、以下のようなことができます。
- 部門別、役職別の承認ルート設定
- コメントや差し戻し
- 承認状況のリアルタイム表示
ただし、同じ「社内稟議対応」でも、操作性はシステムによって大きく異なります。
社内稟議がスムーズに回せるかどうか、通知はSlackなのかメールなのかなど、チェックすべき点は多いです。
トライアル期間などを活用しながら、稟議の機能が使いやすいかどうかチェックしてみてください。
担当者ごとに権限を細かく設定できるか
権限設定の自由度も、電子契約システムを選ぶ際のポイントです。
紙の契約であれば、契約書の原本を厳重に保管することで、意図せぬ人が契約書を閲覧する事態を防ぐことができました。
しかし、電子契約の場合、何も対策をしなければ誰もがすべての契約書を閲覧できてしまいます。
そこで必要になる機能が、契約書に対する権限設定です。
例えば部門ごと、役職ごとに閲覧・編集・承認などの権限が細かく設定できれば、情報漏洩のリスクを軽減できます。
なお、権限設定機能の仕組みは、各システムで異なります。
例えばクラウドサインでは、「管理者」と「メンバー」の2つに分けて権限を管理しますし、kintoneでは個別に最大10つまで契約書にアクセスできるメールアドレスを設定できます。
どの仕組みが向いているかは、自社の組織体制や業務プロセス次第です。
権限設定に関しても、実際にシステムを試してみてから導入を決めるとよいでしょう。
おすすめ電子契約システムの人気ランキング
クラウドサイン

引用:クラウドサイン
| 運営会社 | 弁護士ドットコム株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 月額費用+送信件数ごとの費用 |
| 料金(Light) | 11,000円/月(税込) |
| 料金(Corporate) | 30,800円/月(税込) |
| 料金(Business) | 要問い合わせ |
| 料金(Enterprise) | 要問い合わせ |
「クラウドサイン」は日本国内シェアNo.1を誇る電子契約サービスです。
法律の専門家である弁護士がサービスを監修しているため、コンプライアンス面でも安心して利用できます。
契約書の作成から送信、締結まで全てクラウド上で完結でき、電子契約システムを導入していない相手方でもメール経由で簡単に署名依頼をすることが可能です。
操作が簡単で分かりやすく、サポート体制も充実しているため、今までクラウドシステムを導入していなかった中小企業でも安心して導入できるでしょう。
まずは無料プランから気軽に試し、自社の契約フローに合うか確認できるのも嬉しいポイントです。
【クラウドサインの特徴】
- 国内シェアNo.1の信頼性
- 弁護士監修の安心サービス
- 契約件数無制限で利用可能
電子印鑑GMOサイン

| 運営会社 | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 月額費用+オプション費用 |
| 料金(契約印&実印プラン) | 9,680円/月(税込) |
「電子印鑑GMOサイン」は、インターネット大手のGMOグループが提供する電子契約サービスです。
契約印(立会人型)と実印(当事者型)の2通りの電子署名ができるため、取引先との契約形態に合わせて使い分けることができます。
月額プランは約1万円から利用可能で、1件あたりの送信料もクラウドサインの約半額(立会人型で税込110円)と低コストなので、契約件数が多い場合でも費用を抑えられます。
無料で試せるフリープランも用意されているため、まずは社内テストをしてから本格導入することもできます。
「なるべく費用を抑えて電子契約を始めたい」という中小企業にとって、GMOサインは安心して導入できる選択肢と言えるでしょう。
専門知識がなくても直感的に操作できる画面設計で、紙契約からスムーズに移行できます。
【電子印鑑GMOサインの特徴】
- 実印・契約印の両方式に対応
- 他社より送信料が低価格
- 無料プランありで導入ハードル低い
CONTRACTHUB@absonne

| 運営会社 | 日鉄ソリューションズ株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 要問い合わせ |
| 料金 | 要問い合わせ |
「CONTRACTHUB@absonne」は、日本製鉄グループの日鉄ソリューションズが提供する電子契約サービスで、もともと大企業向け市場でシェアNo.1を獲得するなど実績があります。
紙の契約書も電子契約と一緒に管理できる点が特徴で、紙書面のスキャン保管や、これまで紙で行っていた社内承認フローをスムーズにデジタルに置き換えることができます。
「契約書の種類や取引先によって紙運用が残っている」という中小企業でも、CONTRACTHUBを使えば紙・電子をまとめて一元管理し、徐々にペーパーレスを進めることが可能です。
また、契約のリスクや運用ルールに応じて署名タイプを細かく選択できるため、不要なコストをかけずに運用できる柔軟さも中小企業に人気のポイントです。
初期導入時には専門スタッフの手厚いサポートも受けられるため、ITに不慣れな企業・担当者でも安心して導入することができるでしょう。
【CONTRACTHUB@absonneの特徴】
- 大企業でも使われる高い信頼性
- 紙契約と電子契約を一元管理
- 署名方法を柔軟に選択可能
ContractS CLM
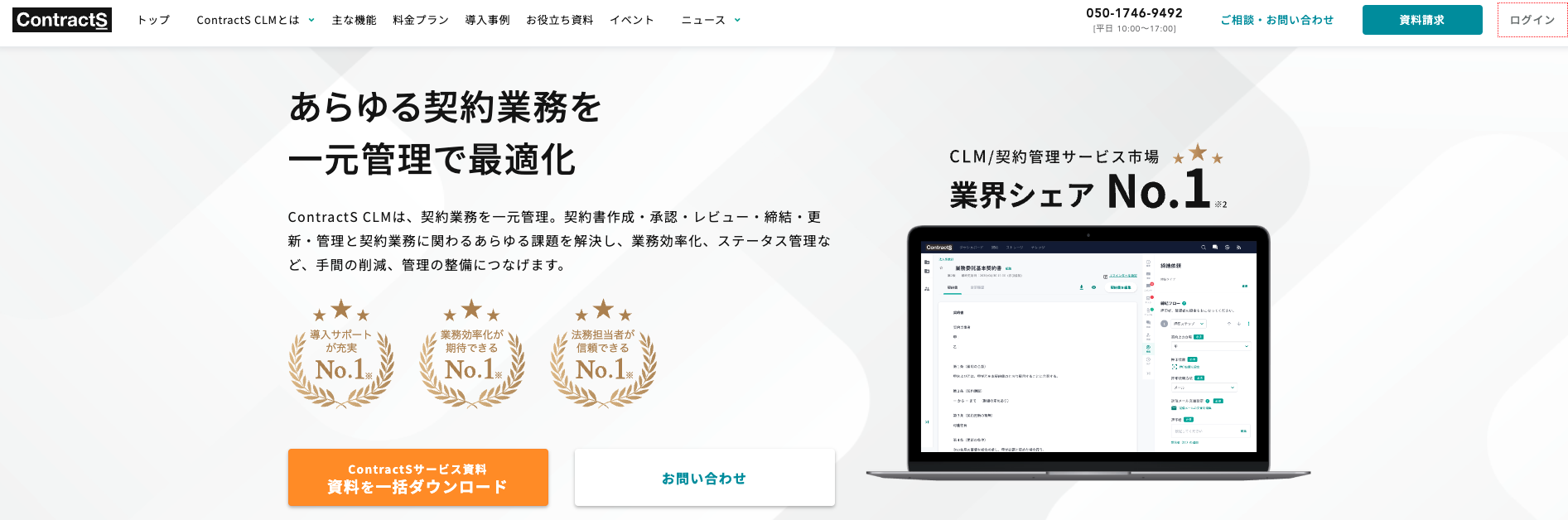
| 運営会社 | ContractS株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 初期費用+月額費用+オプション費用 |
| 料金 | 要問い合わせ |
契約書の作成支援、法務レビュー、社内承認、電子締結、そして締結後の契約書管理や更新管理に至るまで、契約に関するあらゆる業務プロセス管理・最適化できる本格的なCLM(契約ライフサイクルマネジメント)システムです。
単に紙と印鑑を電子化するだけでなく、Word文書をそのまま取り込んで使える編集機能や、契約書の社内ナレッジを共有できる機能があり、属人的になりがちな契約実務を標準化できる点が高い評価を得ています。
導入企業からは年間数百時間の業務削減や大幅なコスト削減効果が報告されるほどで、社内の契約管理体制を根本から見直し、強化したいと考えている企業に最適といえるでしょう。
【ContractS CLMの特徴】
- 契約業務の一元管理を実現
- Wordと連携し契約書を編集可能
- 契約書のテンプレ共有機能搭載
freeeサイン

引用:freeeサイン
| 運営会社 | freee株式会社 |
|---|---|
| 料金形態 | 月額費用 |
| 料金(Starter) | 7,180円/月(税込) |
| 料金(Standard) | 35,760円/月(税込) |
| 料金(Advance/Enterprise) | 要問い合わせ |
「freeeサイン」はクラウド会計ソフトなどで知られるfreee株式会社が提供する電子契約サービスで、会計・人事労務サービスと一貫したシンプルで使いやすい機能が特徴的です。
料金面も中小企業に優しく、例えばStarterプランでは毎月50通まで追加費用なしで契約締結ができ、契約件数が少ない企業なら実質定額で使い放題に近い形で利用できます。
ユーザー数もプランによって無制限に追加可能なので、「部署ごとにアカウントを分けたい」という場合でも安心です。
他のfreee製品(会計や人事労務)とも連携する場合、契約データを経理処理にスムーズに反映させるなど、バックオフィス業務全体を効率化することができるでしょう。
クラウド型のためインストール不要ですぐに始められるので、導入・運用コストを抑えつつ気軽に電子契約に移行したい中小企業におすすめできます。
【freeeサインの特徴】
- 低コストではじめやすい料金体系
- 直感的UIで誰でも使いやすい
- 他のfreeeサービスと連携可能
マネーフォワード クラウド契約

| 運営会社 | 株式会社マネーフォワード |
|---|---|
| 料金形態 | 月額費用 |
| 料金(契約締結のみ) | 3,278円/月(税込) |
| 料金(フル機能版) | 要問い合わせ |
「マネーフォワード クラウド契約」の最大の特徴は契約書の送信料・保管料が無料であること。月額定額制で使えるため、契約数が多い会社でも追加コストが発生せず安心です。
初期費用も無料で、契約数が少なく電子署名・電子契約をするだけであれば月額3,000円程度のプランで利用することができるため、コストをかけづらい中小企業でも気軽に導入をすることができます。
マネーフォワードのサービスはバックオフィス業務全般を支援するクラウドサービスなので、会計や経費精算システムとデータ連携しやすい点も中小企業には魅力です。
【マネーフォワード クラウド契約の特徴】
- 送信料0円のシンプル定額制
- 社内承認ワークフロー機能あり
- 会計ソフト等他サービス連携充実
WAN-Sign

| 運営会社 | 株式会社NXワンビシアーカイブズ |
|---|---|
| 料金形態 | 従量課金制+オプション費用 |
| 料金(立会人型) | 110円/件(税込) |
| 料金(当事者型) | 330円/件(税込) |
「WAN-Sign(ワン・サイン)」は、日本通運グループのNXワンビシアーカイブズで長年にわたり機密文書管理を手掛けてきたノウハウが活かされており、契約書の保管・管理機能が充実しています。
紙の契約書原本と電子契約データの一元管理にも対応しているため、「一部の取引先とは紙契約が残る」という企業でも安心です。
また、契約の締結方法として当事者型電子署名(実印相当)から立会人型電子署名(契約印相当)まで幅広くサポートしており、取引リスクに応じて適切な署名方式を選択できます。
立会人型の署名なら月10件まで、当事者型の署名なら月3件までは無料で利用できるため、毎月の新規契約はそこまで多くないものの電子契約システムを導入したいという会社にピッタリでしょう。
【WAN-Signの特徴】
- 紙と電子の契約書を一括管理
- 送信料100円~と低コスト
- 無料プランあり気軽に試せる
BtoBプラットフォーム 契約書

| 運営会社 | 株式会社インフォマート |
|---|---|
| 料金形態 | 初期費用+月額費用+従量課金制 |
| 料金(シルバープラン) | 11,000円/月(税込) |
| 料金(ゴールドプラン) | 33,000円/月(税込) |
「BtoBプラットフォーム 契約書」は、食品業界のDXなどを手掛け、110万社以上の利用実績を持つインフォマートが提供する電子契約サービスです。
他社では有料オプションになりがちな社内ワークフロー(稟議承認)機能も標準で付いており、契約書の社内決裁から締結・保管まで一気通貫で管理することができます。
導入企業からは、直感的で分かりやすい操作性と優れたコストパフォーマンスが好評で、まずは低コストで電子契約システムを試してみたいという会社におすすめです。
ゴールドプランであれば契約書の電子保管は無制限にできるので、いずれ契約数が増えそうな会社でも使い続けることができるでしょう。
【BtoBプラットフォーム 契約書の特徴】
- 1通100円の業界最安級送信料
- 稟議など社内ワークフロー標準対応
ベクターサイン

引用:ベクターサイン
| 運営会社 | 株式会社ベクターホールディングス |
|---|---|
| 料金形態 | 従量課金制+オプション費用 |
| 料金(プラン5) | 5通:1,320円/月(税込) |
| 料金(プラン30) | 30通:6,600円/月(税込) |
| 料金(プラン100) | 100通:13,200円/月(税込) |
ベクターサインは、基本料金ゼロで利用できる電子契約サービスです。初期費用も月額固定費用も発生せず、契約書を送信するごとに料金を支払う従量課金モデルのため、小規模企業でも無駄なく運用できます。
文書の保管件数やユーザーアカウント数に制限がないので、契約書を大量に保管・共有したい場合でも追加コストを気にせず安心して利用可能です。
月間または年間の送信件数に応じて割引が利く定期契約プランも用意されており、利用量に合わせて柔軟にプランを選択できます。
【ベクターサイン 契約書の特徴】
- 基本料金0円で始めやすい従量課金
- 保管文書数・ユーザー数無制限
- 月/年の送信数に応じた定額プラン有
電子契約システムを導入するメリット
電子契約システムの導入には、単なる業務効率の向上はもちろん、コスト削減やセキュリティ強化、さらにはコンプライアンス対応など大きなメリットがあります。
また、昨今ではリモートワークやDXを推進する企業も多いです。
電子契約システムは、これらを実現するうえでも欠かせないツールといえます。
紙面の製本・郵送などのコストを削減でき、スピーディーに契約締結ができる
電子契約システムを導入する最大のメリットは、コストの削減と契約締結の効率化です。
紙で契約する場合には、多くの費用がかかります。例えば以下の企業を考えましょう。
- 毎月200件の契約を処理している
- 契約1件につき、平均5枚の契約書を作成している
- 収入印紙は200円分を使用する
この場合のランニングコストを、簡単に試算してみました。
| 計算式 | 年間費用 | |
|---|---|---|
| ①紙代・印刷費用 | 1枚5円✕1,000枚✕12ヶ月 | 60,000円 |
| ②郵送費 | 1件140円✕2回✕200件✕12ヶ月 | 672,000円 |
| ③収入印紙 | 200円✕200件✕12ヶ月 | 480,000円 |
| 合計 | ①+②+③ | 1,212,000円 |
一方、電子契約だとこれらの費用がかかりません。
特に収入印紙が不要なので、無駄な出費を抑えることができます。月
額2万円の電子契約システムを導入するのであれば、年間で100万円程度のコストカットにつながるのです。
また、電子契約の場合は契約の締結も非常にスピーディーです。
郵送はどんなに速くても1日かかるので、紙での契約締結は最低でも2日程度見込んでおく必要があります。
電子契約であればすぐに送信できるので、最短即日で契約可能です。
紙の契約書を長期間保管する場所・コストを削減できる
紙の契約書を保管しなくてよい点も、電子契約システムを導入するメリットです。
紙の契約書を保管するためには、倉庫やキャビネットを用意する必要があります。
しかし、電子契約システムであればこれらが不要です。
ファイルやバインダーなどのオフィス用品を調達するコストも削減できます。
また、電子契約システムにはキーワード検索やAIタグ付け機能があるので、必要な契約書を見つけやすくなるメリットもあります。
過去の契約書が1万件を超える場合でも、紙の契約書をかき分けて探す必要がありません。
担当者がリモートワーク中でも契約を進めることができる
電子契約システムを導入するメリットとして、リモートでも契約締結できるという点も挙げられます。
リモートワークの場合、紙面上での契約締結が非常に難しいです。
社内稟議を行う場合も、「次の課長の出社は1週間後」といった事情で業務が滞ってしまうケースも少なくありません。
中には、「契約書に押印するためだけに出社した」という経験をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。
電子契約システムであれば、こうした非効率な業務が生じることなく、スピーディーに契約や稟議を進めることができます。
海外にある取引先と契約を締結する際も、国際郵便などを発送する手間がないため、非常にスムーズです。
契約書改ざんのリスクを減らし、コンプライアンスを強化できる
電子契約システムを導入すれば、コンプライアンスの強化も実現できます。
電子契約というと、どうしても「紙の契約書よりも改ざんされやすいのでは」と思われがちです。
しかし、現代の電子契約システムは、第三者による改ざんのリスクを極力減らしていると考えてよいでしょう。
ここでは詳しく説明しませんが、多くの電子契約システムは、秘密鍵と公開鍵と呼ばれるデジタル鍵を用いてデータの暗号化を行っています。
このため、第三者が内容を不正に書き換えることは極めて難しいです。
そもそも紙の契約書も、セキュリティ対策次第では簡単に書き換えることができてしまいます。
コンプライアンスを強化するのであれば、電子契約システムの利用がおすすめです。
電子契約システムを導入する際のコスト・注意点
電子契約システムの導入は多くのメリットがありますが、初期費用やシステムの引き継ぎなどでいくつかの注意点が存在します。
また、取引先によっては、紙での契約を求められることもあるでしょう。
電子契約システムをスムーズに運用するためには、こうした注意点をあらかじめ頭に入れておくことが大切です。
電子契約システム導入時は社内でのフローを調整する必要がある
電子契約システムを導入するのであれば、社内の業務フローを再設計する必要があります。
例えば紙の契約書であれば、「遠方の拠点からの承認はまとめてもらう」といった業務フローになっていることもあるでしょう。
電子契約システムを導入するのであれば、拠点ごとの承認ではなく、役職ごとに承認をもらうように手順を改めた方が効率的です。
また、電子契約システムの導入後も紙の契約書を引き続き活用するのであれば、原本を保管するタイミングや保管する場所などを別途決めておく必要があります。
「WAN-Sign」など、原本を倉庫で保管してくれるサービスを利用することもおすすめです。
契約相手が書面での契約書を希望する場合はシステムが使えない
契約の相手方によっては、電子契約が利用できない場合もあります。
例えば以下のような契約書は、相手方の同意がなければ電子化することができません。
- 建設工事の請負契約書
- 宅地建物の売買・交換の媒介契約書と代理契約書
- 貸金業法に基づく各種書面
- 金銭支払の受取証書
これら以外の契約書も、相手からの同意なしに電子化するとトラブルにつながるリスクがあります。
官公庁などの一部の組織は、書面での契約を希望するケースも少なくありません。
この点に関しては、以下の対策がおすすめです。
- 電子契約と書面での契約のハイブリッド化を検討する
- 契約が電子化可能かをあらかじめ取引先に確かめる
完全に契約を電子化するのではなく、「書面での契約と電子契約を並行する」という前提で運用するとよいでしょう。
一度電子契約システムを導入すると他のシステムへの乗り換えが難しい
電子契約システムを導入すると、他システムへの移行が難しくなります。
一度契約した電子システムを乗り換える際には、以下のようなコストが必要です。
- 金銭的コスト
- 新システムの初期費用、既存システムへの違約金
- 時間的コスト
- 契約データの移行、社内ルールの再整備
一度導入した電子契約システムの変更は、よほどの事情がない限り難しいと考えるべきです。
取引先にも、契約手順の変更によって工数をかけてしまう可能性があります。
対策としては、システムの無料トライアル期間などを活用して、自社に最適なシステムを見極めることがおすすめです。
導入予定のシステムは、法務や総務だけでなく、担当者レベルでテストしておきましょう。
法的に電子契約が認められていない書類もある
2025年時点では、法的に電子契約が認められていない書類も存在します。
例えば以下の場合は、2025年の記事執筆時点でも電子契約の利用ができません。
- 事業用定期借地契約
- 任意後見契約書
- 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約
これらは、いずれも公正証書による契約の締結が必要です。
現時点では、すべての契約書を電子化できるわけではないので注意しましょう。
※ 公正証書の電子化に向けた検討も進められているため、将来的にはこれらも電子契約できるようになる可能性があります。
電子契約システム導入時によくある質問
ここでは、電子契約システムの導入や運用に際して、よく寄せられる疑問に回答します。
電子契約システムの導入時には、ぜひ参考にしてください。
電子契約システムは相手も同じものを導入していないと使えない?
いいえ。
ほとんどの電子契約システムは、「送信者のみの導入」で利用できる仕組みになっています。
電子契約システムの基本的な利用の流れは、以下の通りです。
- システム上で契約書を作成する
- 契約書のURLを発行し、メールやSlackなどで共有する
- 相手がURLから契約書にサインする
- 契約の締結完了
取引先は、メールなどで共有されたリンクにアクセスするだけで、署名や情報入力をすることができます。
「同じシステムを導入していない相手とは電子契約できない」というわけではないため、安心してください。
電子契約システムで締結した契約書に法的拘束力はある?
電子署名法に準拠したシステムであれば、法的な拘束力は十分に担保されています。
総務省や法務省、経済産業省などが発表した政府の公式見解では、以下の2つの要件が満たされているサービスであれば、契約が真正なものとして認められるとのことです。
- 電子署名法第3条に規定する電子署名が付されている
- 上記電子署名が本人の意志に基づき行われている
多くの電子契約システムは、これらの基準に基づいています。
例えばクラウドサインやGMOサインは、二段階認証を導入することで契約の有効性を担保しています。
海外企業と契約書を交わす時に電子契約システムは使える?
海外企業との取引でも、電子契約システムを使うことができます。
ただし、各国で電子契約に関する規格を定めている場合があるので、取引先の国の規格に対応しているシステムを選ぶと安心です。
代表的な規格としては、以下が挙げられます。
- eIDAS規格(EU)
- ESIGN法(米国)
これらの規格に準拠している電子契約システムとしては、docusignが挙げられます。
docusignは世界中で用いられている電子契約システムなので、海外企業との取引が多い場合にはおすすめです。
このほか、CMサインもeIDAS規格やESIGN法といった海外の基準に対応しています。
無料で使える電子契約システムはある?
無料で使える電子契約システムも存在します。
無料で使える主な電子契約システムは、以下の通りです。
| サービス名 | 主な制限 | 有料の場合の料金 |
|---|---|---|
| クラウドサイン | 月3件、1アカウントまで | 月額10,000円〜 |
| WAN-Sign | 月3件まで | 月額10,000円〜 |
| GMOサイン | 月5件、1アカウントまで | 月額8,800円〜 |
| FAST SIGN | 月10件、1アカウントまで | 月額10,000円〜 |
無料の電子契約システムを用いた場合でも、電子契約の法的な有効性が損なわれることはありません。
ただし、これらはあくまでも「有料システムの一部を無料で試すことができる」という位置づけで提供されていることがほとんどです。
契約数の制限も月3〜10件までと厳しいことが多いため、本格運用する際には有料プランへの加入を検討しましょう。
電子契約システム|まとめ
電子契約システムは、DXやリモートワークを推進するうえで非常に重要です。
紙の契約書の持つさまざまなデメリットを一気に解決できるため、多くの企業で導入が進んでいます。
一方、電子契約にはさまざまなシステムがあります。
自社にぴったりなものを選ぶためには、規模や契約数、法的要件やセキュリティ対策、そしてUI・UXの使いやすさなど、さまざまな観点から比較することが大切です。
ペーパーレス化を促進するためにも、ぜひこの記事の内容を参考に、電子契約システムの導入を検討してみてください。
SHARE
関連記事
-
2025年10月06日(月)
【2026年最新】ハラスメント社外相談窓口のおすすめ比較10選!外部委託の費用相場やメリットは?
- おすすめ

-
2025年09月21日(日)
【2026年最新】決済代行サービスのおすすめ比較10選|機能・メリット・導入時の注意点まで徹底解説
- おすすめ
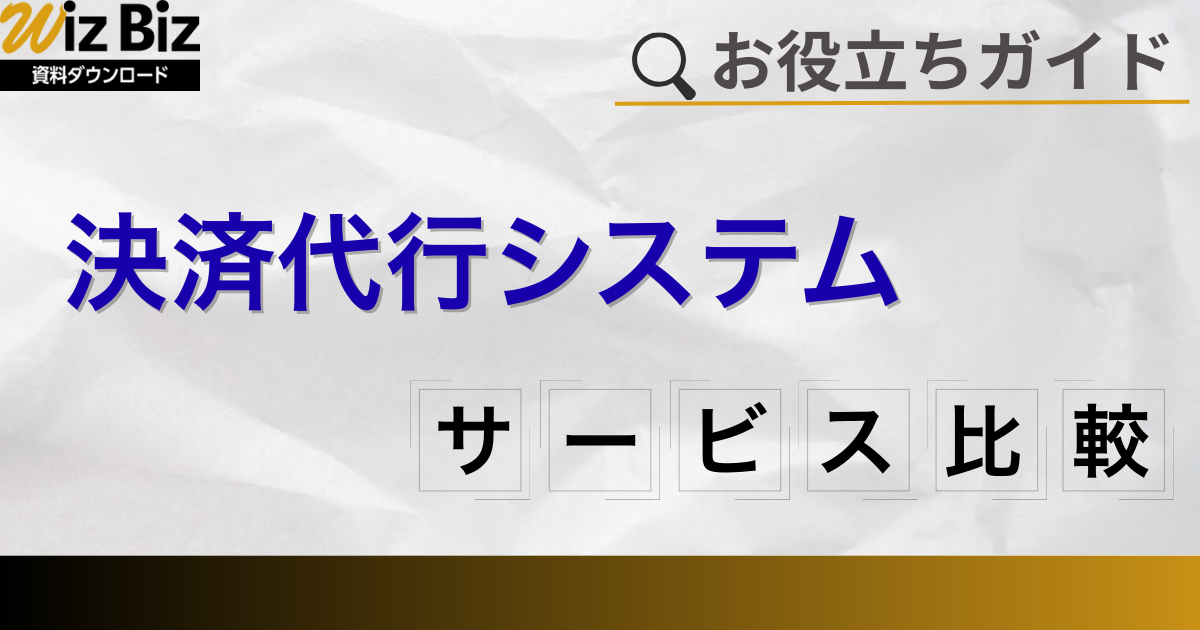
-
2025年09月21日(日)
【2026年最新】メール配信システムのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気のメール配信システムを解説
- おすすめ
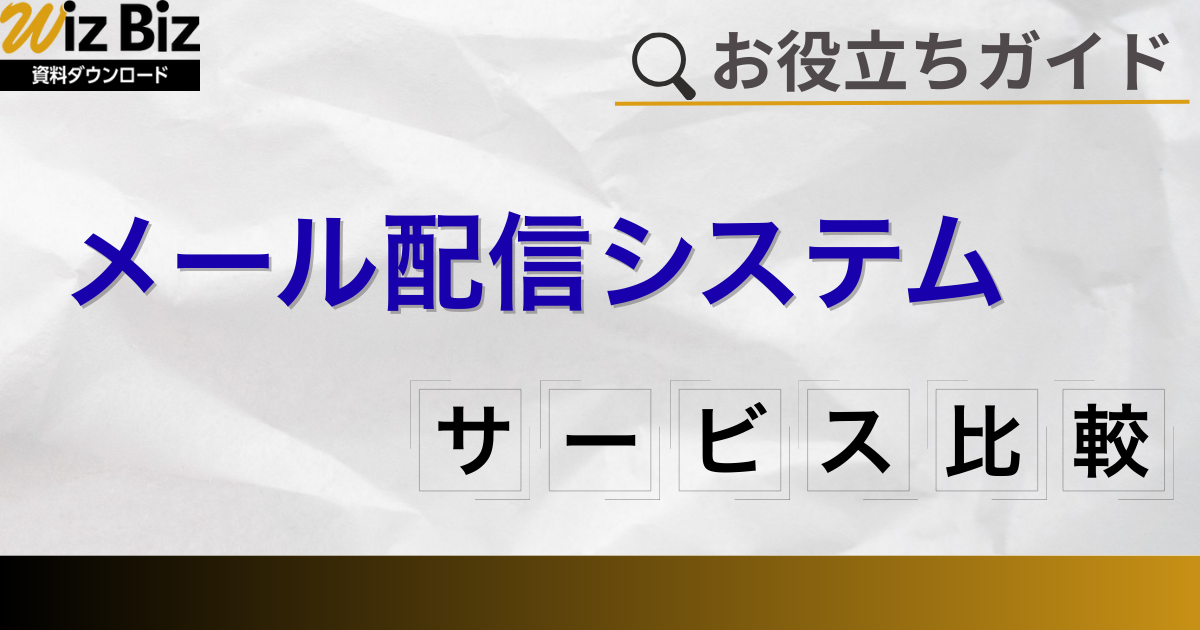
-
2025年09月21日(日)
【2026年最新】SFAツールのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気営業支援システムを解説
- おすすめ
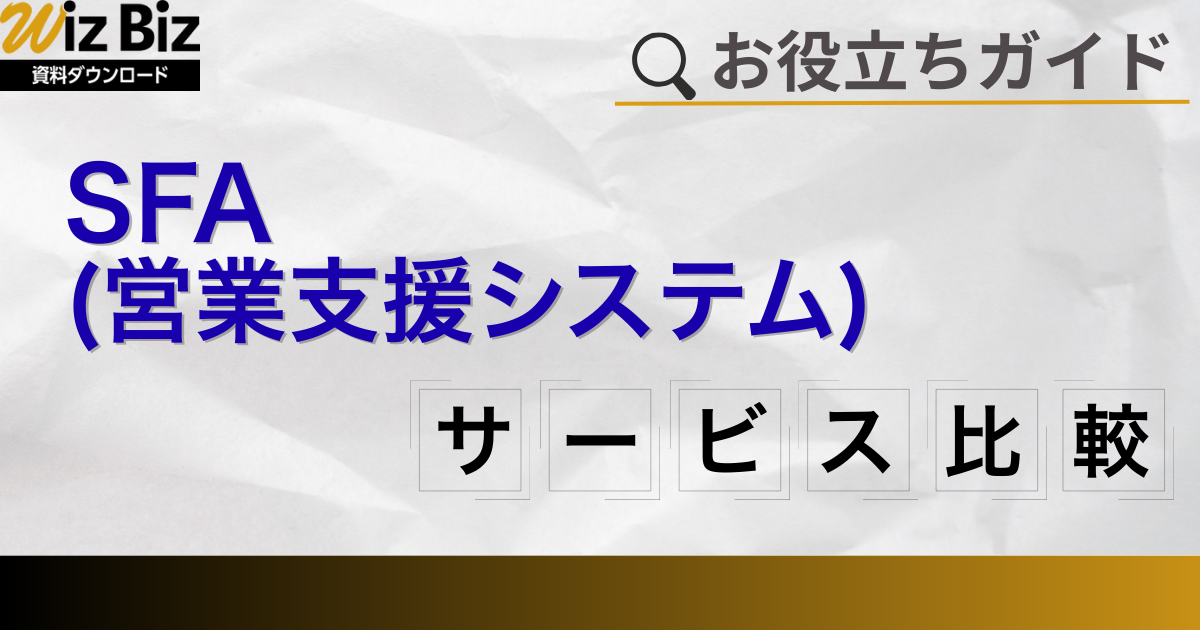
-
2025年09月21日(日)
【2026年最新】名刺管理ソフト・アプリのおすすめ比較10選|機能別・料金別で人気製品を比較!
- おすすめ
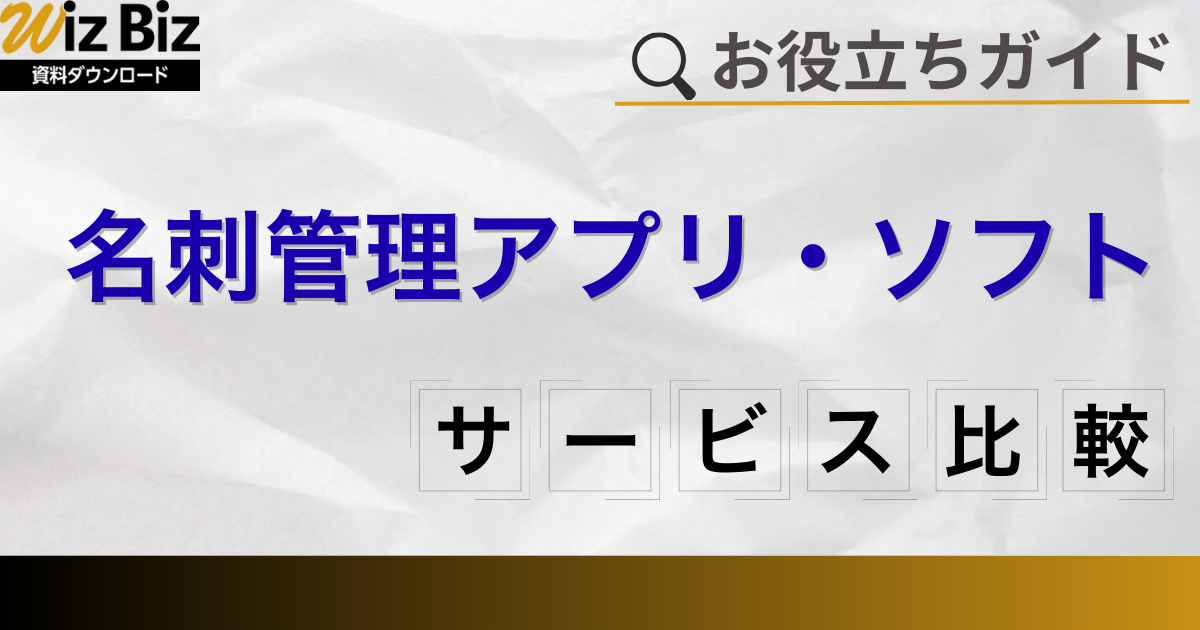
-
2025年09月21日(日)
【2026年最新】POSレジのおすすめ比較10選|業界別・機能別の人気POSレジやタブレット端末で使えるシステムは?
- おすすめ
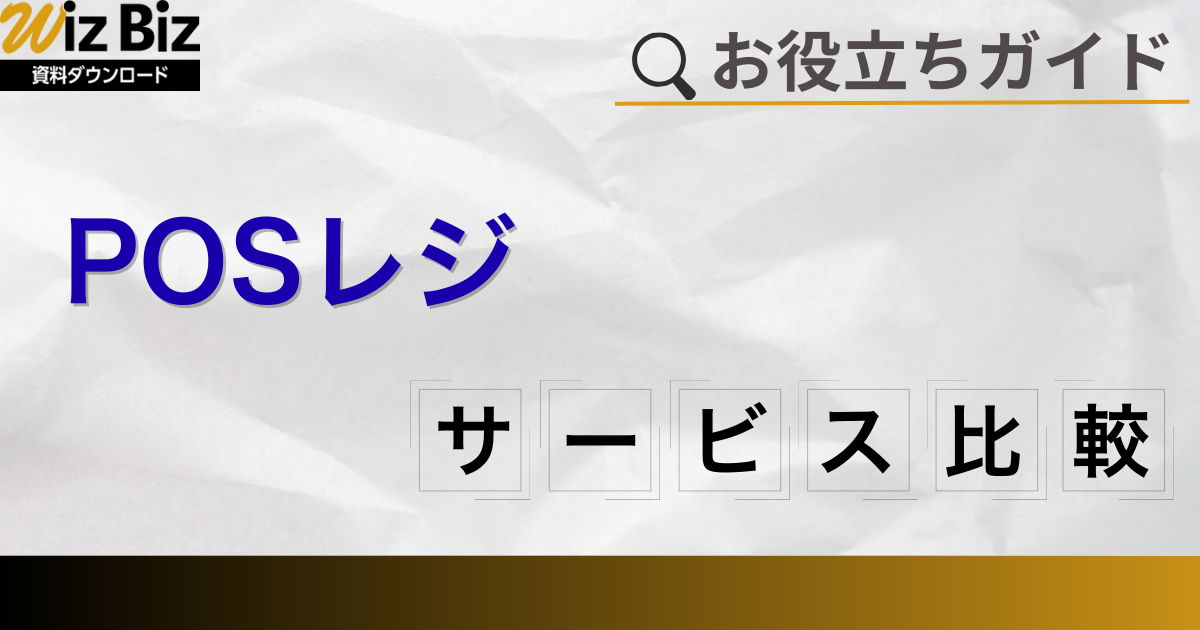
おすすめサービス
- 契約書管理システムのおすすめ比較10選【2026年最新】会社規模別や料金の人気システムは?
- 一覧へ戻る
- 経費精算システムのおすすめ比較10選【2026年最新】大企業も導入している使いやすいシステムは?

ダウンロード候補に
追加しました!

削除しました