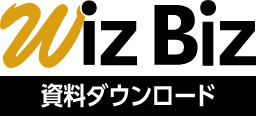お役立ちガイド
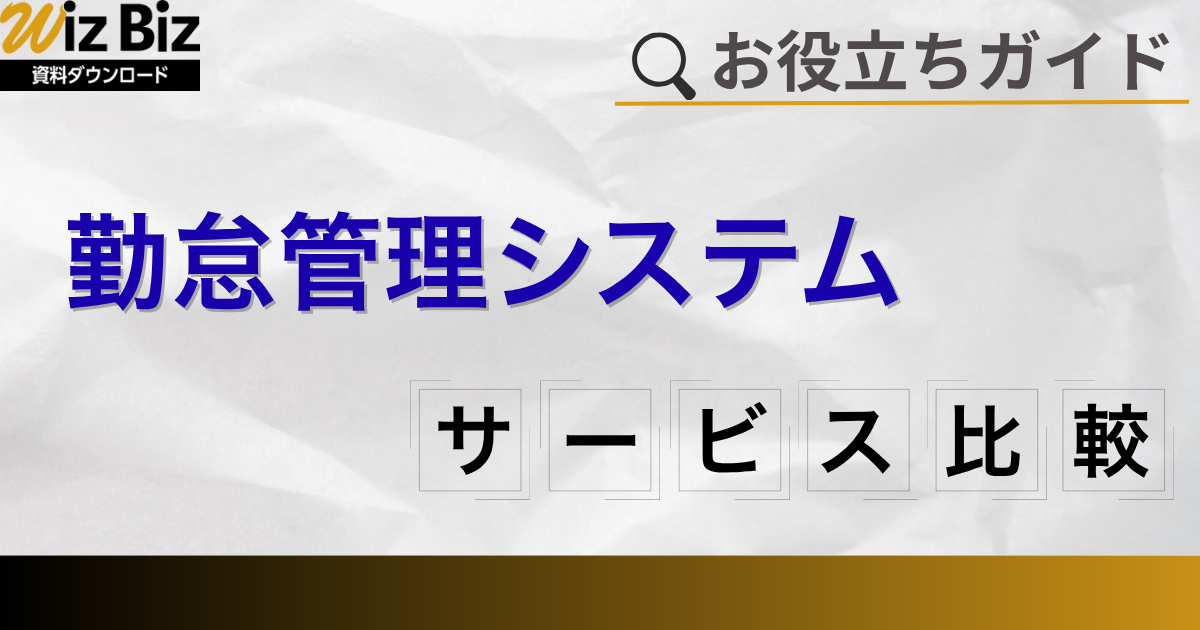
勤怠管理システムとは、社員の勤怠データを効率よく管理できるITツールです。出勤時間や退勤時間、休暇の取得状況などを一括で集計できるため、勤怠管理のコストを大きく減らしてくれます。
勤怠管理システムは、選択肢が非常に豊富です。大企業向けから中小企業向け、業界特化型のものまで幅広く存在するため、「何を導入すればよいのかわからない」という方もいらっしゃるでしょう。
そこでこの記事では、勤怠管理システムを比較する際のポイントや、おすすめの勤怠管理システムを詳しく解説します。勤怠管理システムの導入でお困りの担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。
勤怠管理システムの機能とできること
勤怠管理システムでは、社員の出退勤情報や残業時間、休暇の利用状況などを一括で管理できます。
最近ではリモートワークやフレックスタイム制といった多様な働き方が浸透しつつあるため、勤怠管理は複雑になりがちです。勤怠管理システムを活用すれば、こうした複雑な勤怠情報も楽に管理できます。
各社の勤怠管理システムの基本機能
勤怠管理システムにはさまざまなものがありますが、多くのシステムに共通して搭載されているものは以下の機能です。
- 出退勤の打刻機能
- 休暇管理機能
- シフト管理
- 予実管理
- レポート出力
まず、勤怠管理システムに必ず搭載されている機能が、出退勤の打刻機能です。
利用者は、出勤時と退勤時にスマホやICカードを用いて打刻を行います。この出退勤記録をもとに、システム上から残業時間を算出したり、労務超過がないかチェックしたりするものが勤怠管理システムの基本的な仕組みです。
残業時間の超過や有給の未消化があった場合には、本人や上長へ通知を配信できるものもあります。
打刻方法はいくつかありますが、代表的なものは以下の通りです。
- スマートフォン打刻
- PC打刻
- ICカード打刻
- 生体認証打刻
どれか一通りの打刻方法しか対応できないというわけではなく、これらの中から必要なものを組み合わせて使うことが一般的です。
大企業向けのシステムほど、幅広い打刻方法に対応している傾向があります。
休暇管理機能も、出退勤機能と同じくほとんどの勤怠管理システムに搭載されています。
社員がいつ有給休暇を取得したのか、育休や産休の期間はいつなのかといった情報を、システム上で一括管理することが可能です。
このほか、システムによっては以下の機能が搭載されている場合もあります。
| 機能名 | 内容 |
|---|---|
| シフト管理 | シフトを手動で登録したり、シフト希望から自動作成したりする |
| 予実管理 | 残業代や手当を自動で計算して、予算超過がないかチェックする |
| レポート出力 | 残業時間や有給取得状況などをグラフや表で可視化する |
参考までに、代表的な勤怠管理システムである「ジョブカン勤怠管理」「freee勤怠管理Plus」「KING OF TIME」「チムスビ勤怠」「kincone」における各機能の対応状況をまとめておきます。
| 製品名 | 出退勤の 打刻 |
休暇 管理 |
シフト 管理 |
予実 管理 |
レポート 出力 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョブカン勤怠管理 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ✕ |
| freee勤怠管理Plus | ◯ | ◯ | ✕ | ◯ | ✕ |
| KING OF TIME | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| チムスビ勤怠 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| kincone | ◯ | ◯ | ✕ | ✕ | ◯ |
勤怠管理システムを導入した方が良い会社
結論から言うと、以下のような点に該当する企業は勤怠管理システムを導入した方が良いといえます。
- 30人以上の社員がいる企業
- フレックスタイムや裁量労働制などを採用している企業
- 厳密な労働時間の管理が必要な企業
企業規模が小さい場合は、Excelでの勤怠管理で十分な場合もあるでしょう。しかし、Excelでの勤怠管理には限界があります。社員数が30人を超えたあたりが、勤怠管理システムを導入する目安です。
フレックスタイム制や裁量労働制などの複雑な勤務形態を採用している場合も、勤怠管理システムの導入がおすすめです。
こうした勤務形態の勤怠を手作業で管理すると、ミスが発生しやすくなります。
また、建設業や物流業、飲食業など、厳密な労働時間の管理が求められる場合も勤怠管理システムを導入するとよいでしょう。
これらの業種では、業界特化型の勤怠管理システムも販売されています。例えば飲食業向けの「ASPIT」では、POSデータや券売機データと勤怠情報を連携させることが可能です。
勤怠管理システムだけでなく、労務・経理システムと連携できるものもある
勤怠管理システムの中には、労務・経理システムと連携できるものもあります。
給与計算は、各社員の雇用形態や手当、控除などを考慮する必要があるため、非常に煩雑です。
勤怠管理システムを労務・経理システムと連携すると、こうした作業を勤怠管理の段階から自動化できます。
勤怠管理システムと労務・経理システムを連携するメリットは、以下の通りです。
- 勤怠情報を給与計算へリアルタイムに反映できる
- 給与計算のミスが起こりづらくなる
- データの二重入力が不要で、担当者の手間を省ける
社員数が30人を超える場合は、労務・経理システムとの連携を積極的に検討するとよいでしょう。
勤怠管理システムと労務・経理システムの連携タイプは、大きく以下の3つに分かれています。
- 一体型……勤怠管理と労務・経理管理を一つのツールで行う
- シリーズ連携型……同じベンダーのツール同士で連携する
- 外部連携型……異なるベンダーのツールをAPIやCSVファイルを通して連携する
一体型の場合、シームレスに連携できるので管理が楽です。勤怠管理や労務管理だけでなく、会計や販売管理まで幅広くカバーするERPと呼ばれるツールもあります。ただし、ツールの選択肢はそれほど多くありません。
シリーズ連携型も、一体型ほどではありませんが連携がスムーズです。例えばfreeeが提供している「freee勤怠管理Plus」と「freee人事労務」は、従業員情報などを共有することで情報を一元管理できます。
外部連携型は、APIやCSVファイルを通して、異なるベンダーのシステムを連携させるパターンです。
APIの設定やCSVファイルの書き出しなどに手間がかかるため、連携手順が煩雑になることがあります。ただしツール選定の自由度は高いので、どうしても使いたい勤怠管理ツールがある場合にはおすすめです。
勤怠管理システムを導入するメリット
総務省が公表した調査によると、勤怠管理システムを導入している企業は2020年度時点で全体の29.6%にのぼり、その割合は年々増えています。勤怠管理システムが人気を集めているのは、多くのメリットがあるからです。
例えば勤怠管理システムを導入すると、勤務時間の記入や残業時間の計算、有給取得日のカウントといった業務を一気に自動化できます。また、労働基準法違反を防ぎやすいですし、法改正への対応も容易です。
煩雑な勤怠管理業務を大幅に削減できる
勤怠管理システムを導入する最大のメリットは、勤怠管理業務の効率化です。
勤怠管理システムを用いない場合、Excelで出勤時刻や退勤時刻を管理することになります。しかし、社員数が増えるとExcelでの管理は非効率です。
関数やマクロを組んで効率化することはできますが、「担当者がいないと回らない」という状態を招く可能性があります。
勤怠管理システムを使えば、こうした属人化を防ぎつつ、大量のデータを効率よく処理することが可能です。
社員が100人や1,000人といった規模になっても、大企業向けの勤怠管理システムであれば問題なく対応できます。転記ミスやデータの見間違えといったヒューマンエラーも減るため、人事業務全体がグッと効率化するのです。
労働時間を正確に計測できる
勤怠管理システムでは労働時間を正確に記録できるため、信憑性の高い勤怠データを得ることができます。
勤怠管理システムを用いない場合、社員からの出勤時刻や退勤時刻を自己申告してもらうことが一般的です。しかし、この方法だと以下のような不正が起こるリスクがあり、データの信頼性が担保できません。
- 誰かの代理で打刻する
- 一度打刻した時刻を書き換える
- 出勤前、退勤後に打刻する
また、建設業や物流業では現場移動が多く、正確な労働時間の把握が難しいケースもあるでしょう。
勤怠管理システムを使えば、システムが正確に打刻してくれます。一人一つずつアカウントが割り振られるので、不正が起こりづらいです。
さらに、遠隔からスマホ1つで打刻できるため、現場移動が多くても勤務時間を正確に把握できます。
また、ICカードでの打刻であれば、カードをタッチするだけで打刻できます。生体認証であれば、顔をかざすだけで打刻は完了です。
いずれにしても従来よりも気軽に打刻できるので、休憩や私用の時間も正確に把握できるようになります。
リモートワークの勤務時間も把握しやすい
リモートワークも、勤怠管理システムであれば管理しやすいです。
リモートワークの場合、メールやチャット、さらにはExcel上で管理する出勤簿などで勤怠管理することになります。
しかし、上司の目が行き届かないリモートワークの場合、これらのデータは信憑性が低下しかねません。また、メールでの報告や出勤簿への記入を忘れてしまったり、煩わしいと感じたりする社員もいるでしょう。
その点、勤怠管理システムであれば、リモートワークでも普段と変わらない方法で打刻できます。より正確な勤怠管理ができるようになりますし、打刻の手間が減るので社員にとってのメリットも大きいです。
中には、以下の機能を備えたシステムもあります。
- 打刻した際の位置情報を記録する
- 出勤予定時刻に打刻がなければアラートで通知する
- LINEやSlackを用いて打刻する
特定の場所のみで打刻させたい場合や、普段使っているチャットツールと連携したい場合も、勤怠管理システムが非常に便利です。
労働基準法違反を防ぎやすい
勤怠管理システムを導入すると、労働基準法違反を防ぎやすいというメリットもあります。
労働基準法では、使用者が労働時間を適切に管理するよう義務付けられています。厚生労働省が公表しているガイドラインによると、始業と終業の時刻を確認する方法は以下の2つです。
使用者が、自ら現認することにより確認し、記録すること。
タイムカード、ICカード等の客観的な記録を基礎として確認し、記録すること
引用:厚生労働省「労働時間の適正な把握のために」
現実的には、タイムカードやICカードを用いる2番目の方法となるでしょう。勤怠管理システムによる打刻は、原則としてこの2番目の規則を満たしているとみなされます。
そのため、勤怠管理システムを用いれば、労働基準法や厚生労働省のガイドラインに沿った形で、適切に勤怠時間を管理できるようになるのです。
また、労働基準法には以下の内容も定められています。
- 労働時間の上限(労働基準法第32条)
- 時間外労働に対する割増賃金(労働基準法第37条)
- 有給休暇の付与(労働基準法第39条)
ほとんどの勤怠管理システムは、これらの法令に沿った形でアラートを発したり、社員や上長にメールで通知を送信したりしてくれます。労働基準法に違反しそうな状態が発生した場合にも、すぐに気づくことが可能です。
法改正にすぐ対応できる
法改正に素早く対応できるのも、勤怠管理システムを導入するメリットです。
労働基準法などは、たびたび改正されているのをご存知でしょうか。例えば2019年4月に行われた法改正では、主に以下のような変更がありました。
- 時間外労働の上限時間導入
- 最低5日間の年次有給休暇の取得の義務付け(条件あり)
- フレックスタイム制の拡充
また、2020年や2023年、2024年にも、中小企業における割増賃金率の引き上げを含むいくつかの改正が行われています。
勤怠管理システムを導入していると、こうした改正にいち早く気がつくことができます。
法改正があった場合には必ず改正後の規制に対応したアップデートがありますし、法改正が行われる前にシステム上でメッセージが届くことも多いです。
勤怠管理システムを導入するデメリット・コスト
勤怠管理システムにはさまざまなメリットがありますが、当然ながら導入する際にはコストがかかります。
社員にシステムの使い方などを説明するのには手間がかかりますし、会社の規模が大きいと初期費用や月額利用料も高額になりがちです。
勤怠管理システムの導入時にこうしたデメリットを考慮していないと、「思ったほどの効果がなかった」となりかねません。以下で詳しく解説しますが、それぞれのデメリットごとに対策を講じておくことが大切です。
導入時の社員への説明などコストがかかる
勤怠管理システムを導入する際には、社員に対する説明コストがかかります。
社員に対する説明を怠ると、せっかく導入した勤怠管理システムが社内に浸透しない可能性があります。
「システムがあるが、結局Excelで管理している」という状況になると、勤怠管理システムの導入費用も無駄になってしまうでしょう。
勤怠管理システムを導入する際には、社内チャットや社内ミーティングなどで社員にシステムの周知をする必要があります。使い方だけでなく、システムのメリットや意義も交えて伝えることがコツです。
なお、その際には以下の3方面ごとに説明内容を変えましょう。
- 一般社員
- 上司
- 人事部
一般社員に対して説明する際は、基本的なツールの操作方法や打刻手順の説明がメインとなります。
一方、上司に対して説明する際には、部下の勤怠情報を確認する方法や、打刻が上手くいっていない場合の対応方法などを説明しましょう。
残業や有給についても、「月の半分時点で20時間以上残業がしていたら本人に伝える」など、一定のルールを共有しておくのがおすすめです。
人事に対しては、データの処理方法やシステムの運用方法を説明します。
必要に応じて、勤怠管理システムに関する不明点を質問できるヘルプデスクを設置するのも効果的です。
会社の規模が大きいとその分システム利用料もかさむ
勤怠管理システムには、金銭的なコストも発生します。勤怠管理システムにかかるコストは、主に以下の2種類です。
| 料金 | 費用の目安 | タイミング |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円〜数十万円 | 導入時の一回のみ発生 |
| 月額料金 | 100〜500円/人 | 毎月、利用アカウント数に応じて発生 |
初期費用は、勤怠管理システムを導入する際の1回だけ発生する費用です。ブラウザ上などで操作するクラウド型の勤怠管理システムであれば、初期費用がかからないケースもあります。
大手企業向けのものや、オンプレミス型でカスタマイズ機能が充実しているようなものは、数万円〜数十万円程度を見積もっておきましょう。
初期費用以外にも、勤怠管理システムには月額料金が発生します。システムによって異なりますが、利用アカウント数に応じて値段が決まるケースが多いです。
例えば1アカウント200円のツールで50人の社員を管理するのであれば、毎月10,000円が固定費用として発生します。
費用を少しでも安く抑えるコツは、ズバリ「自社にとって必要十分な機能を持ったシステムを選ぶこと」です。機能が豊富なツールは一見便利そうに見えますが、そうしたツールは料金も高い傾向があります。
事前に勤怠管理システムで自動化したい業務をリストアップして、自社に必要な機能を取捨選択しましょう。システムによっては、一部機能がオプション料金となっている場合もあるので注意してください。
既存の勤怠管理方法からの変更が大変
勤怠管理システムを導入する場合、すでに何らかの方法で勤怠管理を行っていることと思います。勤怠管理方法の変更には手間がかかるため、注意が必要です。
例えばExcelで社員ごとに勤怠管理している場合は、社員名簿を勤怠管理システム上へアップロードする必要があります。
年度の途中で切り替える場合など、タイミングによってはこれまでの勤務状況の引き継ぎも必要です。勤怠管理方法の変更にあわせて、業務報告書や日報のフォーマット、マニュアルなどを書き換えなければいけないこともあるでしょう。
こうしたデメリットを最小限に抑えるためには、余裕を持ったスケジュールを設定しておくことが大切です。
間違っても、「システム稼働日に全社的な切り替えを行う」といったことは避けてください。導入から本格運用までは、中小企業の場合で最低1〜2週間、大企業の場合は1ヶ月以上余裕を持たせておくことがおすすめです。
システムエラーが起こると正確に勤怠管理ができなくなる
勤怠管理システムの弱点に、システムエラーが挙げられます。
稀ではありますが、勤怠管理システム側の不具合で、サーバーと正常に通信できなくなる場合があります。この場合、サーバーが復旧するまで正常に打刻はできないので、あとから打刻し直すといった対応が必要です。
また、システムエラーではありませんが、人為的なミスによって打刻が正確にできないケースも考えられます。
誤って出勤日以外に打刻してしまったり、打刻に必要なICカードを紛失・破損してしまったりすることもあるでしょう。こうした場合も、正常に勤怠管理ができなくなってしまいます。
対策としては、以下の2つが重要です。
- 勤怠管理の代替手段をあらかじめ考えておく
- あとから打刻時刻を修正できるシステムを導入する
例えば「正常に打刻できない場合は、Slackで上司に出勤時刻・退勤時刻を報告すること」といったルールを定めておくことが考えられます。
システムによってはあとから打刻時刻を修正できるので、こうした機能を活用するのも便利です。
各社の勤怠管理システムを比較する際のポイント
勤怠管理システムは、各ベンダーからさまざまなものが販売されています。各社の製品を比較する際には、以下のようなポイントを意識しましょう。
- 機能と料金
- カスタマイズ性
- 使いやすさ
- テスト利用や連携の可否
- サポート体制
各システムの特徴を見極め、自社にマッチしたものを選ぶことが大切です。
自社の規模に見合った機能・料金か?
勤怠システムを選ぶ際にまず見るべき点が、機能と料金です。
出退勤の打刻機能や休暇管理機能はどの勤怠管理システムにも搭載されていますが、以下のような機能は差が出るポイントです。
- シフト管理機能
- 予実管理機能
- レポート機能
- 中抜けや早退、遅刻への対応
システムによって対応している場合とそうでない場合があるので、よく確認しておきましょう。
また、打刻方法の豊富さもチェックポイントです。共有パソコンやモバイル端末で打刻するパターンが多いですが、システムによってはICカードや生体認証での打刻に対応していることもあります。
ただし、打刻方法が豊富だと料金も高くなるので、予算とのバランスを勘案することが重要です。
料金に関しては、以下の2つに分けてチェックしてください。
- 初期費用
- 月額料金
中小企業の場合は、初期費用がかからないシステムがおすすめです。
反対に、高度なカスタマイズが必要な場合や、大企業で複雑な就業規則がある場合は、初期費用を払ってでも高機能なものを導入しましょう。
月額料金はアカウント数に応じた従量課金が主流ですが、中には「月額3,980円で固定」といったシステムも存在します。
自社の就業規則に合ったカスタマイズができるか?
勤怠管理システムを選ぶ際は、自社の就業規則と照らし合わせることもポイントです。
例えば就業規則で以下のような働き方を導入している場合は、これらに沿った打刻をシステムで正常に処理できるか確認しましょう。
- フレックスタイム制
- リモートワーク
- 裁量労働制
- 3交代制
ちなみに、フレックスタイム制に対応している勤怠管理システムは多いですが、裁量労働制や3交代制などまでカバーしているものは少ないです。
休日や休暇に関しても、以下の点がカスタマイズできるかチェックしてみてください。
- 半日休暇
- 会社独自の特別な休暇
- 産休や育休
例えば有給休暇に関しては、半日単位や時間単位での取得を可としている場合もあるでしょう。
この場合は、半日や時間単位で休暇を計上できるシステムが必須です。福利厚生の一環として定めている特別な休暇がある場合も、システムでそれらを処理できるかチェックする必要があります。
管理者や利用者にとって使いやすいシステムか?
勤怠管理システムを導入する際のチェックポイントの一つとして、操作性や利便性も挙げられます。
勤怠管理システムは、年齢もITリテラシーも異なるすべての社員が使うツールです。
打刻のしやすさはもちろんですが、休暇の申請や登録が簡単に行えるか、残業時間や有給休暇の取得状況をわかりやすく表示できるかなどを総合的にチェックしましょう。
なお、よくある失敗が「管理者側の画面が使いづらく、上司から不満が出る」というケースです。最近のシステムだと「打刻の操作そのものが難しい」ということはほとんどありませんが、打刻記録の管理は煩雑な場合もあります。
上司のITリテラシーにばらつきがある場合には、シンプルな管理画面のものを選ぶか、操作方法を説明する動画が用意されているものを選ぶ方がよいでしょう。
後述するように、一部の勤怠管理システムでは本契約前のテスト利用が可能です。ツールの使いやすさは、テスト利用中によくチェックしてみてください。
本契約前にテスト利用ができるか?
本契約前にテスト利用できるかどうかも、勤怠管理システムを選ぶ際のポイントです。
勤怠管理システムのテスト利用に関しては、以下の3パターンがあります。
- 機能制限つきの無料プランがある
- 期間限定で本契約期間と同じ機能を無料利用できる
- 無料期間がない
無料プランが用意されているツールは、「10アカウントまで無料で作成できる」「打刻のみ無料で、休暇申請やワークフロー機能は有料」といったパターンが多いです。スモールスタートで運用を始める場合は、無料プランから始めてみることもおすすめです。
システムによっては、本契約期間と同等の機能を1〜2ヶ月の間、無料で使える場合もあります。こちらの場合は、より本契約期間に近い条件でシステムをテストすることが可能です。
なお、テスト期間中には実際に社員へシステムを使ってもらうことがポイントです。
人事部だけでテストしていると、どうしても「上司の管理画面が使いづらい」といった点を見逃してしまう可能性があります。社員と上司にも協力してもらい、現場の声を吸い上げるのが大切です。
既存システムを利用している場合は連携・引き継ぎできるか
すでに何らかのシステムを運用している場合は、連携や引き継ぎに関しても注意が必要です。特に注意すべきポイントとしては、以下の2点が挙げられます。
- 既存の勤怠管理方法からの引き継ぎ
- 給与管理・労務管理など周辺システムとの相性
例えば現在Excelで勤怠管理を行っているのであれば、内容を引き継ぐ際にCSV形式でのデータ取り込み機能が必要です。
もちろん一からシステム上でデータを作り直すことも手ですが、社員の人数によっては膨大な工数が発生する可能性もあります。スムーズな導入のためにも、データの引き継ぎ方法はベンダー側の担当者まで入念に確認することがおすすめです。
周辺システムとの相性に関しては、「ベンダーを揃える」ことが最も手っ取り早い解決策です。例えば業界大手のfreeeは「freee勤怠管理Plus」と「freee人事労務」を販売しており、これらの間でデータの連携が可能です。
基本的に同じベンダーから販売されているツールであれば、「他社システムよりも相性が悪い」ということはまずありません。状況によっては、勤怠管理や労務管理をワンストップで処理できるERPを導入することも手です。
不明点・不具合があった場合にすぐサポートしてくれるか
サポート体制も、勤怠管理システムを選ぶ際のチェックポイントです。
勤怠管理システムのサポートは、以下の3つのフェーズに分けられます。
- 導入時のサポート
- テスト運用時のサポート
- 本運用時のサポート
導入時に関しては、「ベンダーが初期設定を行うパターン」と「自社で初期設定して、不明点は問い合わせるパターン」の2つがありますが、おすすめは断然前者です。
ベンダーに初期設定してもらえばミスが起こりづらいですし、自社に合った使い方や便利機能を教えてくれるかもしれません。ただし、勤怠管理システムの導入経験者がいる場合や、少しでも初期費用を安く済ませたい場合は、後者でも問題ないでしょう。
テスト運用時と本運用時には、以下のようなサポートが受けられます。
- チャットやビデオ通話によるサポート
- 定期的な保守点検(オンプレミス型の場合)
- システムの使い方に関する研修の実施
例えば「勤怠管理システムの導入後に就業規則が変更になった」というケースでは、どのようにしてシステムを設定すればよいのかわからなくなる可能性があります。こうした際に、チャットやビデオ通話でのサポートがあると安心です。
また、使い方を社員へ説明する研修を代行してくれたり、サポートしてくれたりするベンダーもあります。大企業向けのものであればあるほど、こうした充実したサポートを受けやすいです。
おすすめの勤怠管理システム10選の人気ランキング
マネーフォワード クラウド勤怠

| 運営会社 | 株式会社マネーフォワード |
| 料金形態 | ◎50名以下の法人 基本料金+従量課金+オプション◎51名以上の法人 初期費用+固定利用料金+超過利用料金 |
| 料金 | ◎50名以下の法人 スモールビジネスプラン 年払い:35,760円(2,980円/月) 月払い:3,980円/月◎50名以下の法人 ビジネスプラン 年払い:59,760円(4,980円/月) 月払い:5,980円/月◎51名以下の法人 要相談 |
「マネーフォワード クラウド勤怠」は、クラウド会計やクラウド経費なども扱う大手マネーフォワード社が出しているクラウド型勤怠管理システムです。
出退勤の打刻、シフト管理、残業や有給の管理など一般的な機能は全て備わっているため、基本的な機能を簡単に導入したい会社におすすめです。
また、給与計算ソフトや他の人事労務ツールとも簡単に連携でき、勤怠関連のデータを一括で管理・集計できる点も人気のポイントといえます。
パソコンやスマートフォンから場所を問わず利用できるため、リモートワークを導入している会社でも従業員の勤怠を正確に管理可能。
実際の導入企業からはサポート対応の手厚さも評価されており、初めてシステムを導入する担当者にも安心のサービスです。
【マネーフォワード クラウド勤怠の特徴】
- 給与計算ソフトなど他サービスとスムーズに連携可能
- パソコン・スマホから手軽に打刻可能
- 豊富な導入実績と充実したサポート体制
ジョブカン勤怠管理

引用:ジョブカン勤怠管理
| 運営会社 | 株式会社DONUTS |
| 料金形態 | ユーザー数と利用機能数による従量課金 |
| 料金 | 無料プラン:0円/月(機能制限あり)
有料プラン:200〜500円/月(最低200円、1機能追加ごとに+100円) |
ジョブカン勤怠管理は、出退勤管理の他にシフト管理・休暇申請管理・タスク管理など様々な機能がついたクラウド勤怠管理システムです。
ジョブカン勤怠管理には無料プランもあり、初期費用やサポート費用をかけずにミニマムスタートできることも特徴の一つ。
有料プランであっても、1ユーザーあたり200〜500円/月という低価格な従量課金制のため、SaaSに費用を割きたくない中小企業でも導入しやすいでしょう。
ジョブカンシリーズには給与計算や経費精算などもあり、勤怠データをジョブカン給与計算へ連携することで給与計算業務まで一貫して効率化できるため、社内システムをジョブカンシリーズで統一して導入している会社も多いです。
スマートフォンアプリやICカード打刻、Slack連携による在席確認などモバイル・リモート対応も万全で、医療機関をはじめ多様な業界で累計25万社以上の導入実績があります。
大手ならではのサポート体制も整っており、初めてのシステム導入でも安心できるでしょう。
【ジョブカン勤怠管理の特徴】
- 必要な機能を選択して組み合わせ可能な高いカスタマイズ性
- スマホやICカード・Slackなど多彩な打刻方法に対応
- 導入実績10万社以上を誇る信頼のサービス
freee勤怠管理Plus

引用:勤怠管理システムのおすすめなら|freee勤怠管理Plus
| 運営会社 | freee株式会社 |
| 料金形態 | ユーザー数よる従量課金 |
| 料金 | 1ユーザーあたり300円/月 |
freee勤怠管理Plusは、クラウド会計ソフトで知られるfreeeが提供する、勤怠管理機能に特化したサービスです。
初期費用不要で1人あたり月額300円の従量課金制で利用でき 、紙の出勤簿やタイムカードを利用していたような会社に特におすすめできます。
freeeの他サービスを利用している場合、勤怠データはそのままfreeeの給与計算機能や年末調整機能と連携できるため、出退勤の記録から給与計算・社会保険手続きまで一貫してクラウド上で完結できる点もポイント。
もちろんパソコンやスマホでの打刻もでき、在宅勤務を取り入れている会社でも、人事担当者はリアルタイムに勤怠状況を把握できます。
操作性とサポートも充実しており、初めてシステムを導入するといった中小企業からの支持も高く、労務管理システムのシェアNo.1として多くの導入実績があります。
【freee勤怠管理Plusの特徴】
- 勤怠から給与計算・労務手続きまで一元管理可能
- PC・スマホ対応で場所を問わず打刻
- クラウド人事労務ソフトシェアNo.1の信頼性
KING OF TIME

引用:勤怠管理システム KING OF TIME(キングオブタイム)
| 運営会社 | 株式会社ヒューマンテクノロジーズ |
| 料金形態 | ユーザー数による従量課金 |
| 料金 | 1ユーザーあたり300円/月 |
KING OF TIMEは国内の勤怠管理クラウド市場でシェアNo.1を誇る勤怠管理システムで、1ユーザーあたり月額300円で全ての機能が利用でき、初期費用も不要なため、中小企業でもコストを抑えて導入しやすいのが特徴です。
打刻手段はICカードや指紋認証、顔認証、スマホアプリ、GPS打刻、QRコードなど非常に豊富で 、出社・在宅を問わず確実な勤怠記録ができるため、人事担当者の負担も減らすことができるでしょう。
記録された勤怠データは各種給与ソフトへの出力やAPI連携が可能で、既に給与計算システムを導入している場合でもスムーズに連動できる点も人気のポイントです。
また、36協定管理や残業アラート、有給管理など法令遵守の機能も充実しており、サポート体制や導入実績の多さから初めて勤怠管理システムを導入したい中小企業にもおすすめなシステムです。
【KING OF TIMEの特徴】
- 初期費用なし・追加料金なしの明瞭な定額制
- ICカード、指紋、GPS打刻など業界最多の打刻手段に対応
- 在宅勤務の位置情報管理やシフト・有休管理など柔軟に対応可能
ジンジャー勤怠

引用:クラウド型勤怠管理システム「ジンジャー勤怠」|jinjer株式会社
| 運営会社 | jinjer株式会社 |
| 料金形態 | ユーザー数による従量課金 |
| 料金 | 1ユーザーあたり300円/月 |
ジンジャー勤怠は、大手の人事労務クラウド「jinjer」シリーズの勤怠管理システムで、初めての担当者でも扱いやすいシンプルな画面設計と豊富な機能が魅力です。
打刻から申請承認、シフト管理まで一貫してシステム化されているので従業員も利用しやすく、さらに他のjinjerシリーズ(経費精算や人事管理等)と連携することでさらにバックオフィス業務を一元化できます。
スマートフォンアプリにも対応しており、リモートワーク中の従業員もしっかりと出退勤を記録できるため、勤怠の透明化もできるでしょう。
またサポート窓口は電話・チャット等で365日24時間対応しており 、システム導入から不具合時のサポートまで手厚い支援を受けられるため、初めてシステムを導入したい企業にもおすすめできます。
【ジンジャー勤怠の特徴】
- システムに不慣れでも使いやすいUIと直感的な操作性
- 英語・タイ語・ベトナム語など多言語対応でグローバルな会社にも向いている
- 365日24時間サポートによる導入・運用フォロー体制
楽楽勤怠
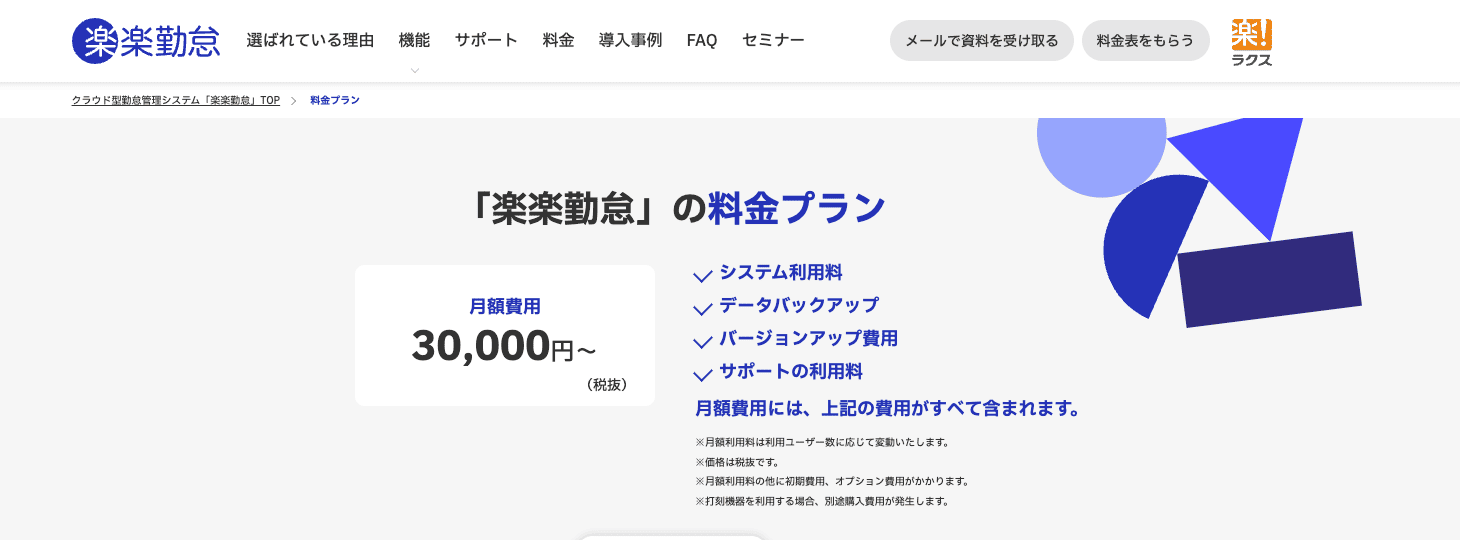
引用:クラウド型勤怠管理システム「楽楽勤怠」【公式】|株式会社ラクス
| 運営会社 | 株式会社ラクス |
| 料金形態 | 初期費用+月額費用+オプション費用 |
| 料金 | 月額費用:30,000円/月〜 |
楽楽勤怠は、中小企業での導入実績が豊富な経費精算システム「楽楽精算」のシリーズで、勤怠データと経費精算データを連動させることで、外回りの営業職が多い企業でも勤怠管理から交通費精算までのフローを一貫させることができます。
導入時は、専門スタッフによる丁寧なヒアリングやシステム設定の代行支援があり、運用開始後も定期的な見直しや改善提案などアフターサポートが充実しているため、初めて勤怠管理システムを導入する企業にもおすすめです。
Webブラウザからでもスマホからでもの打刻できるため、在宅勤務を導入している会社でも従業員の勤怠をきちんと管理することができます。
【楽楽勤怠の特徴】
- 企業規模や運用ルールに応じた柔軟なプランがある(小規模会社向けの低価格プランあり)
- 同社の経費精算ソフト「楽楽精算」とシームレスに連携できる
- 導入支援から運用改善まで手厚いサポート体制
AKASHI

| 運営会社 | ソニービズネットワークス株式会社 |
| 料金形態 | 従量課金制+オプション費用 |
| 料金(タイムレコーダープラン) | 1ユーザーあたり200円/月 |
| 料金(スタンダードプラン) | 1ユーザーあたり300円/月 |
| 料金(プレミアムプラン) | 1ユーザーあたり400円/月 |
AKASHIは最低限の勤怠打刻機能に絞ったプランから、シフト管理やプロジェクトごとの工数管理、フレックス勤務への対応まで含むプランの3プランが用意されており、自社のニーズに応じて1人あたり月額200円~400円で利用できます。
初期費用は0円で、導入時には社労士資格者による就業ルールに沿った設定サポート(50,000円~)をオプションとしてつけることも可能なため、複雑な勤怠制度を採用している会社でも安心して導入できる点が人気のポイント。
スマートフォンやICカードでの打刻、在宅勤務者の勤務管理などの基本機能も充実しており、給与計算ソフトとのデータ連携機能も備えているため、担当者の管理工数を大幅に削減することができます。
大手ソニーグループが運営している勤怠管理システムなので、導入にあたっての信頼性は担保されているでしょう。
【AKASHIの特徴】
- 機能に応じた3つのプランから選択可能
- テレワークやシフト勤務、工数管理まで幅広く対応
- 社労士と相談できる初期設定サポートでスムーズ導入
HRMOS勤怠

引用:【ハーモス(HRMOS)勤怠】無料で使える勤怠管理システム
| 運営会社 | 株式会社ビズリーチ |
| 料金形態 | ユーザー数による従量課金 |
| 料金 | 1ユーザーあたり100円/月〜 |
HRMOS勤怠はビズリーチが運営する勤怠管理システムで、累計6万社以上に導入されているシンプルで使いやすいクラウド勤怠管理システムです。
利用人数が30名未満の場合は基本機能を完全無料で利用することができ、31名以上の場合でも1ユーザーあたり100円からという低価格で導入することができます。
Webブラウザやスマートフォンからの打刻のほか、SlackやLINEから出退勤報告を行う連携機能もあるため、そのようなチャットツールを利用しているベンチャー企業にもおすすめでしょう。
日次・月次の勤怠データをワンクリックでCSV出力できるほか主要な給与計算ソフトへのデータ連携にも対応しており、勤怠から給与計算までの業務負担を大幅に軽減できます。
【HRMOS勤怠の特徴】
- 従業員30名までは無料で利用可能
- シンプルで直感的に操作しやすい画面構成
- 給与ソフトやSlack・LINEと連携し在宅勤務も管理容易
キンコン

引用:キンコン
| 運営会社 | 株式会社ソウルウェア |
| 料金形態 | ユーザー数による従量課金 |
| 料金 | 1ユーザーあたり220円/月〜 |
キンコンは、交通系ICカードをかざすだけで勤怠打刻ができ、そのICカードの乗車記録から交通費精算も同時に行える便利なクラウド勤怠管理システムです。
導入時の初期費用はかからず、勤怠管理と交通費精算を1ユーザーあたり月額220円という低価格で利用できるため、初期費用の負担を減らしてシステムを導入したい中小企業におすすめといえます。
スマートフォンやPCからの打刻にも対応しており、出社時はICカード、テレワーク時はブラウザやモバイルからといった柔軟な運用が可能です。
現在では最大60日間の無料トライアル期間が用意されているため、本導入前に使い勝手を確認できる点も安心材料です。
担当者も従業員も直感的に使えるUIが評判なので、初めてシステムを導入する企業にもおすすめです。
【キンコンの特徴】
- 交通系ICカード連携で出退勤打刻と交通費精算を自動化
- 60日間の無料トライアルでじっくり検証可能
- サイボウズや他勤怠システムとの外部連携機能が豊富
レコル

| 運営会社 | 中央システム株式会社 |
| 料金形態 | ユーザー数による従量課金 |
| 料金(勤怠管理プラン) | 1ユーザーあたり100円/月 |
| 料金(勤怠管理+給与計算プラン) | 1ユーザーあたり300円/月 |
レコルは低価格ながら勤怠管理に必要な機能はすべて含まれており、打刻からシフト管理、残業計算、有給休暇管理、36協定アラートまでを追加料金なしで利用できます。
従業員の休暇申請や残業申請ワークフローも標準搭載しているため、今まで紙やExcelで勤怠管理をしていた中小企業でもスムーズに導入できるでしょう。
集計した勤怠データはMoney Forwardクラウド給与やfreee人事労務など主要な給与ソフトに連携できるため、経理担当者の負担を削減できます。
初期費用もかからず契約期間の縛りもないため、導入のハードルが低い点も中小企業に嬉しいポイントです。
【レコルの特徴】
- 1ユーザー月100円で勤怠に必要な機能を全て利用可能
- 有給休暇管理や36協定管理なども追加料金なしで搭載
- 他社の給与計算ソフトと連携でき、データ連動が容易
勤怠管理システムの導入検討時によくある質問
この記事の最後に、勤怠管理システムの導入時にありがちな質問にまとめてお答えします。勤怠システムについてわからない点がある場合は、ぜひ参考にしてください。
無料で利用できる勤怠管理システムはある?
はい、勤怠管理システムの中には無料で利用できるものもあります。代表的なものは以下の通りです。
- HRMOS勤怠
- ジョブカン勤怠管理
- タブレット タイムレコーダー
- Teasy
上記4つのツールは、どれも期間制限なく無料で利用することができます。
ただし、いずれもシステムも無料で全機能を使えるわけではないので注意してください。例えばHRMOS勤怠管理の場合は、利用人数が30人以下の場合に限り無料で利用可能です(広告・機能制限あり)。ジョブカン勤怠管理の場合は、一部の機能に制限があります。
また、「Hachikin」の90日間無料、「キンコン」「FocusU タイムレコーダー」の2ヶ月無料など、期間制限つきで無料利用できるシステムも存在します。
勤怠管理システムの料金相場は?
勤怠管理システムの相場は、以下の通りです。
- 初期費用……0円〜数十万円
- 月額料金……1アカウントあたり100円〜500円
ブラウザなどを介して利用するクラウド型の場合は、「初期費用0円」「月額料金100円〜300円(1アカウントあたり)」程度を見込んでおきましょう。月額料金は、例えば100アカウント利用する場合は毎月10,000円〜30,000円程度になります。
会社のシステムに直接インストールするオンプレミス型の場合は、「初期費用数万円〜数十万円」「月額料金200円〜500円」が相場です。
クラウド型より相場が高い理由には、クラウド型よりもメンテナンスコストがかかるのと、そもそもオンプレミス型には大企業向けの高機能なシステムが多いという背景があります。
なお、初期費用と月額費用以外にも、以下の料金が発生することがあります。
- サポート料・メンテナンス料
- オプション機能
これらの値段はシステムによって大きく異なるので一概には言えませんが、例えばオプション機能の場合は「1つの機能追加につき、月額利用料がプラス100円/人」といったパターンが多いです。
勤怠管理システムはリモートワークにも対応していますか?
多くの勤怠管理システムは、リモートワークにも対応しています。代表的なリモートワーク向けの機能は、以下の通りです。
- 自宅PCやスマートフォンで打刻
- リモートワークと出社日に分けて勤務日をカウント
- 打刻した時点での位置情報を記録
リモートで打刻できるようになれば、出社することなく社員の出退勤時刻を正確に記録することができます。
なお、リモートワークに対応するための勤怠管理システムを導入する際は、クラウド型のものを選択しましょう。
クラウド型のシステムであれば、自宅や外出先からもシステムにアクセスできます。オンプレミス型のシステムだと、システムをインストールした社用パソコンのみしかアクセスできないので注意してください。
おすすめの勤怠管理システム|まとめ
勤怠管理システムは、社員の出退勤時刻を記録したり、残業時間や有給取得状況を管理したりするうえで非常に便利なツールです。
昨今ではリモートワークやフレックスタイム制の導入を目指す企業も多く、勤怠管理の業務は複雑になりつつあります。これまではExcelで管理できていたとしても、今後はミスや手戻りが増え、効率が低下してしまうかもしれません。
勤怠管理システムの機能やサポートはベンダーによって大きく異なるため、いかに最適なものを見極めるかが導入成功の秘訣です。
ぜひこの記事を参考にして、自社にぴったりな勤怠管理システムを見つけてください。
SHARE
関連記事
-
2025年10月06日(月)
【2025年最新】ハラスメント社外相談窓口のおすすめ比較10選!外部委託の費用相場やメリットは?
- おすすめ

-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】決済代行サービスのおすすめ比較10選|機能・メリット・導入時の注意点まで徹底解説
- おすすめ
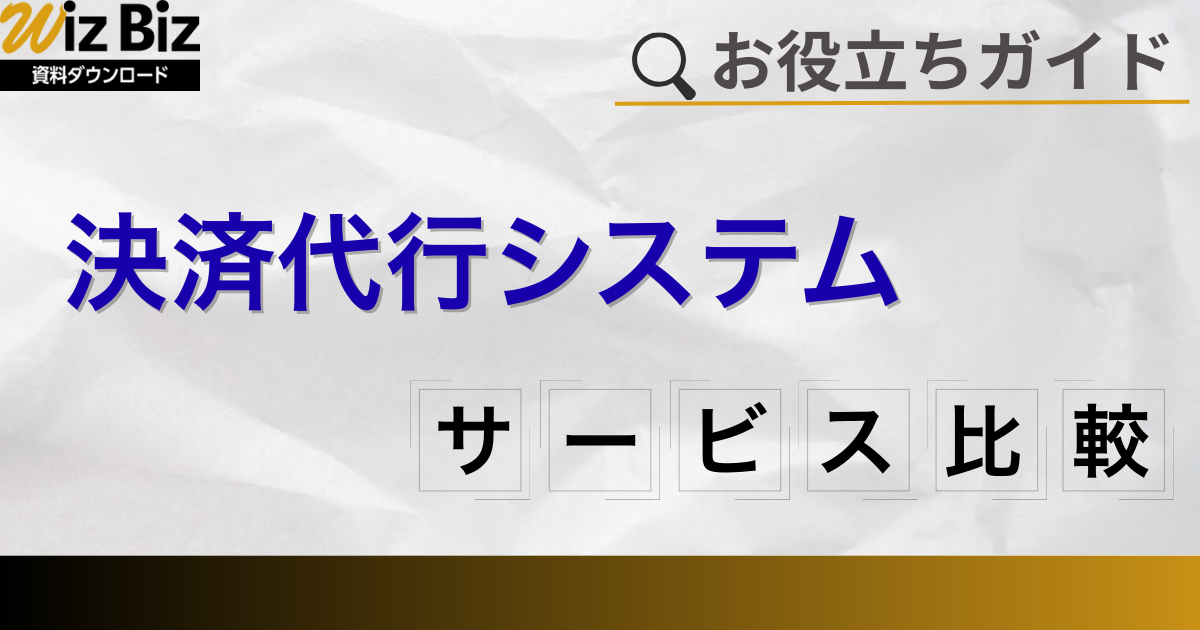
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】メール配信システムのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気のメール配信システムを解説
- おすすめ
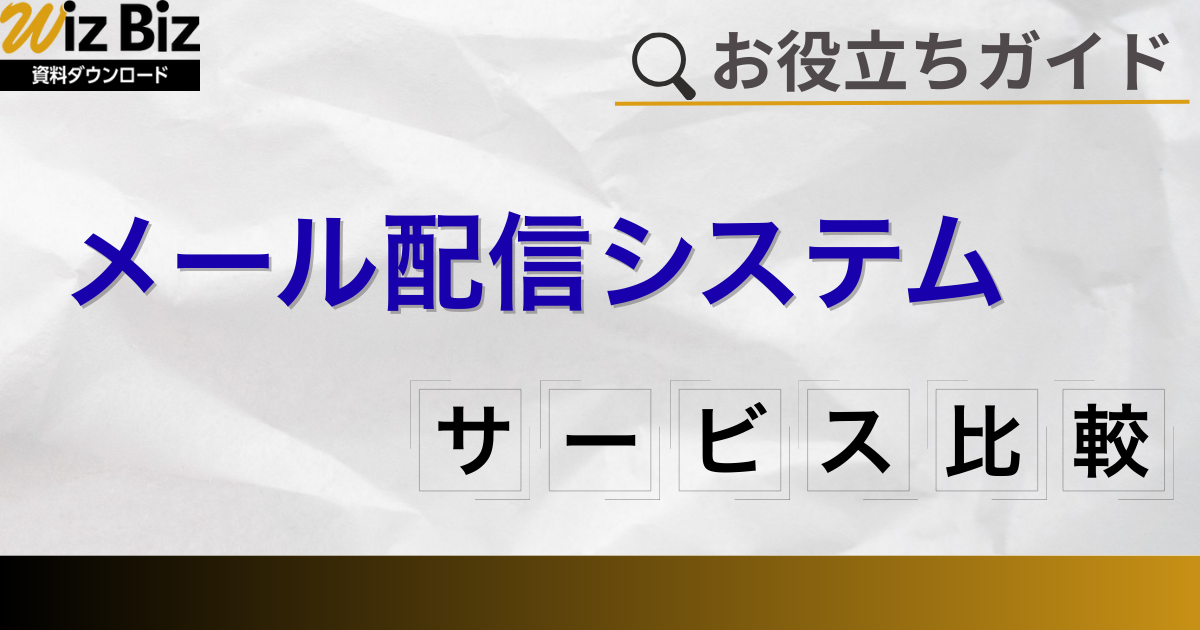
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】SFAツールのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気営業支援システムを解説
- おすすめ
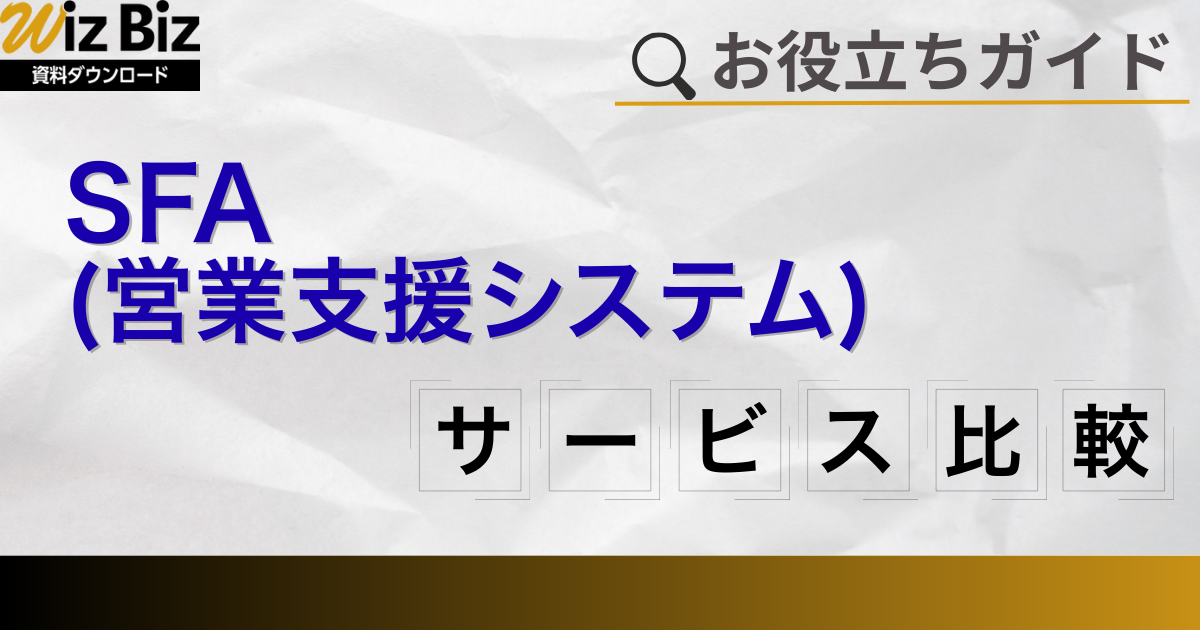
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】名刺管理ソフト・アプリのおすすめ比較10選|機能別・料金別で人気製品を比較!
- おすすめ
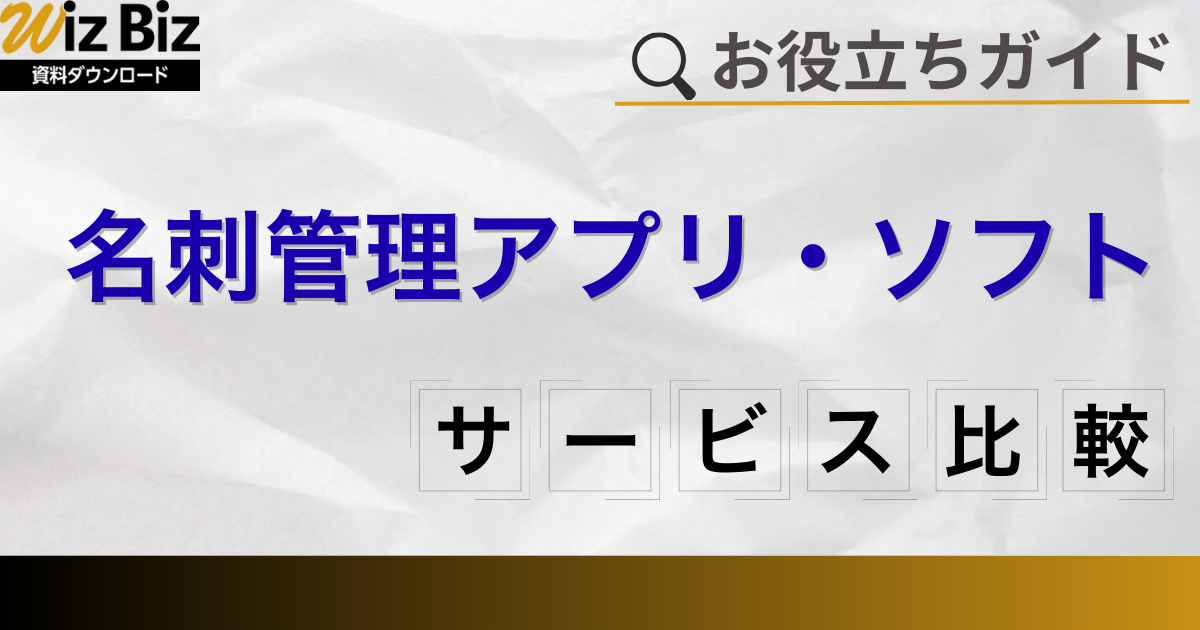
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】POSレジのおすすめ比較10選|業界別・機能別の人気POSレジやタブレット端末で使えるシステムは?
- おすすめ
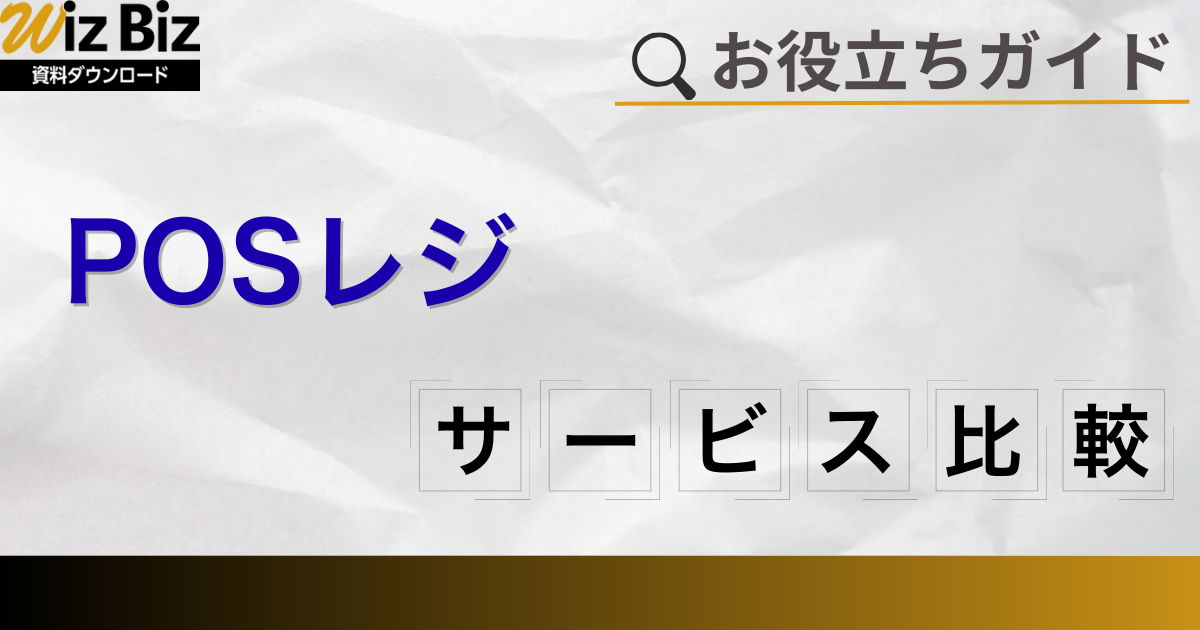
おすすめサービス
- 【2025年度版】企業が使うべき書類管理・電子化サービス10選!ペーパーレス化を実現する選び方と注意点を解説
- 一覧へ戻る
- IVR(電話自動音声応答システム)のおすすめ比較5選【2025年最新】適切な電話応対でオペレーションコストを削減する方法

ダウンロード候補に
追加しました!

削除しました