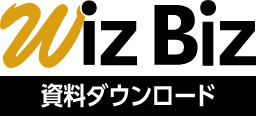お役立ちガイド

職場において、いわゆる「モンスター社員」に直面したことはありませんか?
モンスター社員とは、周囲との協調性に欠け、業務遂行に支障をきたす社員のこと。昨今はハラスメントへの意識が高まる一方で、権利ばかり主張するモンスター社員の問題行動を適切に指導できないケースも増えています。
本記事では、モンスター社員の特徴や悪影響、生まれる原因を詳しく解説します。モンスター社員への効果的な対処法・指導方法も紹介するので、ぜひ職場のマネジメントにお役立てください。
モンスター社員とは?
モンスター社員とは、職場で問題行動を繰り返す社員のことを指します。問題行動の典型例は、次の通りです。
- 業務命令に従わない
- 遅刻や欠勤を繰り返す
- 同僚へ攻撃的な態度を取る
モンスター社員は自身の行動が組織全体へ与える影響を理解せず、むしろ「自分は正当な権利を主張しているだけだ」と考えていることも多いです。
しかし、モンスター社員は周囲の社員の士気や生産性を大きく低下させます。
例えば、部署内であるメンバーが毎回締め切りを守らず、そのフォローを他の社員が行わなければならない状況を想像してみてください。当初は協力的だった周囲も、次第に「なぜ自分たちばかりが負担を負うだろうか?」と不公平感を抱くようになります。
こうした状況が続くと、優秀な人材ほど「この職場にいても評価されない」と感じて離職を検討するなど、職場全体に悪影響が及ぶのです。
組織全体のパフォーマンスを維持するためにも、モンスター社員には早めに対処する必要があります。
モンスター社員の特徴と問題点
モンスター社員には、次の4つの特徴が挙げられます。
- 自己中心的で周りに無関心
- 会社への評価が低く、自分への評価が高い
- 遅刻や欠勤を繰り返す
- 上司の指示に従わない
社員にこれらの兆候が見られた場合には注意が必要です。管理職や人事部は、このような特徴を持った社員がいないか常に意識しておきましょう。
自己中心的で周りに無関心
自己中心的な行動は、モンスター社員の最大の特徴といっても過言ではありません。
モンスター社員は、自分自身の都合を最優先に考える傾向があります。チーム全体への気配りがないばかりか、むしろチーム全体の生産性を低下させる行動を取ることも多いです。
例えばチームで仕事を進めているとき、モンスター社員は「自分の担当部分は終わった」と報告します。しかし、次の工程を担当する同僚への引き継ぎは一切行いません。確かに担当部分自体は終わっていても、これでは結果的に周囲の仕事が滞り、全体の業務効率は低下します。
また、モンスター社員は他者の感情や周囲の状況にも無関心です。同僚が困っていても、進んで手を差し伸べることがありません。その結果チーム全体の結束力が弱まり、組織のパフォーマンスが徐々に低下していくのです。
会社への評価が低く、自分への評価が高い
モンスター社員は、会社や上司に対して批判的な態度を取る一方で、自分への評価は過剰に高い傾向があります。
彼らは「会社が自分を正当に評価できていない」「上司が無能だから仕事がうまく進まない」などと考えがちです。例えば人事評価の結果が悪い場合には、「評価制度が間違っている」などと主張するでしょう。客観的に見ればコミュニケーションや勤務態度に問題があることも多いですが、本人はそれらをあまり認識していません。
モンスター社員が評価制度や上司への不満を口にすると、組織全体のマネジメントがうまく機能しなくなります。また、建設的なフィードバックを素直に受け入れられないので、本人の成長も見込めません。
遅刻や欠勤を繰り返す
周囲に、遅刻や欠勤を繰り返す社員はいないでしょうか。こうした勤怠の乱れも、モンスター社員にありがちな問題行動です。
具体的には、以下のような行動が挙げられます。
- ほぼ必ず遅刻して出勤する
- 重要な会議の日に限って体調不良で欠勤する
- 繁忙期に突然「明日から3日間休みます」と連絡してくる
本人は、こうした行動に対して罪悪感を持っていません。「休暇を取得するのは当然の権利なので」と開き直っているため、上司が注意しても改善されないことが多いです。
モンスター社員のこのような態度は、本人の業務を滞らせるだけでなく、他の社員の負担を増やすことにつながります。例えば6人チームで仕事を進めている場合、1人が欠席すると他の社員の負担は単純計算で普段の1.2倍です。
欠勤が1回や2回であれば「お互いさま」で済みますが、これが何度も続くと、真面目に働く社員が尻拭いをする状況が発生します。
組織内に不公平感が蔓延し、「あの人は休んでも誰かがやってくれるから楽でいいよね」などと不満の声が上がり始めるでしょう。長期的には、優秀な人材が流出するリスクも高まります。
上司の指示に従わない
上司からの業務指示や指導を無視することも、モンスター社員に見られる傾向の一つです。
「その方法は非効率だと思う」「自分のやり方の方が正しい」などと主張し、組織のルールや上司の業務命令を軽視します。上司が「急ぎでやってほしい」と指示した仕事を後回しにして、自分のやりたい仕事だけを優先することもしばしばです。
当然ながら、モンスター社員がこのような行動を取ると、組織内のマネジメントが立ち行かなくなります。
仮に上司がモンスター社員の行動を黙認した場合、「あの人は上司の言うことを聞かなくても許されるのか」という不満感が他の社員にも広がり、真面目に指示に従っている社員までもが「従わなくてもいいのではないか」と考え始める危険性があります。反対にモンスター社員を厳しく叱責すると、「ハラスメントではないか」などと主張し始めるでしょう。
まさに、管理職にとって頭痛の種とも言うべき存在になってしまうのです。
モンスター社員が生まれてしまう理由
モンスター社員の具体的なイメージが湧いた方も多いでしょう。それでは、今後に期待して採用したはずの社員が、どうしてこのようなモンスター社員となってしまうのでしょうか。
モンスター社員が生まれる原因は、主に以下の3つです。
- 「ハラスメント」という言葉を拡大解釈してしまう
- 上司がパワハラを恐れて注意できない
- メンタルに問題を抱えている
近年はハラスメントが社会問題化していますが、モンスター社員はこれを拡大解釈してしまう傾向にあります。また、メンタルに問題を抱えており、精神的に不安定な状況に置かれていることも少なくありません。
単に本人を責めるだけでなく、これらの原因を解消してあげることが、モンスター社員の誕生を防ぐ第一歩です。
「ハラスメント」という言葉を拡大解釈してしまう
昨今、さまざまな業界で「ハラスメント」が取り沙汰されるようになりました。しかし、モンスター社員はこの言葉を拡大解釈する傾向があります。
例えば納期を守れなかったことに対して上司が注意すると、「人格を否定された」「ハラスメントだ」などと反発するのです。「この報告書は誤字が多いので修正してください」などと事実に基づいた指示を出しても、まるで感情的な叱責を受けたかのように感じてしまいます。
この原因の一つは、組織内で「ハラスメント」という言葉の線引きが曖昧な点です。モンスター社員は単に「パワハラ」という言葉を盾に自己防衛しているのではなく、正当な指導を本心から「パワハラ」と捉えてしまっている可能性があります。
上司がパワハラを恐れて注意できない
最近はハラスメントへの懸念から、上司側が指導をためらうケースも増えています。
多くの企業でパワハラ対策が進んだ昨今、一度パワハラが認定されると出世ルートから外れたり、降格や懲戒解雇などの厳しい処分を下したりすることも多いです。このため、「厳しく注意するとパワハラだと訴えられるのではないか」という不安が先行する上司が増えてきています。
実際、管理職のおよそ60%が「パワハラと指導の違いは曖昧だ」と感じているというデータもあるほどです。
このような状況が、結果的にモンスター社員の増加を招いています。上司側がモンスター社員の指導へ消極的になることで「この程度の行動は許容される」と誤解し、さらに問題行動がエスカレートするという悪循環に陥るのです。
メンタルに問題を抱えている
モンスター社員の問題行動の背景には、メンタル面での問題が隠れている場合があります。
うつ病や適応障害などの精神的な困難を抱えているために、業務遂行や対人関係に支障をきたしているケースです。最近では、「大人の発達障害」の存在も指摘されています。
このような場合、本人に悪意はなくても、心身の不調を原因とする遅刻や欠勤が増えたり、業務に集中できなくなったりします。発達障害の特性によって、職場の暗黙のルールを理解できずに周囲と摩擦を起こすケースもあるでしょう。
メンタル面の問題が疑われる場合には、産業医や専門家と連携して対応する必要があります。記事の後ほどで紹介するように、外部相談窓口の設置もおすすめです。
モンスター社員の具体例
モンスター社員の問題行動は、さまざまな形で職場に現れます。
モンスター社員にありがちな問題行動の具体例をまとめました。
| 具体的な問題行動 | |
| 勤務態度 |
|
| 協調性 |
|
| その他 |
|
モンスター社員は、勤務成績が悪いことが多いです。遅刻や欠勤によって周囲に負担をかけるばかりか、チーム全体の士気も低下させかねません。また、協調性が欠けていることも多く、人間関係の悪化や心理的安全性の低下を招くことがあります。
この他、深刻なケースでは暴言や暴力行為などが見られることも。社内外での行動によって、会社の信頼を傷つける場合もあります。
モンスター社員の適切な対応方法
モンスター社員は非常に厄介な存在ですが、当然ながらいきなり厳しい対応を取るわけにはいきません。急に降格や懲戒処分を告げてしまうと、企業側が訴えられる可能性もあります。
モンスター社員には、いくつかの段階に分けて対応することがポイントです。
- 直ちに指導をする
- 定期的な面談を行う
- 異動などで様子を見る
- 厳格な懲戒ルールを設ける
まずは指導や面談を行い、本人のメンタルに問題がないか確認しましょう。それでも対応が難しい場合には異動などで様子を見て、最終的な手段として懲戒ルールなどの厳格な対応を検討します。
また、これらとは別に「外部の相談窓口を設置する」という対応もおすすめです。外部の相談窓口には産業医や弁護士などの専門家が在籍していることも多いため、モンスター社員へ効果的に対処できます。
直ちに指導をする
モンスター社員の問題行動を確認したら、まずは速やかな指導を行いましょう。放置する期間が長くなればなるほど、本人は「この程度は許容される」と誤解しかねないからです。
パワハラだと反論されないようにするためには、感情的にならず、具体的な事実に基づいて冷静に伝えることがポイントです。「君はいつもだらしないね」といった抽象的な表現ではなく、「先週の月曜日と水曜日に、始業時刻の9時を過ぎて9時30分頃に出社していますね」などと、どの行動が問題なのかを明確に説明しましょう。
なお、対応に時間がかかりそうな場合は、早い段階から指導内容を記録しておくことがおすすめです。日時や場所、指導内容、本人の反応などを残しておくことで、後から「パワハラを受けた」と訴えられた際の対策になります。
定期的な面談を行う
一度の指導で改善されない場合は、定期的な面談を設定しましょう。
週に1回〜月に1回程度を目安に1on1ミーティングを設定し、業務状況や行動変化を確認します。単に叱責するのではなく、本人の成長をサポートすることを意識してみてください。
また、本人の言い分や事情も丁寧に聞き取ることが大切です。例えば、「業務の進め方で困っていることはありませんか」「遅刻の原因はありますか」などの質問を投げかけてみましょう。
もしかすると、業務量が本人のキャパシティを超えていたり、家庭の事情で睡眠時間が確保できていなかったりするケースがあるかもしれません。こうした原因がある場合には、必要に応じて業務量を調整するといった対応が必要です。
異動などで様子を見る
なかなか改善が見られない場合、現在の部署や業務が本人に合っていない可能性もあります。面談でも対応が難しければ、配置転換を通じて様子を見てみましょう。
人間関係のストレスや業務内容とのミスマッチが原因で問題行動が生じている場合、環境を変えると改善されることがあります。例えば「営業部で顧客対応に問題があった社員が、内勤の事務職に配置転換したら実力を発揮し始めた」といった事例は多いです。
ただし、異動が根本的な解決策になるとは限りません。「困った社員を押し付けられた」などと、受け入れ側の部署が不満を持つ可能性もあるからです。異動先の部署に対する負担も考慮しながら、異動の経緯を関係者間で丁寧に共有してみてください。
厳格な懲戒ルールを設ける
どうしても対応が難しい場合、懲戒措置の検討が必要です。
就業規則に基づいた懲戒ルールを設け、段階的な処分を行います。以下のような処分を設けることが一般的です。
- 口頭注意
- 書面での警告
- 減給
- 出勤停止
- 解雇
ただし、こうした措置を取る際は訴訟リスクに注意が必要です。処分の前に弁明の機会を設ける、弁護士と連携しながら対応するなど、慎重に手続きを進めましょう。
外部相談窓口を設置する
社内だけでは解決が難しい場合、外部相談窓口の設置を検討してみてはいかがでしょうか。
外部相談窓口とは、社内で生じたさまざまな問題を外部の専門家に相談できるサービスのことです。相談には産業医やメンタルヘルスの専門家、弁護士などが対応するため、社外の客観的な視点から、専門性の高いアドバイスを受けることができます。
外部相談窓口を設置することで、モンスター社員へ効果的に対処できるようになります。例えば産業医に相談すれば、本人の問題行動が何らかの疾患や障害に起因するものかどうかを専門的に判断してもらえるでしょう。懲戒処分や解雇を検討する場合にも、弁護士や労務コンサルタントのアドバイスが非常に参考になります。
また、モンスター社員自身に外部相談窓口を利用してもらうことも可能です。この場合、本人の相談内容を客観的に記録しておけるので、後々のトラブルを防ぐことにつながります。上司の意見には批判的な態度を取る社員でも、外部相談窓口の専門家の意見であれば素直に従うこともあるでしょう。
モンスター社員への対応でお困りの場合には、ぜひ外部相談窓口の設置を検討してみてください。
モンスター社員|まとめ
モンスター社員の存在は、チーム全体に大きな影響を及ぼします。
遅刻や欠勤を繰り返すと、本人だけでなく周囲に負担がかかりかねません。「業務指示に従わない」といった反発的な態度も、組織全体の生産性が低下する要因になります。こうした問題行動は周囲のモチベーションにも悪影響を及ぼすため、管理職が頭を悩ませるのも無理はありません。
一方、モンスター社員の背後にはメンタルの問題などのさまざまな問題が隠れている可能性があります。単に厳しく叱責するだけでは、問題の根本的な解決につながらないことも多いです。面談や配置転換などの段階的な対応を行ったり、外部相談窓口を設置して客観的な意見をもらったりする必要があります。
モンスター社員は、組織全体に関わる問題です。早期に対処して、組織全体への悪影響を最小限に抑えることが肝心です。
ぜひこの記事を参考にモンスター社員への適切な対応を進め、組織全体のマネジメントを強化してみてはいかがでしょうか。
SHARE
関連記事
-
2025年10月06日(月)
権利ばかり主張するモンスター社員にはどう対応したらいい?問題社員の具体的な対策を解説!
- コラム

-
2025年10月28日(火)
【インタビュー】目指すは「AI財務部長」|三井住友銀行の新サービス「Trunk」の全貌とは?
- コラム
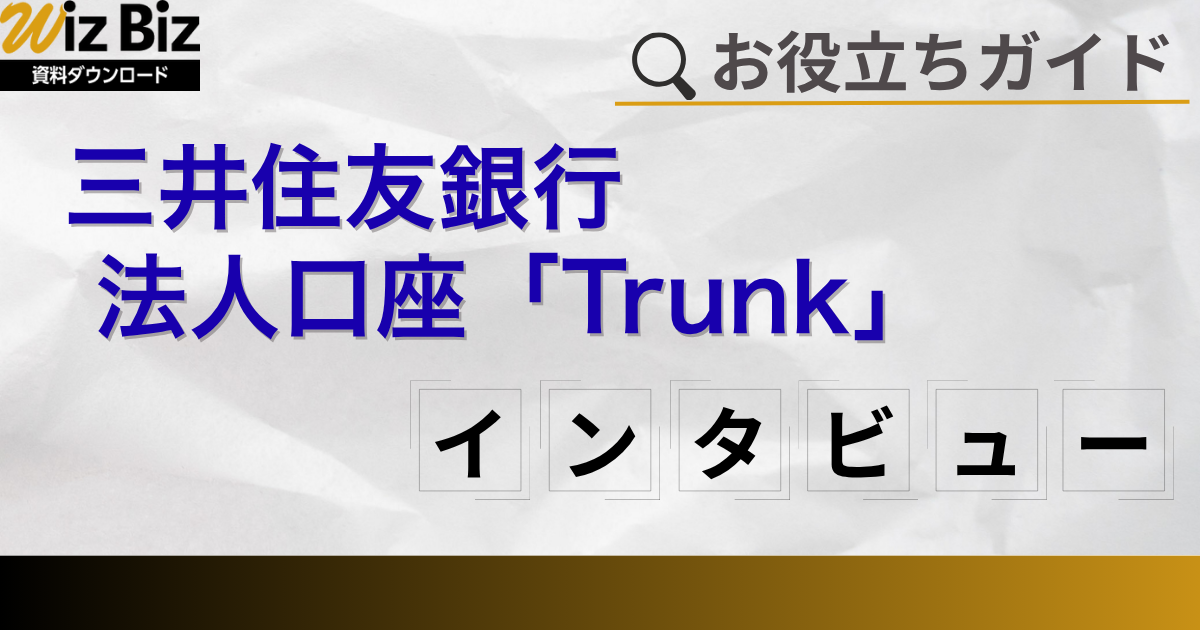
-
2025年07月31日(木)
AIは仕事で使っても問題ない?業務での活用事例と注意点・困った時の対処法を解説
- コラム

-
2025年05月28日(水)
BtoBマーケティングの要「リード獲得」の方法を解説!オフライン・オンライン施策の違いとは?
- コラム

-
2025年02月16日(日)
社長が「やるべき仕事」と「よくある悩み」とは?社長の業務効率化を実現するサービス5選を解説
- コラム

-
2024年10月24日(木)
すぐに実践できる「経費削減」!会社のキャッシュフローを改善する目的と方法を解説!
- コラム

おすすめサービス
- 【2025年最新】決済代行サービスのおすすめ比較10選|機能・メリット・導入時の注意点まで徹底解説
- 一覧へ戻る
- 【2025年最新】ハラスメント社外相談窓口のおすすめ比較10選!外部委託の費用相場やメリットは?

ダウンロード候補に
追加しました!

削除しました