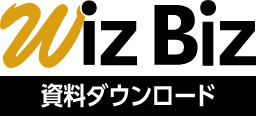お役立ちガイド

職場でのハラスメント対策を強化したい企業担当者の方も多いのではないでしょうか。
ハラスメントは日本企業にとって深刻な問題の一つですが、その対応はなかなか難しいものです。厚生労働省が令和5年に公表した調査では、パワハラを受けた社員のうち実に約40%が泣き寝入りしていることが明らかになっています。
ハラスメント社外相談窓口は、こうした問題を防ぐうえでおすすめなサービスの一つ。導入することで、社内では相談しにくいハラスメントの問題に第三者が中立的な立場から対応し、解決へと導いてくれます。
本記事では、ハラスメント社外相談窓口のおすすめランキングを紹介します。料金相場や導入メリット、選定時のポイントも詳しく解説するので、ぜひ最後までお読みください。
ハラスメント社外相談窓口とは?
ハラスメント社外相談窓口とは、企業が外部の専門機関に委託して設置するハラスメント相談受付サービスです。導入すると、職場で発生したパワハラやセクハラ、マタハラなどの問題を、会社とは独立した第三者に相談できるようになります。
2022年4月に施行された改正労働施策総合推進法、いわゆる「パワハラ防止法」によって、中小企業にも職場におけるハラスメント防止措置を講じることが義務付けられました。
しかし、社内でハラスメント対応窓口を運用するハードルは高いことも事実です。ハラスメントに対応できる専門知識を持った人材は確保しづらいですし、社内相談だとどうしても引け目を感じてしまったり、適切な対応が取れなかったりすることもあります。
一方、社外相談窓口だと相談しやすい環境を確保することが可能です。社内窓口と異なり、相談者の匿名性を確保しながら中立的な立場でハラスメント問題に対応できます。
ハラスメント社外相談窓口では、専門のカウンセラーや弁護士、社会保険労務士などの専門家が相談を受け付けるサービスも多いです。また、どのサービスも電話やメール、チャット、WEBフォームなど複数の連絡手段を用意しており、相談者が利用しやすい環境を整備しています。
ハラスメント社外相談窓口のメリットと注意点
ハラスメント社外相談窓口を導入すると、パワハラ防止法の対策や職場環境の改善を実現できます。一方で、人間関係の些細なトラブルの相談が増えるなど、対応コストが上昇するといったデメリットも存在します。
導入時には、メリットと注意点をどちらも把握しておくことが大切です。
パワハラ防止法の対策になる
ハラスメント社外相談窓口を導入すると、パワハラ防止法へ確実に対応できます。
2022年4月に改正されたパワハラ防止法では、すべての企業に対してパワハラ対策が義務付けられています。違反した場合には厚生労働大臣による助言・指導・勧告の対象となるため注意が必要です。
パワハラ防止法に対応するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
- パワハラに関する指針を明確化して、従業員に周知すること
- パワハラの相談に対応できる体制を整備すること
- パワハラの相談があった場合には、適切かつ速やかに対応すること
社外相談窓口を設置することで、これらをすべて満たすことができます。
なお、企業にはセクハラやマタハラの防止措置も義務付けられています(男女雇用機会均等法第11条・育児・介護休業法第25条)。ハラスメント社外相談窓口を設置することで、これらの法律に対応できる点もメリットです。
社内窓口と違い、匿名・中立を保てる
ハラスメント社外相談窓口で相談に対応すると、匿名性と中立性を担保できます。
ハラスメント窓口を社内で運用すると、「相談したことが加害者や上司にバレるのではないか」「報復を受けるかもしれない」といった不安から、被害者が相談を躊躇するケースが生じます。規模の小さな企業では、「相談者と加害者が実は親しい関係にあった」といった可能性もあるでしょう。
社外相談窓口では、相談者の匿名性を保護することが可能です。パワハラ被害を企業へ報告する際も、相談者が特定されないように配慮された形で情報共有が行われるため、相談者のプライバシーが守られます。
また、対応するのは弁護士やカウンセラーなどの専門知識を持った第三者です。中立的な立場で対応できるため、相談者は安心して状況を説明できます。
匿名相談やチャットでの相談に対応しているサービスも多く、従業員の泣き寝入りを防ぐことが可能です。
リスクマネジメントの強化と離職の防止に繋がる
ハラスメントを放置すると、以下のように企業全体にとって深刻な事態を招きかねません。
- 被害者が精神的な病気を発症し、労災認定される
- SNSでハラスメント被害が拡散され、企業イメージが悪化する
- 優秀な管理職が加害者として懲戒処分を受け、仕事が回らなくなる
社外相談窓口があることで、問題の芽を早期に発見できるようになります。大きなトラブルに発展する前に当事者を引き離すなど、適切な解決策を見つけられるでしょう。さらに、「いつでも相談できる窓口がある」という安心感から会社への信頼が向上し、離職率が低下する効果も期待できます。
なお、ハラスメント社外相談窓口の多くは定時後まで相談を受け付けています。中には休日でも対応できるサービスもあるので、忙しい社員でも利用しやすいでしょう。
相談のハードルが下がるので無駄に件数が増える可能性もある
社外相談窓口を導入すると些細なことでも相談しやすくなりますが、無駄に相談件数が増える可能性があることも念頭に入れておきましょう。
「同僚が自分だけ挨拶してくれない」「上司の指導が厳しすぎると感じる」「自分だけ飲み会に誘われなかった」といったグレーゾーンは、多かれ少なかれどの職場にもあるものです。こうした線引きが難しいケースの相談件数が増えると、対応工数やサービス利用料の増加を招く可能性があります。
ハラスメント社外相談窓口の料金相場
ハラスメント社外相談窓口の料金相場は、以下のようになっています。従量課金制と定額課金制のサービスがあるので、企業規模や相談頻度に応じて適切なものを選択しましょう。
| 従業員数 | 月額料金相場 | 初期費用 | 特徴 |
| 100名以下 | 5,000円~ 20,000円 |
0円~ 50,000円 |
中小企業向け。 相談件数に応じた従量課金制が主流。 |
| 101名〜500名 | 20,000円~ 100,000円 |
50,000円~ 150,000円 |
従量課金・定額課金制の両方存在。 レポート作成などの付帯サービスも。 |
| 501名以上 | 100,000円~ | 150,000円~ 500,000円 |
研修対応やメンタルヘルスケアなどのサービスとセットのことが多い。 |
社外相談窓口では従量課金制を採用しているサービスが多いですが、その中にも以下の2種類が存在します。
- 人数に対する従量課金
- 相談件数に対する従量課金
例えば「ハラスメント相談窓口外部委託センター」は従業員10名ごとに月額1,000円ずつ課金(最初の9名までは月額4,980円)されますが、「ハラスメント等外部相談窓口サービス」は入電1件あたり5,000円という料金体系です。人数に対して相談件数が多ければ前者、少なければ後者が有利になります。
また、基本的な相談受付サービスに加えて、企業向けのレポート作成や管理職向け研修、ハラスメント防止セミナーなどのオプションサービスが利用できるものもあります。これらの費用は個別の見積もりとなるケースがほとんどです。
ハラスメント社外相談窓口を導入するべき企業
以下の3つの課題を抱える企業では、ハラスメント社外相談窓口の導入効果が特に高くなります。
- 従業員がなかなか定着しない
- 店舗などの現場を直接監視できていない
- ハラスメントの相談担当者が社内にいない
上記に該当する場合には、積極的に導入を検討してみましょう。
従業員がなかなか定着しない
社員の離職率が高いことにお悩みの場合、相談窓口の導入がおすすめです。
早期離職が多い企業では、ハラスメント問題が隠れた原因となっている可能性があります。表面的には「キャリアアップのため」「待遇への不満」といった理由で退職していても、実際にはハラスメントが原因で職場環境に耐えられなくなっているケースは多いです。
特に、以下のような兆候がある場合には要注意です。
- 入社3ヶ月以内の新入社員が複数退職している
- 特定の部署だけ離職率が異常に高い
- 退職面談時に「人間関係が合わなかった」という曖昧な回答が多い
こうしたケースでは、社外相談窓口を設置することで、これまで表面化していなかった問題を発見できる可能性があります。
また、相談窓口の存在自体が従業員の安心感につながります。その結果、職場環境への満足度向上や人材定着率の改善が期待できます。
店舗などの現場を直接監視できていない
複数の店舗・営業所を持つ企業やテレワーク中心の組織では、現場で発生する問題を本社が把握しづらいです。
例えば、店長がアルバイトに対してパワハラをしていても、アルバイトはなかなか本社へ相談する機会がないかもしれません。また、オンラインの1on1面談で上司が部下を厳しく叱責していても、周囲がそれに気づくことは難しいでしょう。
リモートワークでは、オフィス勤務よりもハラスメントの被害が顕在化しづらいです。これらに本社の人事部門がいち早く対応できなければ、事態はどんどん深刻化してしまいます。
ハラスメント社外相談窓口を設置することで、物理的に離れた現場で働く従業員も気軽に相談できる環境を整備することが可能です。多くのサービスは電話やチャットでも相談を受け付けているので、場所を問わずに被害を相談できます。
「現場との距離が遠い」とお悩みの企業は、ぜひ積極的にハラスメント社外相談窓口の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ハラスメントの相談担当者が社内にいない
ハラスメントの対応には、専門知識が必要です。
例えばハラスメントを相談された時に「我慢しろ」「気にしすぎだ」といった言葉を投げかけてしまうと、相談者を一層追い込んでしまいかねません。被害者の気持ちに寄り添わなければいけませんし、その後の対応に向けた証拠保全やプライバシーの保護といった措置も必要です。「相談を受けても法的な判断ができない」「どのような対応を取るべきかわからない」といった状況では、問題の解決どころか二次被害を引き起こすリスクもあります。
そうはいっても、ハラスメント対応の知識を持った人材を社内で探すことはそう簡単ではありません。中小企業では総務部の社員が人事を兼務することも多く、ハラスメント対応を専門に引き受ける社員は確保しづらいのが実情でしょう。
社外相談窓口を利用することで、カウンセラーや弁護士などの専門家による対応ができるようになります。社内の人的リソースが限られている場合でも、効果的なハラスメント防止体制を構築することが可能です。
ハラスメント社外相談窓口を比較する際のポイント
最適なハラスメント社外相談窓口を選択するためには、自社の課題や目的に合ったサービスを選ぶことが重要です。料金だけでなく、対応範囲やサポート体制、利便性などを総合的に比較してサービスを選びましょう。
メンタルケアやコンプラなど目的にあったサービスにする
ハラスメント社外相談窓口を選ぶ際は、自社の目的に合ったサービスを選択することが大切です。
一言で「ハラスメント社外相談窓口」といっても、それぞれのサービスごとに特徴や得意分野は異なります。単純なハラスメント相談はどのサービスでも利用できますが、メンタルヘルス支援やコンプライアンス強化、労務管理改善などの付帯サービスの有無では差がつきやすいです。
社員のメンタルヘルスを重視する企業では、臨床心理士やカウンセラーが在籍しているサービスが適しています。例えば日本産業カウンセラー境界が運営する「JAICOハラスメント相談窓口」には産業カウンセラーや社会保険労務士などの専門家が多数在籍しているため、相談者の不安に寄り添った対応が可能です。
一方で、リスク管理やガバナンス強化を重視する場合は、弁護士や社会保険労務士による専門的なアドバイスを受けられるサービスが向いています。例えば株式会社Zationが提供する「内部通報窓口」では、弁護士や社労士がハラスメントや法令違反、不正行為などの幅広い事案に対応してくれます。このほか、法律事務所が運営するサービスも多いです。
また、外国人従業員が多い企業では、ダイバーシティ対応や多言語対応に強いサービスを選択しましょう。日本公益通報サービス株式会社の運営する「日本公益通報サービス」は、英語での通報にも対応しています。
このほか、ハラスメント防止研修の実施をパッケージで提供しているサービスも複数あります。社内教育も検討している場合は、研修の有無も要チェックです。
料金とサービス内容のバランスを考える
料金とサービス内容のバランスも比較しましょう。
手軽なサービスでも基本的な相談受付機能は利用できますが、専門性の高い対応や詳細なレポート作成、企業向けのアドバイスなどは利用できない場合があります。
料金を検討する際は、まず月額定額制と従量課金制のどちらを選択するかが重要です。それぞれ、以下のケースが向いています。
| タイプ | 向いているケース |
| 月額定額制 |
|
| 従量課金制 |
|
月額定額制の方が予算管理しやすいですが、相談件数が少ない場合には費用が無駄になってしまいます。基本的には過去の自社の相談件数をもとに料金を試算すれば問題ありませんが、「外部相談窓口を設置したことで相談件数が増えた」というケースもあるので注意してください。
チャットや電話対応など連絡手段との相性
ハラスメント外部相談窓口では、さまざまな方法で社員のハラスメント相談に対応しています。サービス選びの際は、従業員の年齢層や働き方に応じて、自社に合った連絡手段が用意されているかを確認することが重要です。
若い世代が多い企業では、チャットやLINE連携による相談が好まれる傾向があります。一方で30代以降の社員が多い企業では、オンラインフォームやメール、電話での相談に対応しているサービスが向いています。Zoomなどを通じたオンライン面談に対応しているサービスもおすすめです。
また、サービスの利用時間も重要な比較ポイント。例えば夜勤やパートタイムの従業員が多い企業では、本社の営業時間外でも相談できる体制が必要です。また、外国籍の人材が多い場合には、英語や中国語への対応状況も確認しましょう。
おすすめのハラスメント社外相談窓口比較ランキング
おすすめのハラスメント社外相談窓口は、次の10社です。
- コマッタサン【アファアップ合同会社】
- メンタルヘルスサポート【ティーペック株式会社】
- Zation【株式会社Zation】
- リモート産業保健【株式会社エス・エム・エス】
- 日本公益通報サービス【日本公益通報サービス株式会社】
- クオレ・シー・キューブ【株式会社クオレ・シー・キューブ】
- ハラスメント等外部相談窓口サービス【RESUS社会保険労務士事務所】
- サポートメンタルヘルス【株式会社サポートメンタルヘルス】
- ハラスメントの外部相談窓口【よつば総合法律事務所】
- アンリ【株式会社ドクタートラスト】
それぞれの特徴について詳しく紹介します。自社に最適なサービスを選ぶ際の参考にしてください。
コマッタサン【アファアップ合同会社】
.jpg)
アファアップ合同会社が運営するコマッタサンは、主に中小企業を対象としたハラスメント相談窓口サービスです。
料金体系は次のようになっています。
| 初期費用 | 10,000円~ |
| フォームでの対応代行 | 10,000円~(月額) |
| 電話での対応代行(オプション) | 50,000円(月額) |
フォーム・電話での代行サービスのみを展開しているシンプルなサービスで、料金体系が明確でわかりやすい点が特徴です。中小企業などで、工数をかけることなく対応窓口を設置したい場合におすすめです。
ハラスメントに関する相談が寄せられた場合には、PDF形式の月次レポートを通じて内容を把握できます。申込みから最短1営業日で利用を始められるなど、スピーディーな対応も魅力の一つです。
こころのサポートシステム【ティーペック株式会社】
ティーペック株式会社が運営する「こころのサポートシステム」は、総合的なメンタルヘルスケアを包括したサービスです。臨床心理士や公認心理師、精神保健福祉士といった専門資格を持ったカウンセラーなどが連携しながら、相談者の心理面をサポートします。
こころのサポートシステムは、全国224箇所に設置されているカウンセリングルームでの対面相談に対応している点が最大の特徴。数あるハラスメント外部相談窓口サービスの中でも、対面でのカウンセリングができるサービスは珍しいです。
ハラスメント被害によるメンタルヘルス不調者に対しては、長期的なケアプランを作成し、復職支援まで一貫してサポートします。電話カウンセリングは平日9時〜21時、土曜日9時〜16時まで対応しているため、オフィスの営業時間外の相談も可能です。
社員のメンタルヘルスを包括的にサポートしたい場合にぴったりなサービスです。
Zation【株式会社Zation】
「Zation」は、実績豊富な弁護士や社会保険労務士が直接対応するハラスメント外部相談窓口。ハラスメントはもちろん、内部通報や労務に関する相談、法令違反などに幅広く対応してもらえるサービスです。
Zationの特色として、対応する専門家が実績豊富である点が挙げられます。書籍の執筆や講演などの実績が豊富な弁護士・社労士が多く在籍しているため、対応の信頼性が高いです。取引先企業も相談対象に含められるため、違法キックバック行為なども未然に防ぐことができます。
料金体系は、以下のようになっています。
| スタンダードプラン | プレミアムプラン | |
| 初期費用 | 50,000円 | 100,000円 |
| 〜100名 | 月額15,000円 | 月額35,000円 |
| 〜300名 | 月額30,000円 | 月額55,000円 |
| 〜500名 | 月額45,000円 | 月額75,000円 |
| 〜1,000名 | 月額56,000円 | 月額90,000円 |
オプションで、ハラスメント基礎研修や職場コンプライアンス研修などを依頼することも可能です。
リモート産業保健【株式会社エス・エム・エス】
株式会社エス・エム・エスのリモート産業保健は、産業保健サービスと連携したハラスメント相談窓口です。
ハラスメント相談には、匿名での電話相談やWebフォームで対応しています。電話対応は夜間・休日も可能で、専門知識を持った心理カウンセラーに相談するため対応品質も高いです。
リモート産業保健の特徴は、産業保健サービスと連携している点。産業医の選任が必要な企業に対して、産業医と産業看護職の2名体制で訪問・リモートのサポートを実施しています。ストレスチェックや衛生委員会の立ち上げといったコストがかかりがちな業務も、リーズナブルな価格で依頼することが可能です。
※料金体制は要問い合わせ
日本公益通報サービス【日本公益通報サービス株式会社】
日本公益通報サービスは、内部不正とハラスメントの両方に対応できる専門性の高い相談窓口サービスです。精神科医や弁護士、社会保険労務士、産業カウンセラーといった各分野の専門家が在籍しており、公益通報事案に対してチームを組んで対応します。
女性スタッフが初期対応を行うため、セクハラやマタハラなどを相談する際の心理的負担を和らげられる点がメリット。通報は、メールと電話のどちらでも可能です。公益通報が発生した場合には、相談者の秘密を守りつつ、企業のコンプライアンス部門のみに情報提供を行います。
相談窓口は、申込みから最短5日で開設することが可能です。
※料金体制は要問い合わせ
クオレ・シー・キューブ【株式会社クオレ・シー・キューブ】
株式会社クオレ・シー・キューブは、ハラスメントのない職場を目指すことを目的としたコンサルティングを手掛けている企業です。30年以上・合計1,500社に及ぶ社外相談窓口運営の実績を基に、ハラスメント問題の専門的知識と豊富な経験を活かしたサービスを展開しています。
主なサービス内容は、次の6つです。
- 社外対応窓口
- ハラスメント対策向けコンサルティング
- ハラスメント対策の教材提供
- ハラスメント問題対応
- ハラスメント予防対策
- 研修・セミナー
このうち社外対応窓口では、職場の人間関係のような些細な内容から、パワハラやセクハラに至るまで幅広い相談を受け付けています。上位プランでは、生き方や働き方、コンプライアンスに関する相談をすることも可能です。
パワハラ行為者の行動変容を促すためのオリジナル教材も提供しているなど、ハラスメント対策のための総合的なサポートに強みがあります。ハラスメントの抜本的な対策を講じたい場合には、ぜひ導入を検討してみてはいかがでしょうか。
ハラスメント等外部相談窓口サービス【RESUS社会保険労務士事務所】
ハラスメント等外部相談窓口サービスは、RESUS社会保険労務士事務所が運営するハラスメント外部相談窓口です。2022年に改正されたパワハラ防止法に完全対応していることが特徴で、これまでに400社以上からの相談実績を持ちます。
対応方法はメール・電話の2通りで、電話の対応時間は10時〜17時です。相談時間の上限や制限がないため、不安なことがある場合にはしっかり寄り添ってもらうことができます。匿名での相談も可能です。
オプションで、報告レポートを利用することができます。社会保険労務士事務所が運営しているため、法律・実務の両面を踏まえた実効性の高いアドバイスをもらえる点が強みです。
料金体系は、次のようになっています。
- 月額利用料⋯⋯5,000円(一律)
- 報告レポート料⋯⋯5,000円/1件あたり
中小企業など、手軽にパワハラ防止法へ対応したい場合に便利なサービスです。
サポートメンタルヘルス【株式会社サポートメンタルヘルス】
ストレスチェックから医療機関紹介までをワンストップで提供する、総合的なメンタルヘルスサービス。
医療法人をベースとする企業が運営しているため、医療機関との連携やメンタルヘルス面でのサポートが充実している点が強みです。産業医や公認心理師といった国家資格保有者も多数在籍しているため、相談対応の品質にも定評があります。
料金体制は次の通りです。
| 従業員数 | 料金(月額) |
| 1名〜9名 | 5,000円〜 |
| 10名〜29名 | 7,000円 |
| 30名〜49名 | 10,000円 |
| 50名〜99名 | 15,000円 |
※従業員数100名以上は別途見積もり。
また、以下のオプションが利用可能です。
- メンタルヘルス研修
- 個別カウンセリング
- ストレスチェック
- 産業医派遣
ハラスメント対策と社員のメンタルヘルスケアをセットで推進したい場合におすすめなサービスの一つです。
ハラスメントの外部相談窓口【よつば総合法律事務所】
よつば総合法律事務所が運営する「ハラスメントの外部相談窓口」は、法律事務所としての専門性を活かしたハラスメント外部相談窓口サービスです。
弁護士が21名(2025年10月時点)在籍しているため、法的な判断が必要なケースや、訴訟リスクを伴う深刻な事案にも適切に対応できます。これまでに440社以上の企業と顧問契約を締結しているなど、法律事務所としての実績も豊富です。
主なサービス内容は、次のようになっています。
- 外部相談窓口の設置
- 相談後の事実認定
- 企業への報告書作成
オプションで、ハラスメント防止のための就業規則の策定や周知文書の作成、ハラスメント研修の実施も可能です。
料金体系は次のようになっています。
| 従業員数 | 月額 |
| 〜99名 | 20,000円 |
| 100名〜299名 | 30,000円 |
| 300名〜499名 | 50,000円 |
※500名以上は要問い合わせ
なお、上記はメール対応のみの料金で、電話受付は別料金が発生するため注意してください。
アンリ【株式会社ドクタートラスト】
株式会社ドクタートラストの「アンリ」は、医療関連の国家資格者が対応するEAPサービスです。ハラスメント相談窓口の設置も行っており、保健師や精神保健福祉士、公認心理師などの専門資格を持った人材が相談に対応します。相談があった場合には、医療的な見解も交えながら、相談者のプライバシーを守りつつ企業に対して的確なアドバイスを行います。
メンタルだけでなく、フィジカルの問題も一元的に対応できる点がアンリの大きな強みです。例えば栄養や育児、ダイエットなどの相談にも対応しています。マタハラやセクハラに関しても、産業保健に精通した医療職による専門的な対応が可能です。
産業医との連携も行っており、希望に応じて産業医の紹介やストレスチェックなども実施しています。
※料金は要問い合わせ
ハラスメント社外相談窓口|まとめ
ハラスメント社外相談窓口について、基本的な仕組みや導入メリット、選定ポイントなどをご理解いただけたでしょうか。
2022年4月の改正パワハラ防止法の施行によって、企業におけるハラスメント対策は法的義務となりました。ハラスメント窓口を設置すると、パワハラ防止法へ適切に対応できますし、職場の心理的安全性向上や離職防止にもつながります。
本記事でもお伝えしたように、ハラスメントに対処するためには専門的な知識が必要です。ハラスメントが社会問題化している昨今、社内だけでは対処が難しい複雑な事案も増えてきているでしょう。
社員のメンタルヘルスを守るためにも、ぜひハラスメント外部相談窓口の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
その際に、本記事の内容が少しでもお役に立てば幸いです。
SHARE
関連記事
-
2025年10月06日(月)
【2025年最新】ハラスメント社外相談窓口のおすすめ比較10選!外部委託の費用相場やメリットは?
- おすすめ

-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】決済代行サービスのおすすめ比較10選|機能・メリット・導入時の注意点まで徹底解説
- おすすめ
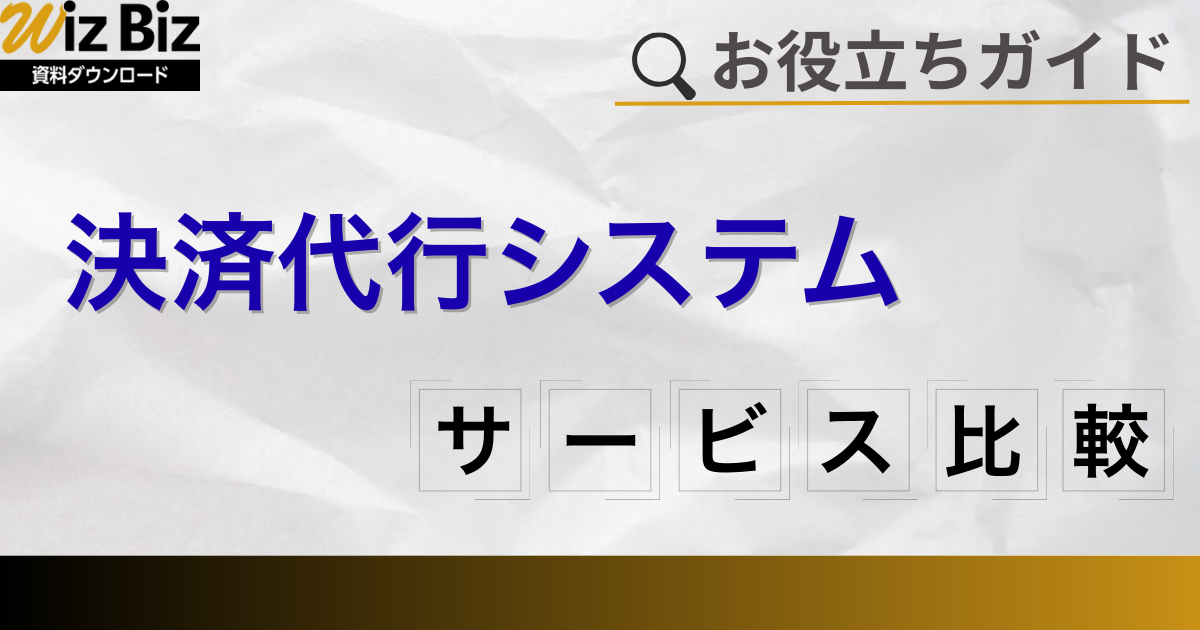
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】メール配信システムのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気のメール配信システムを解説
- おすすめ
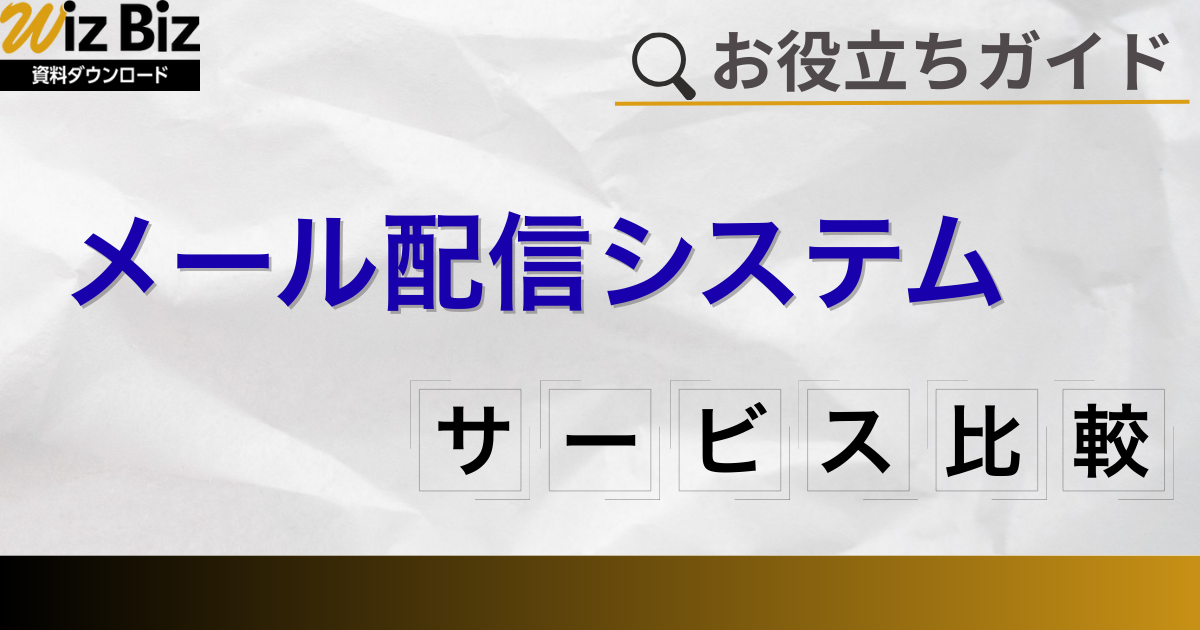
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】SFAツールのおすすめ比較10選|業界別・機能別で人気営業支援システムを解説
- おすすめ
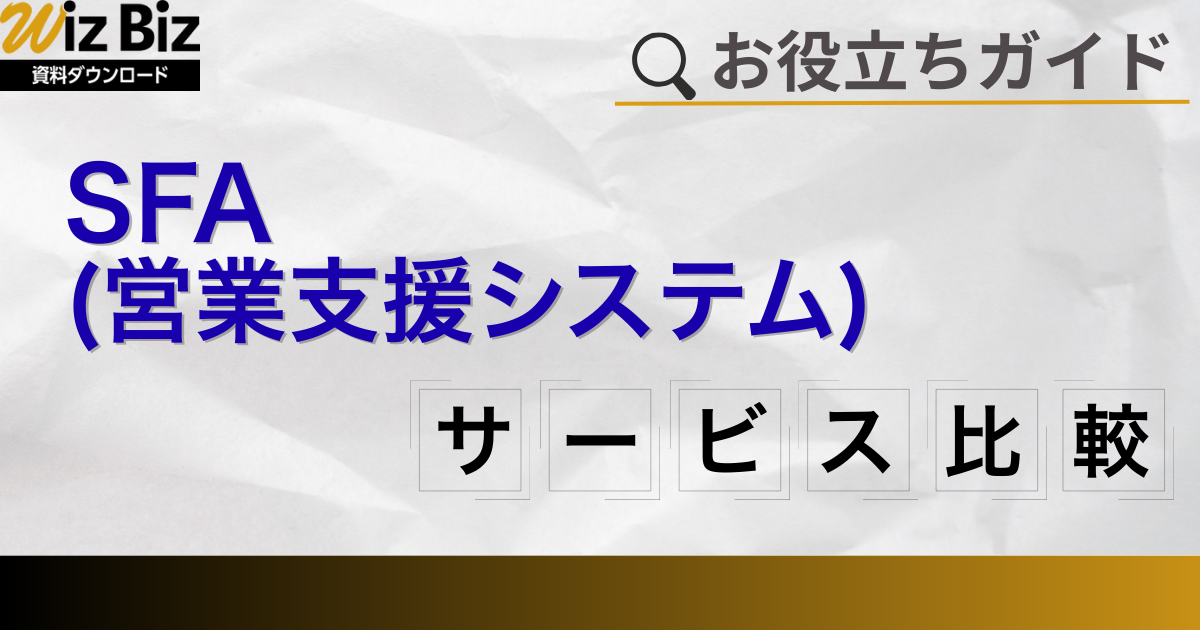
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】名刺管理ソフト・アプリのおすすめ比較10選|機能別・料金別で人気製品を比較!
- おすすめ
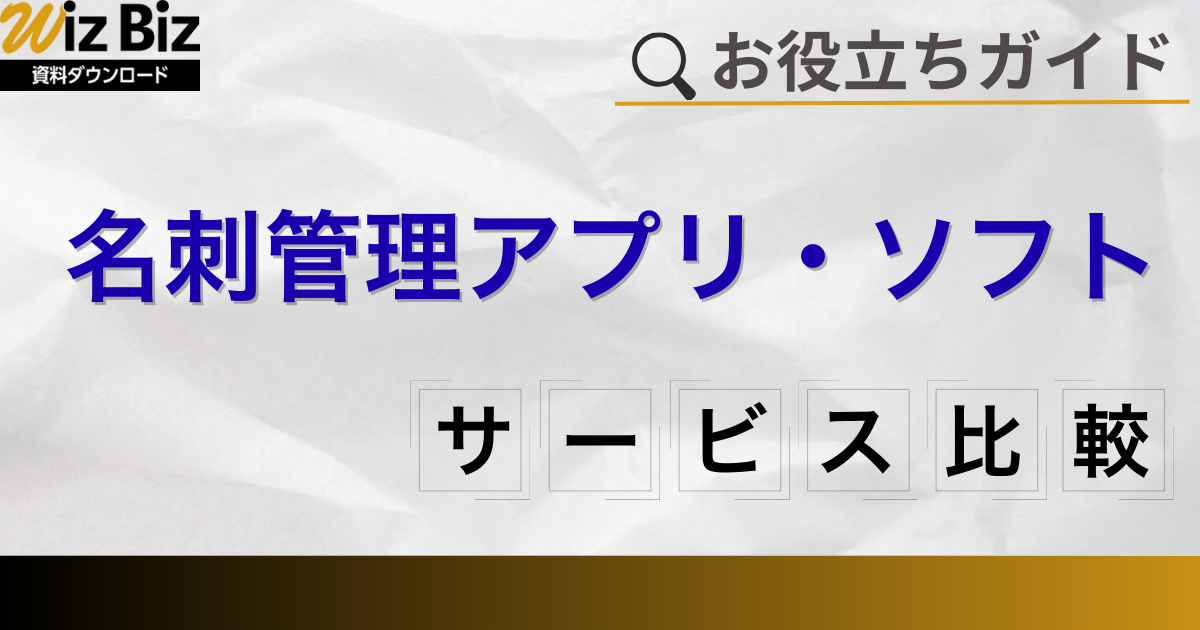
-
2025年09月21日(日)
【2025年最新】POSレジのおすすめ比較10選|業界別・機能別の人気POSレジやタブレット端末で使えるシステムは?
- おすすめ
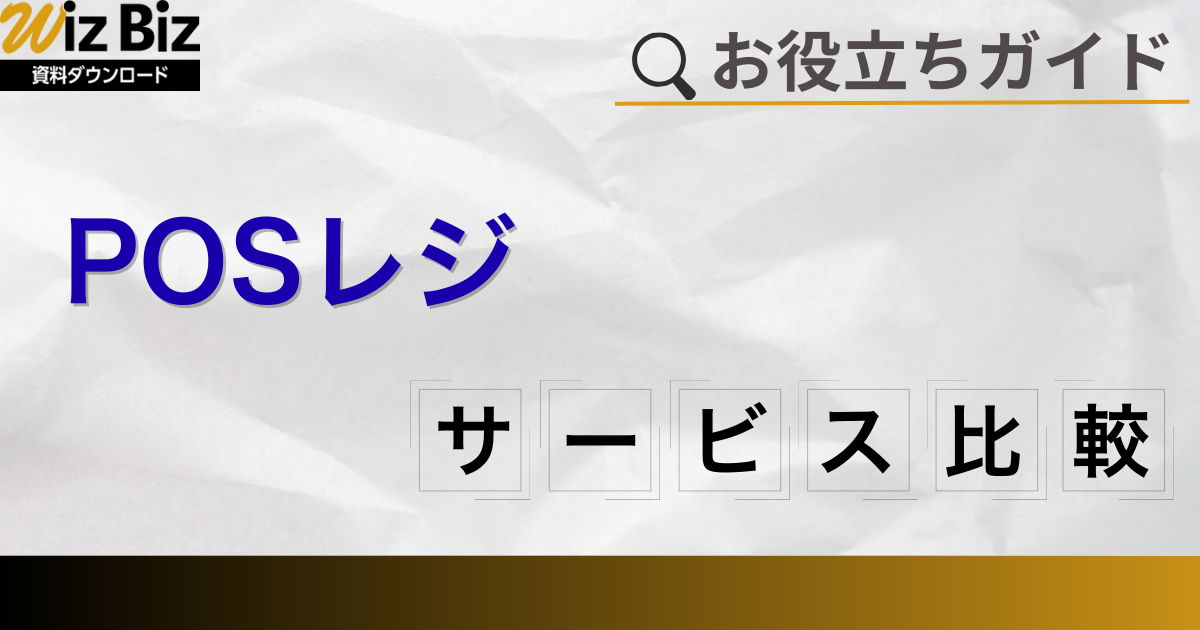
おすすめサービス

ダウンロード候補に
追加しました!

削除しました